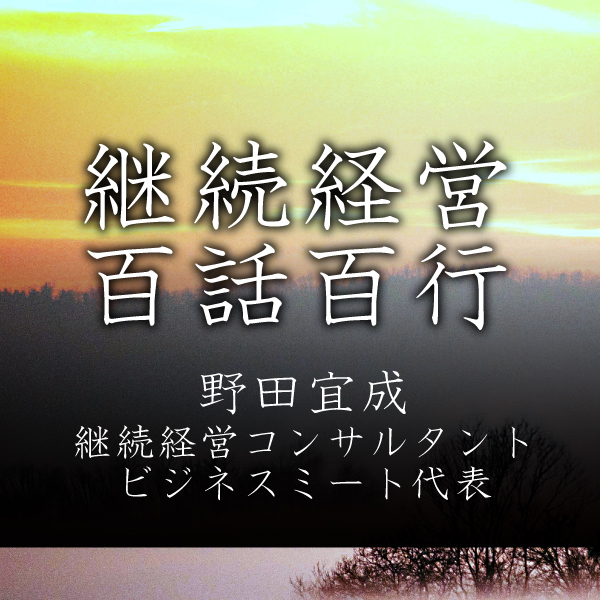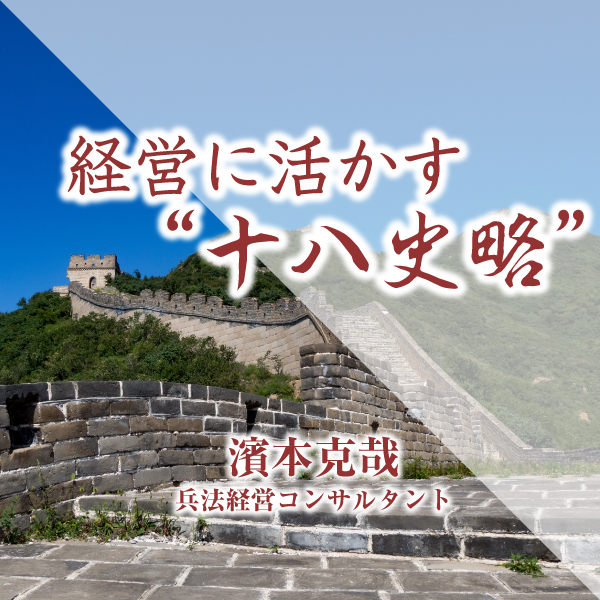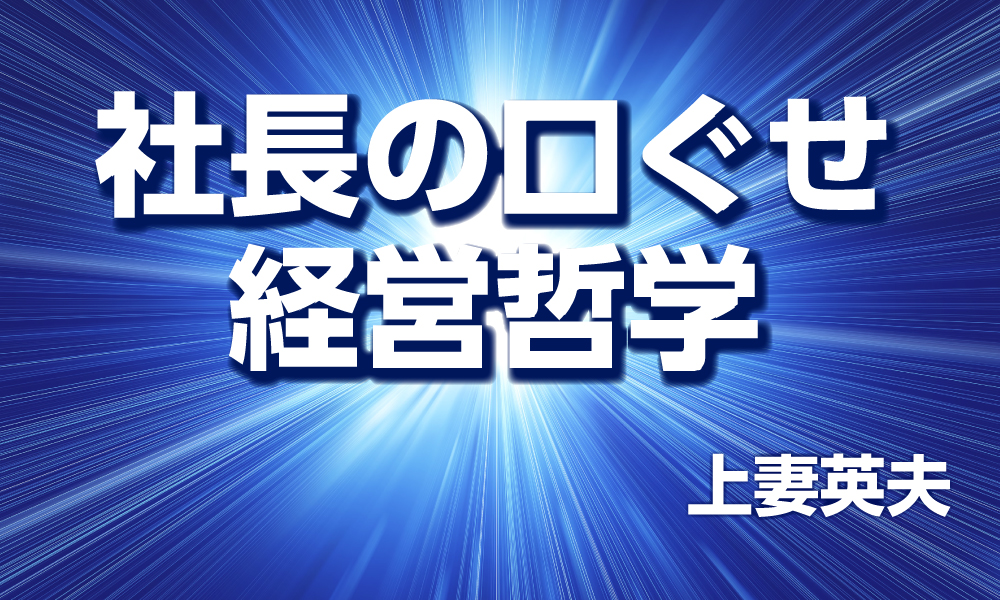1986年(昭和61年)11月21日夕、
「噴火した伊豆大島・三原山の溶岩が元町の市街地に迫っている」
官邸に危機対応を集中する「危機管理センター」
後藤田は、国土庁からの報告を待ったが、ナシのつぶてだ。
「どうなってる。国土庁は何をしている」。後藤田は、
「溶岩が海に流れ込めば大規模な水蒸気爆発で住民は全滅だ。
国土庁を叱っても始まらない。「役所の慣例などどうでもいい。
首相・中曽根康弘の裁可を得て官邸主導で救出作戦が始まった。
「合わせて甲板に何人収容できるんだ」「現在38隻で、
溶岩到着が先か、脱出が先か、事態は一刻を争った。
「どこへ向かっている?」「最寄りの伊豆半島です」「
東京都民である島民を他県に避難させては、
国土庁の長い会議が終わったのは、この日の午後11時45分。
危機への対応は時間勝負である。
トップが決断して、ナンバー2が裁量をふるう。いや、時には、
それができない組織がなんと多いことか。
(この項、次回に続く)
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考文献
『重大事件に学ぶ「危機管理」』佐々淳行著 文春文庫
『政治とは何か』後藤田正晴著 講談社