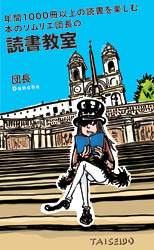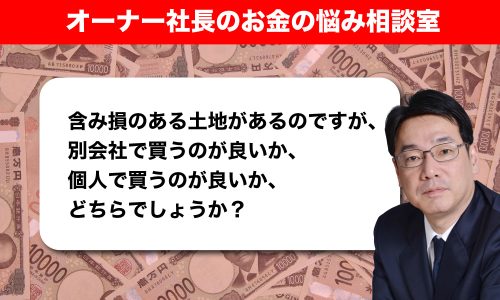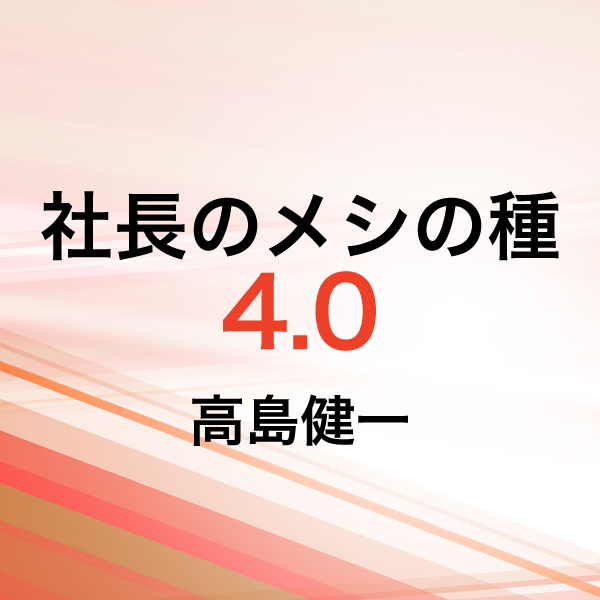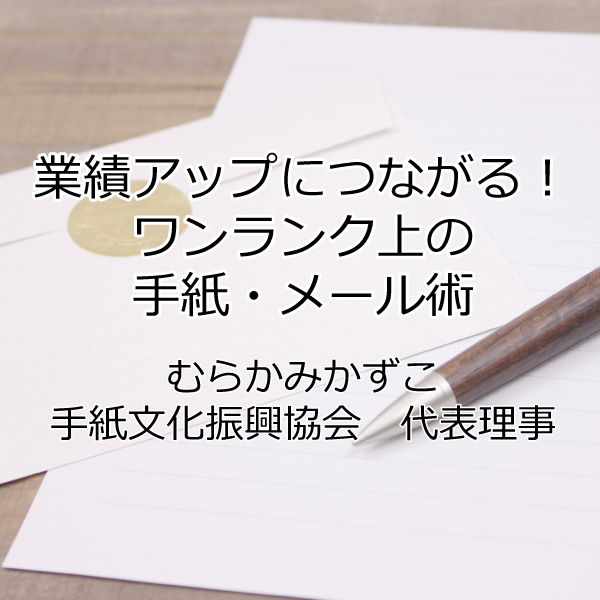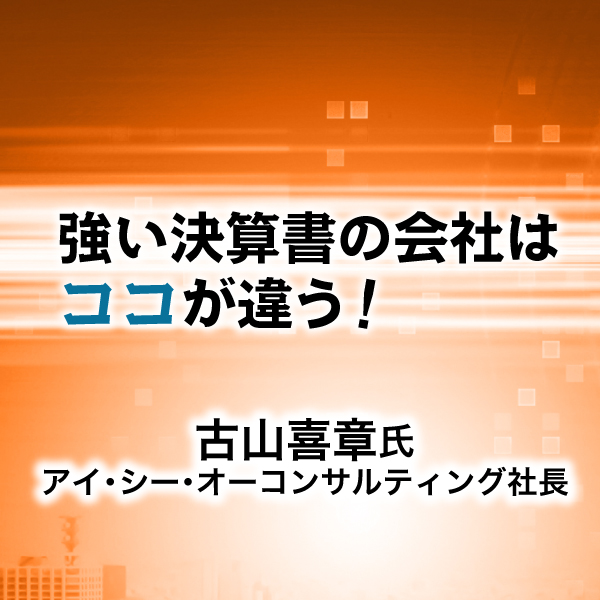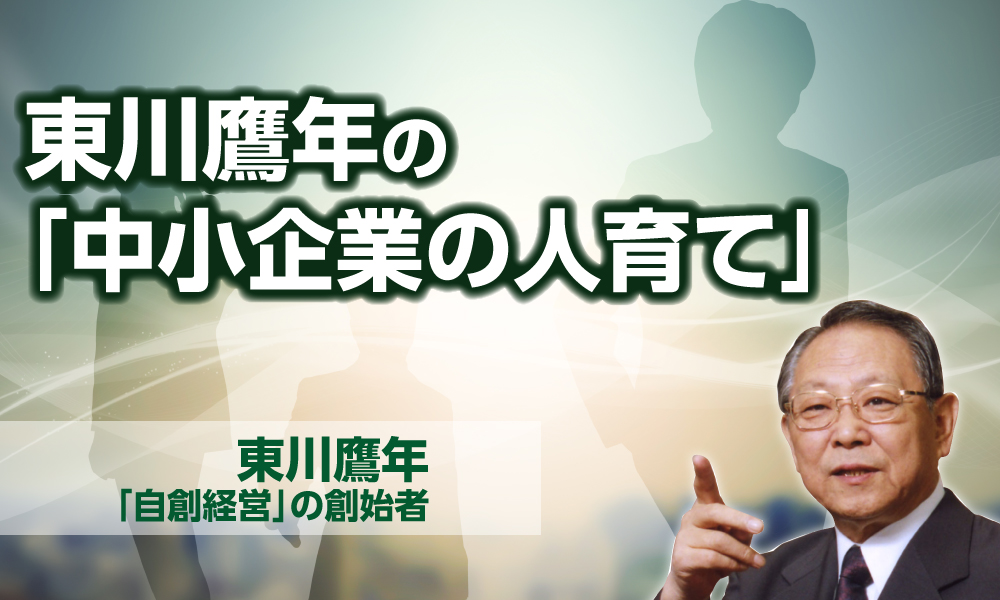- ホーム
- 指導者たる者かくあるべし
- 逆転の発想(11) 論語(道徳)と算盤(強欲)を両立せよ(渋沢栄一)
富貴を求める人間の本性を肯定
明治から昭和にかけて活躍した実業家で、「日本資本主義の父」と呼ばれる渋沢栄一が今、注目を浴びている。ともすれば、カネ、カネ、カネの拝金主義がまかり通る現在の資本主義社会は、富の偏在が全世界的に大きな社会格差を拡大させ社会問題になっている。
ソビエト・ロシアを盟主とするアンチ資本主義としての社会主義の実験は失敗に終わり、近代社会は行き詰まった資本主義に代わる新たな社会運営システムを求めている。そこで渋沢栄一である。
現在の埼玉県深谷市の豪農の家に生まれた渋沢は、藍玉(染料材料)取引の家業に携わった幼い頃から金勘定が身に染み付いている。そして論語を学び、徳川一橋家に仕官して幕末に欧州に留学し、近代社会の金融システムを学んだ。まさに論語と算盤をともに学ぶ青春時代が、彼独特の複線の思考をはぐくんだと言える。
「士農工商」に現れている商人・利殖蔑視の江戸時代の武士思想の誤りは、「論語」の誤読にあると強調する渋沢は、論語が説く次の一節の誤解は甚だしいと言う。
〈富と貴(たっと)きはこれ人の欲するところなり。その道をもってせずしてこれを得れば処(お)らざるなり〉(金銭蓄積と社会的名誉は、人の求めるところだ。しかし道義を踏みはずしての富貴は、私=孔子は求めない)
この一節を「だから、商行為は卑しい」と論語読みは教えたが、渋沢の理解は違った。
「孔子は、倫理の伴わない金儲けを諫めたのであって、金儲け自体は人間の本性として認めている」と。人間の持つその本性こそ社会発展の基礎にある、というのが渋沢の理解だ。「武士は食わねど高楊枝」という武士の常識からの脱却、逆転の発想だった。
今言えば当たり前だが、こうした常識は容易に離れることは難しい。渋沢は、明治維新という時代の転換点で、その後も権力を握る武士階層に蔓延する迷妄を吹き払ったのである。
人間の持つ強欲が社会の発展動力というのは、資本主義理解の根本であるが、渋沢の興味は、そのコントロールの原理に向かう。
武士道と商道
一方で彼は、同じ誤解は商売人側にもあると指摘している。武士道の行動原理は正義、廉直、義侠、礼儀、謙譲であるが、そんな気風は商売人にとって禁物で、「それじゃ商売は成り立たない」と彼らは敬遠してきたと警告している。武士道と殖産功利は矛盾せず、かえって相補うべきだという思想が彼の根本にある。
〈西洋の商工業者は互いに個人間の約束を尊重し、損益を超えて約束を守る。しかるに、我が日本における商工業者、なおいまだ旧来の慣習を全く脱することができず、ややもすれば道徳的観念を無視して、一時の利に走らんとする傾向があって困る〉と嘆く。
明治維新から半世紀、「論語と算盤」が書かれた1916年(大正5年)にしてこのありさまだった。倫理なき商道への警告である。西洋の商道徳の基盤に宗教(キリスト教)倫理があると見抜いた渋沢は、書架から「論語」の埃を払って据えようとしたのだろう。
よく集め、よく散ぜよ
日本近代化のとば口で、第一国立銀行、証券取引所の創設、紡績、鉄道、セメント会社など数々の企業の創立に奔走した実業家としての渋沢の、さらなる功績は、企業の社会貢献の実践だった。
まだまだ社会的地位の低かった女子の教育機関をつくり、貧窮家庭の子供たちを育てる養育院を開設するなど、活動は幅広い。
彼は商業人に向かって言う。「よく集め、よく散ぜよ」と。
〈自分がこんなに資産家になれたのは社会の恩だと自覚せよ。だから社会の救済、公共事業に対して常に率先して尽くすようにすれば、社会は倍々健全になる。同時に自分の資産運用も益々健実になる〉
それを忘れて、富豪が社会を無視し、社会を離れて富を維持し得るがごとく考え、公共事業、社会事業を捨てて顧みなかったならば、ここに富豪と市民との間に衝突が起きて結局、不利益を招く。
〈富を造るという一面には、常に社会的恩誼あるを思い、徳義上の義務として社会に尽くすことを忘れてはならぬ〉
いやいや、うちなんか中小企業でギリギリの経営状態だから、と言い訳するなかれ。渋沢が問うのは企業家としての心構えとともに、「何のために生きているか」という人生観の問題なのだ。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考文献
『論語と算盤』渋沢栄一著 角川ソフィア文庫
『渋沢百訓』渋沢栄一著 角川ソフィア文庫