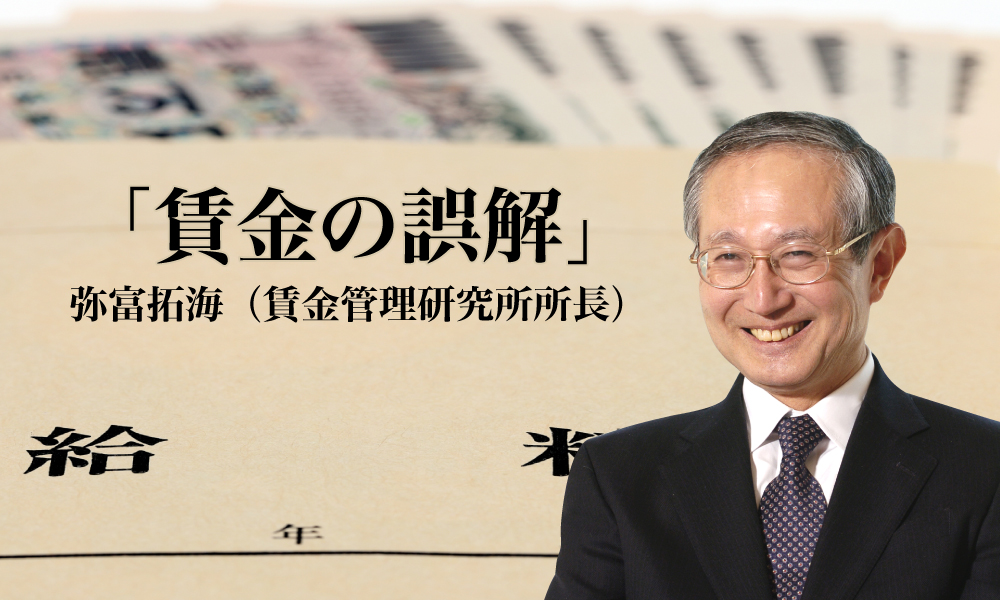お追従(ついしょう)はトップの自己愛につけ込む
組織のトップに就くほどの人物ならば、だれしも自分の判断と手腕に絶対の自信を持っている。部下にとって、自信満々のトップに逆らうのはリスクを伴うから、まわりには追従者たちが群がってくる。そこに落とし穴がある。
マキアヴェッリは、「君主(リーダー)がまぬがれがたい失政について論じたい」として次のように指摘している。
〈その失政とは、君主がよほど思慮に富むか、人選に当を得なければ、なかなか避けがたい。それは宮廷にざらに見かけるお追従者のことである〉
一般民衆(社員)ならば、トップの意向に従順である方が統治しやすいが、宮廷(幹部会)がイエスマンで占められてしまっては、重大局面で判断に多様性がなくなり、ともすれば誤った決断に導かれてしまう。側近を置く意味もなくなってしまう。当然のことなのだが、往々にして側近の媚(こ)びへつらいの甘言はトップの耳に心地よく響くからやっかいだ。さらにお追従(ついしょう)は、側近たちの間でわれもわれもと競い合うように忠誠合戦を起こし、判断機関としての幹部会を無能化してしまう。それはまるでペスト(伝染病)のようにまたたく間に広がる。
〈人間は自分のこととなると、じつに身びいきなものであって、この点をつかれると人にだまされやすいから、このペスト禍から身を守るのはむずかしい〉
よほど注意してかからないと、媚(こ)びへつらいという伝染病は、リーダーの自己愛に寄生し増殖してしまう。
かつての敵対者こそ使える
では新たに組織、企業の長に就いたとして、幹部会の側近をどう選べばいいのだろうか。常識的には、自分を支持しつづけてくれた重役や忠実な部下たちを登用することになるのだが、マキアヴェッリの意見を聞いてみよう。
〈君主、それもとくに新君主が経験するのは、政権の当初に疑わしく見えた人物のほうが、初めから信頼していた者より忠誠心が深く、より役に立つことである〉
トップの座にのぼる過程で当初、敵意を抱いていた者も、新政権が確定すると、いずれ生活のために頼るツテを必要とする。〈だから彼らの気持ちをつかむ気になれば、いつだって容易にできよう〉。しかも彼らは、登用されれば悪評を打ち消そうと忠勤に励む。従来からリーダーの覚えがめでたいことにあぐらをかいて、安穏と組織生活を全(まっと)うしようという者より有用だ、と彼は言う。
逆転の発想だ。もちろん、登用する人物が信頼に足りるかどうか的確に把握してかかる必要はあるが。
トップの決断と助言
媚(こ)びへつらうことなく直言してくれる側近を得たとしよう。彼らの助言を生かす方法についてもマキアヴェッリは触れている。
〈君主は諸般の事項について、彼らだけに諮問し、その意見を聴き、その後は自分がひとりで思い通りに決断をくださなければならない。君主自身の決断をかならず守り、その決断を貫くことである〉
信頼に足る側近を得たとしても、彼らに判断と決断をただ任せるのではない。トップ自身が必要な事柄についてのみ意見を聴き、その助言をもとに自らが決断を下し、出た結論はトップの決断として、揺るがず堅持する。
その責任感があってこそ、部下はリーダーに対して絶対の信頼と尊敬を寄せるのである。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考文献
『君主論』ニッコロ・マキアヴェッリ著 佐々木毅全訳注 講談社学術文庫
『マキアヴェッリ語録』塩野七生著 新潮文庫