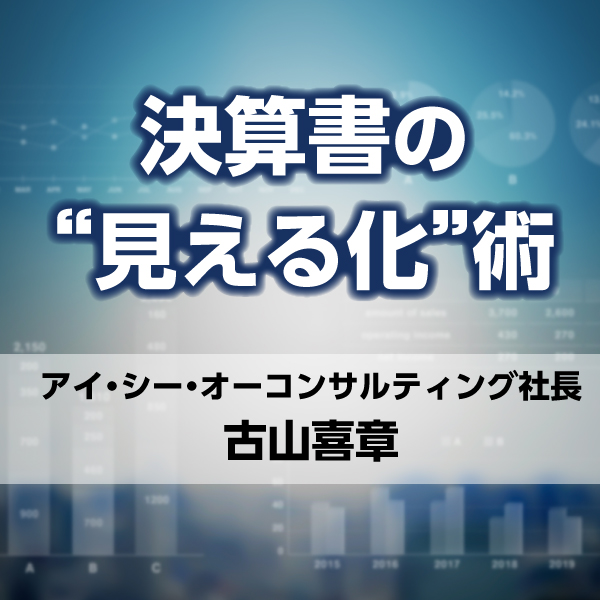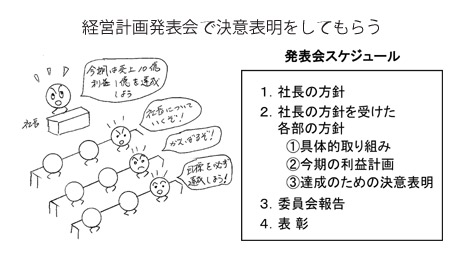- ホーム
- 指導者たる者かくあるべし
- 挑戦の決断(17)売られた喧嘩は買う(河井継之助)
「薩長に義はない」
明治維新を決定づけた戊辰戦争の激戦というと、会津若松城をめぐる会津戦争と五稜郭に立てこもった旧幕府軍が最期を遂げた箱館戦争を多い浮かべるが、新政府軍を最も手こずらせた戦いは、越後長岡城をめぐる北越戦争であった。
朝敵とみなされた長岡藩の家老として四か月に及ぶ戦いを指揮した河井継之助(かわい・つぎのすけ)が決断したのは、領民保全のための止むにやまれぬ戦いである。
継之助が家老に就任したのは、1967年(慶応3年)7月のことだった。薩摩・長州両藩は倒幕クーデターを画策し政治を取り巻く情勢は混沌としていた。佐幕派の継之助としても、現状の幕藩体制では新時代に適応できないことは痛感していた。しかし薩長両藩が目指すのは、幼帝を操っての幕府勢力一掃の体勢転覆であり、日本が内乱に突入することを危惧していた。
果たして薩長は公家と謀って大政奉還のクーデターを強行し、戦争を仕掛けてきた。
「尊王攘夷」を錦の御旗に開国を決断した幕府の追い落としを謀ってきた革命勢力だが、「世の流れは開国でなければならない」と考える継之助には、「尊王」と「攘夷」という異質の論理の結合はご都合主義としか見えない。
「大政奉還」で徳川家を将軍職から追い落とすと、幕府・朝廷の間の妥協を模索する「公武合体」論は消え、薩長を中心に幕府勢力一掃の戦いの準備が進められる。
無益の戦争を避けるために
継之助は行動の人であった。江戸表に詰めていた彼は、主君・牧野忠訓(ただくに)とともに、「歩いては間に合わぬ」と急ぎ海路で上洛する。朝廷に直訴するためである。
御所に入り、面会に応じた下級の公家に、「このままでは戦乱となり、万民は塗炭の苦しみを得ることになる」と建白書を出したが、何の反応もなく追い返された。
長岡藩は譜代の家柄、朝敵とされ討伐を受けることは不可避と見た継之助は、横浜の外国商人から最新鋭の武器を調達し、長岡へ引き返す。新政府軍は、北陸道と東山道から江戸を目指し、途上、山縣有朋(やまがた・ありとも)を総帥に越後攻略に取り掛かっていた。
その要衝は長岡だった。山縣軍は、およそ20キロ南の小千谷(おじや)を占拠し、隣国の会津藩兵も山を越えて越後に進駐し、両軍がにらみあう。継之助の願いは「中立不戦」であった。奥羽越列藩同盟の一員として佐幕の立場は変えられないが、越後の領民を無益な戦いに巻き込むわけにはいかない。行動の人は単身、談判のため小千谷に乗り込む。
山縣は不在を決め込んだ。応対にでた新政府軍監は、「無血開城」を申し入れる継之助を、「今さら何を言うか」と追い返す。
そもそも、新政府軍、とりわけ山縣の敵は会津である。北越戦争そのものが、会津を叩くための戦いである。京都守護職を務め勤皇の志士たちを弾圧した会津藩への私憤であり、無益な私戦の色彩が濃い。継之助は、会津と新政府軍の仲介を試みたが失敗したことで戦いの決意を固めることになる。領民を守るために。売られた喧嘩を買わざるをえないこともある。
武士の魂に殉じる
小千谷談判(5月)の後、継之助はわずか1,300の藩兵を率いて善戦する。戦いのプロである山縣も大苦戦を強いられる。長岡の兵は一時失った長岡城を継之助が銃撃で重傷を負いながらも先頭を切って奇襲し奪還する。新政府軍は占領地の住家に火を放つなどし領民の反感を買っていたから、継之助が戻ってきたと知るや城下は歓呼の声に包まれお祭り騒ぎとなった。
不戦から戦いへと決断した継之助の戦いは、もはや武士の本分に基づき領民守護の鬼としての戦いであった。7月29日、長岡の城は再び陥落し、彼は会津へ落ち延びる途中で銃撃の傷が悪化し世を去る。
死を前に、会津に避難した藩主忠訓に伝えくれと義兄に手紙を書いた。
「やむなく開戦に踏み切ったるは、不義の汚名を後世に残すよりは、義理を守るべきと決断したるもの。されど残念至極の結果のほど誠に申し訳なし」
新政府は予想以上の苦戦を強いられた北越戦争については多くを語らない。そして戊辰戦争そのものを正義の戦いとして語り継ぐ。勝者の歴史のみでは真実はわからない。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考文献
『武士道の英雄 河井継之助』星亮一著 さくら舎
『日本の歴史20 明治維新』井上清著 中公文庫