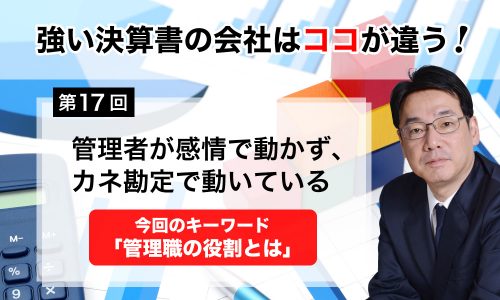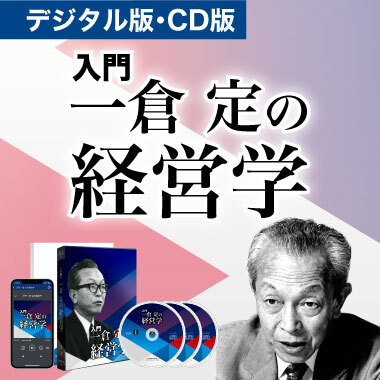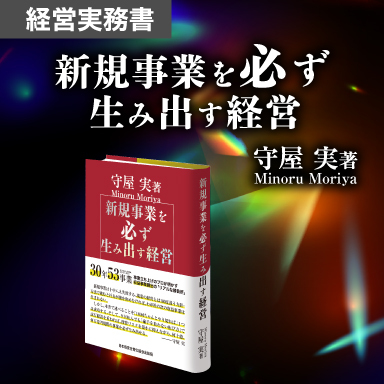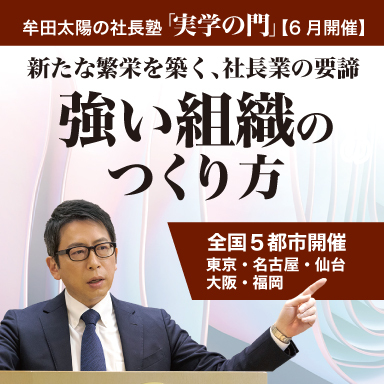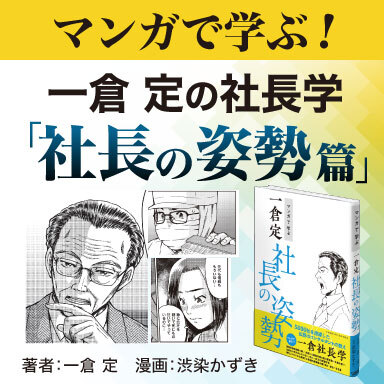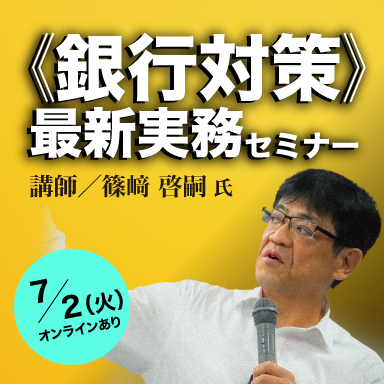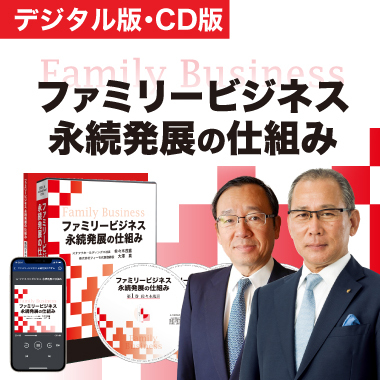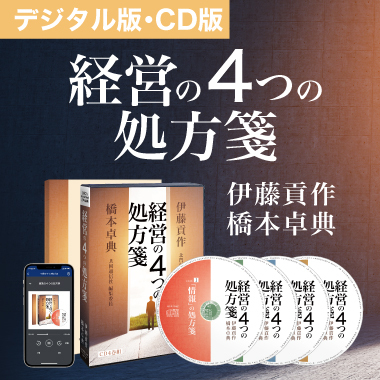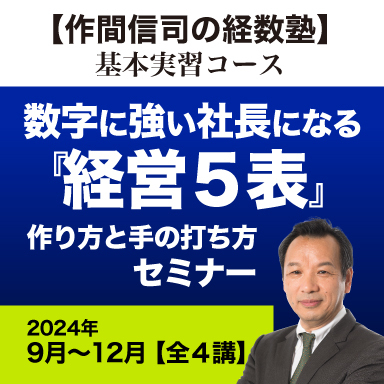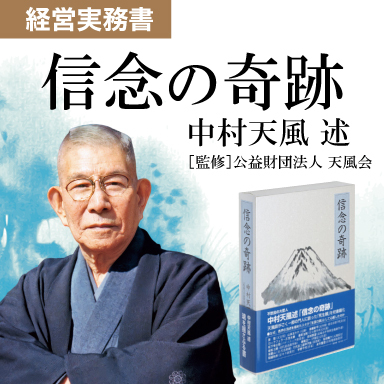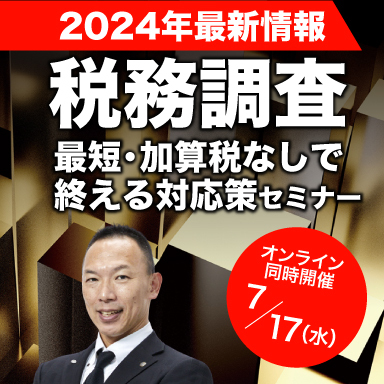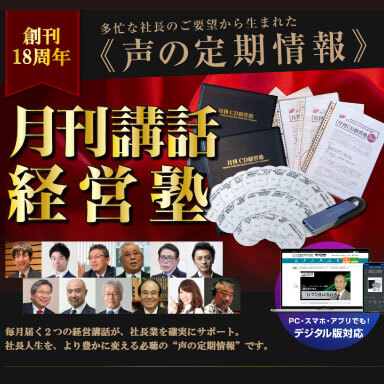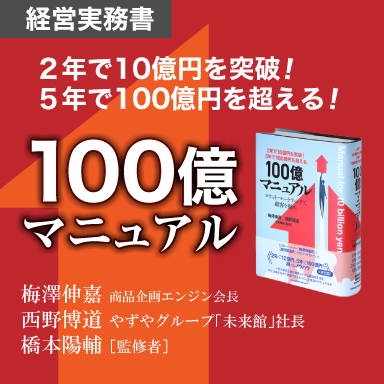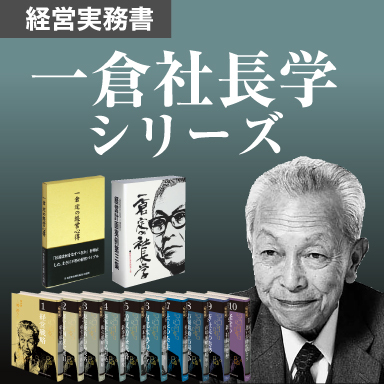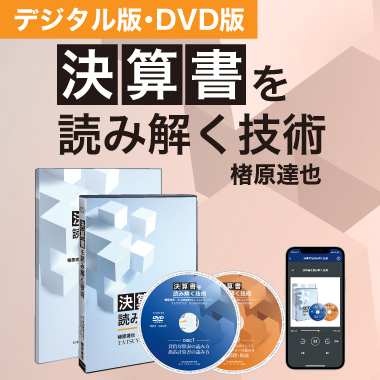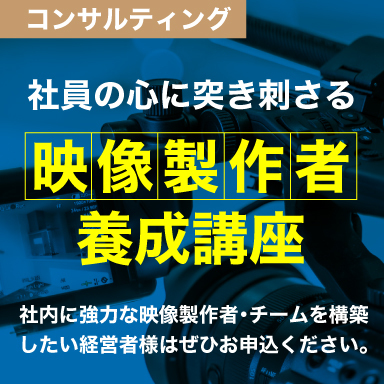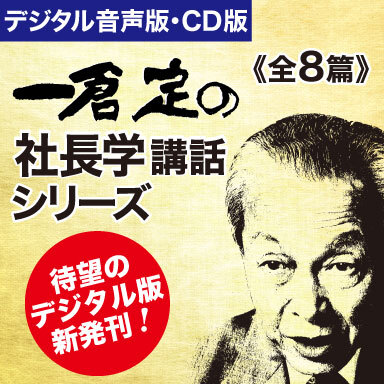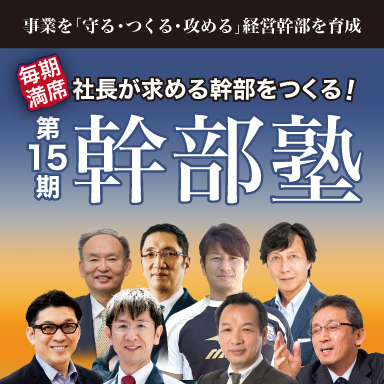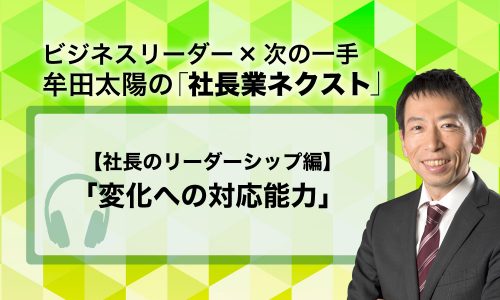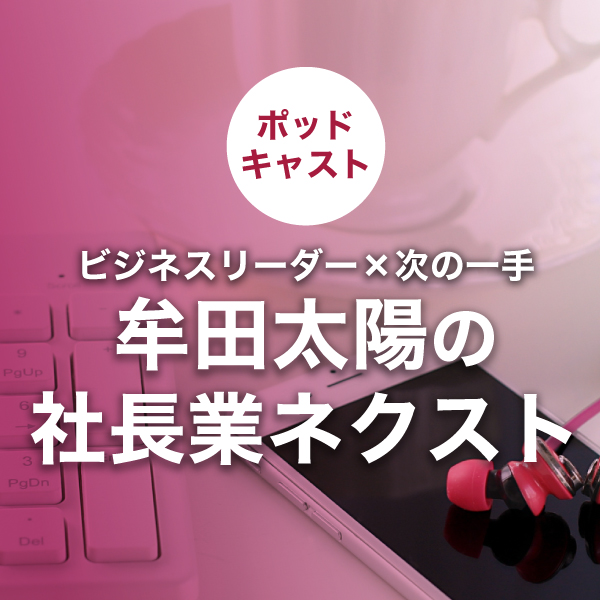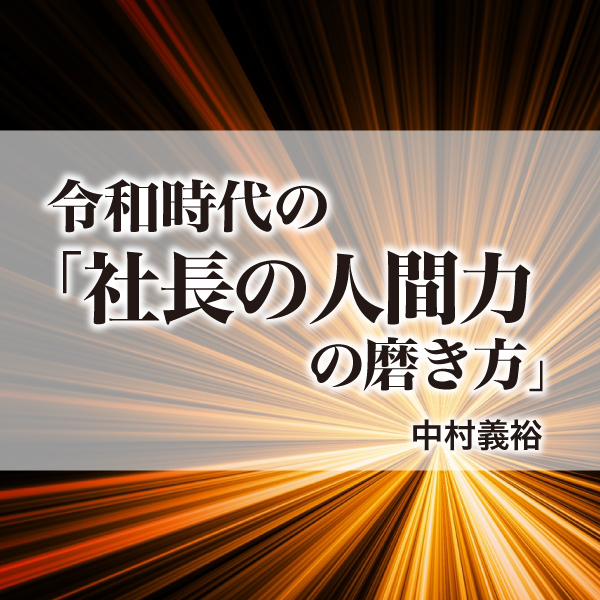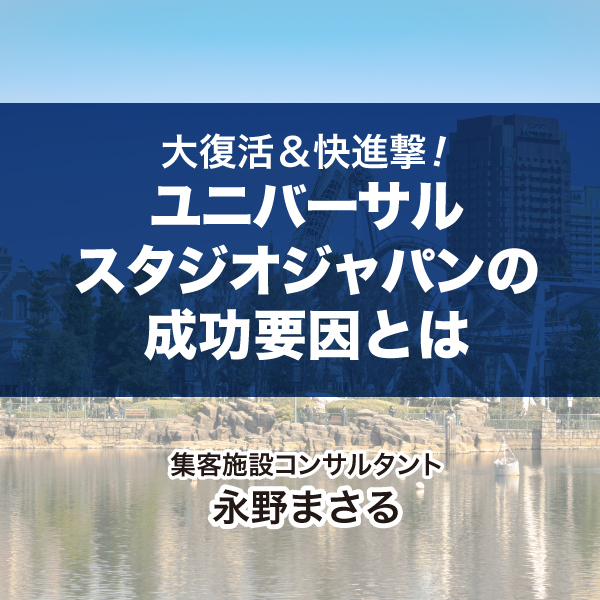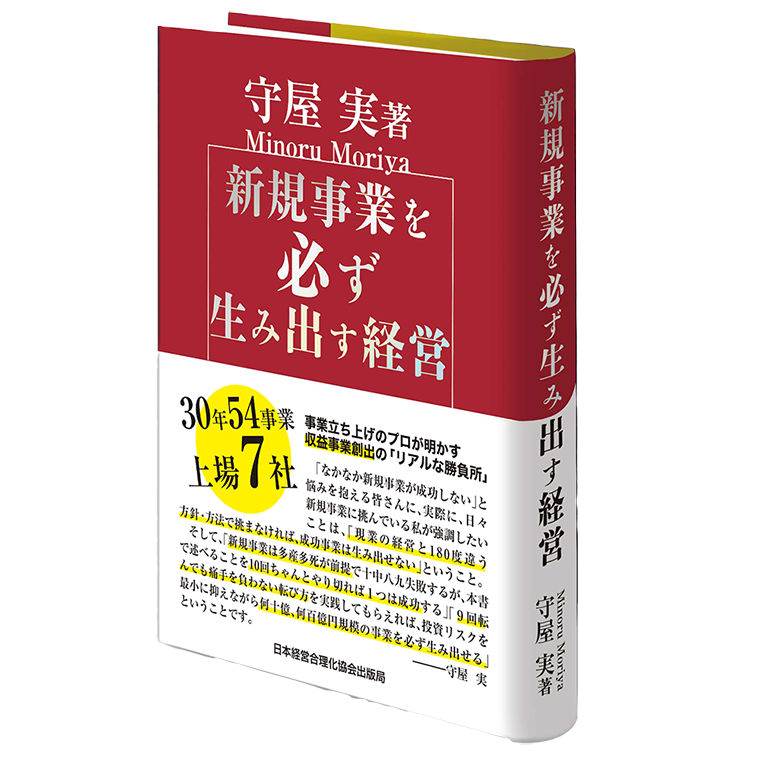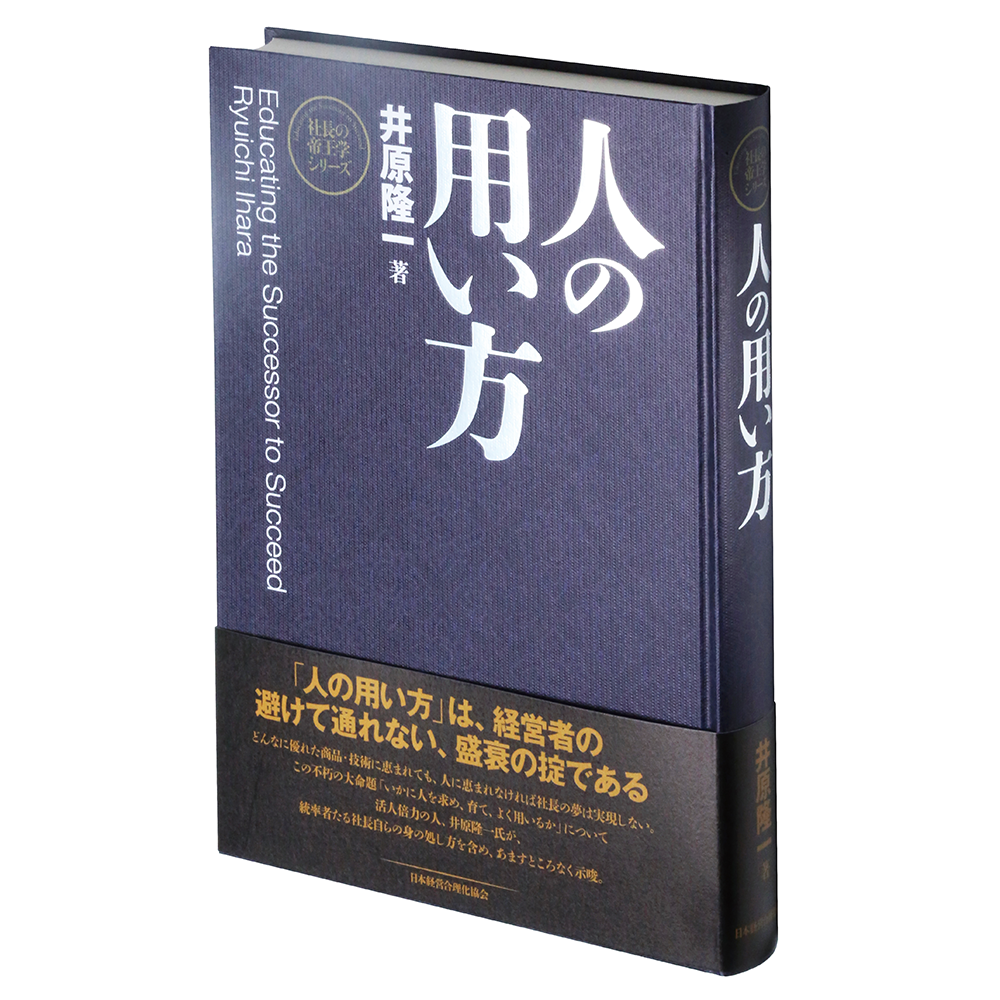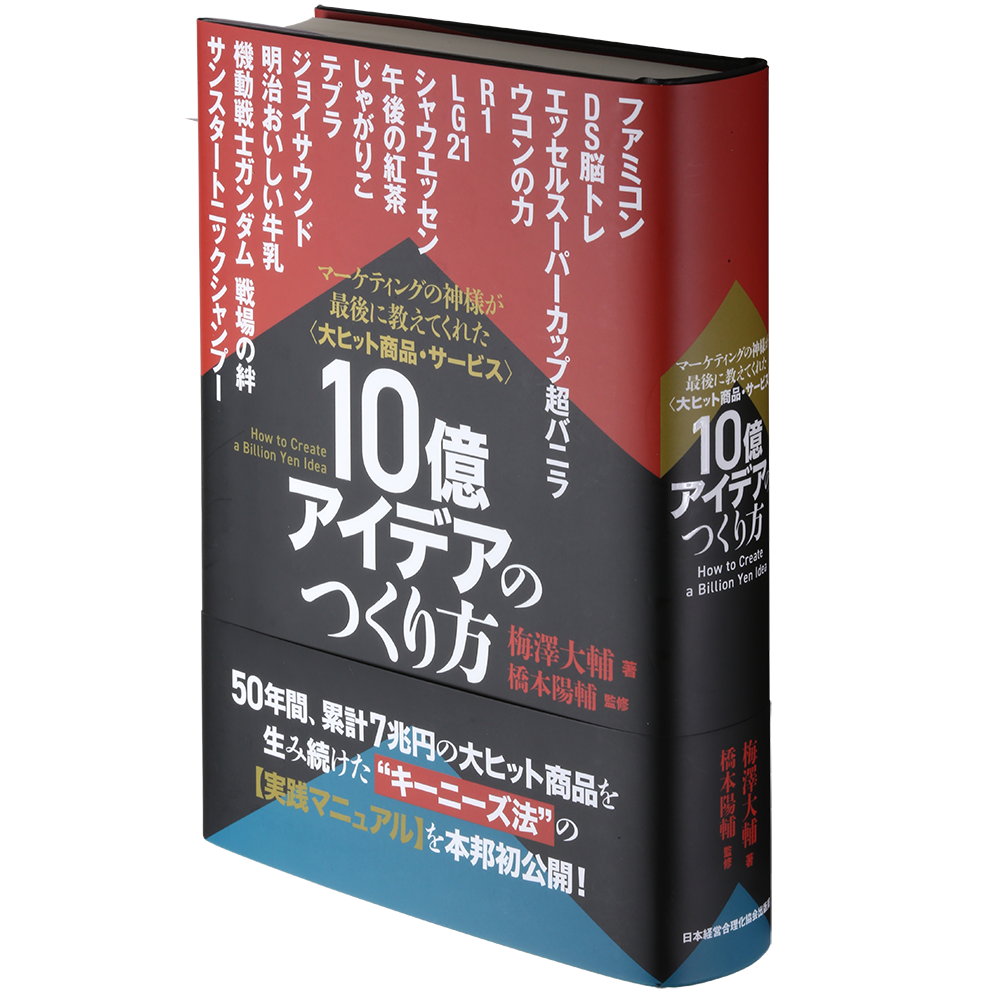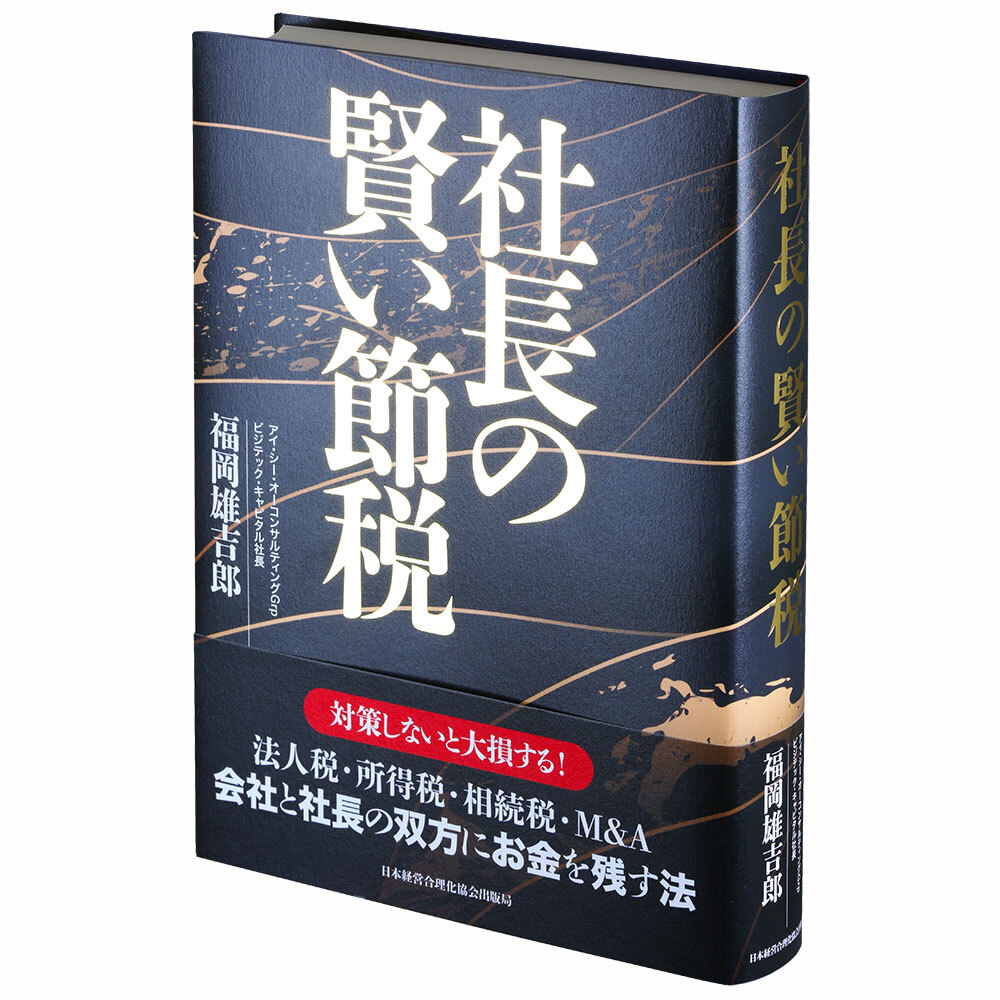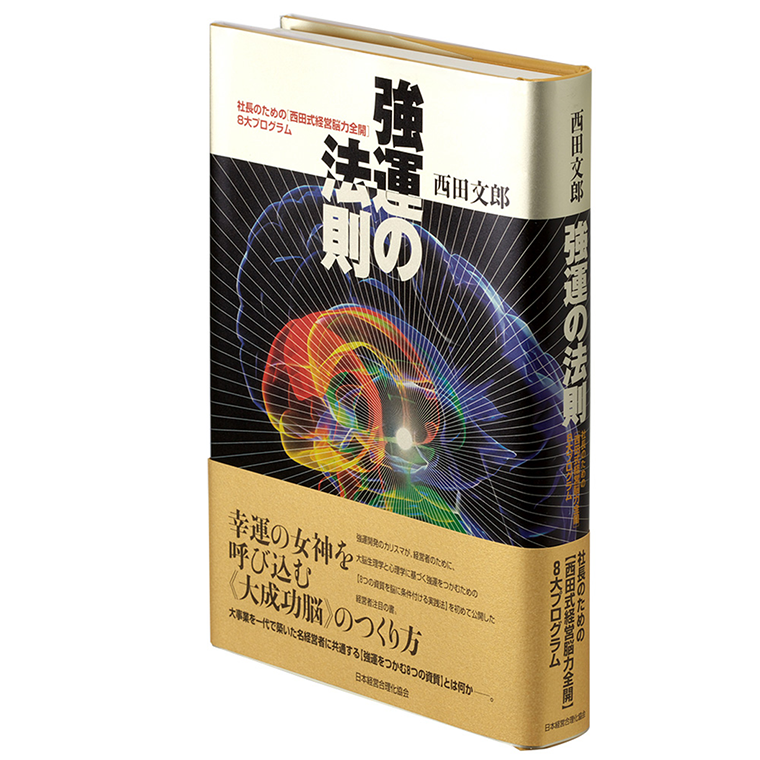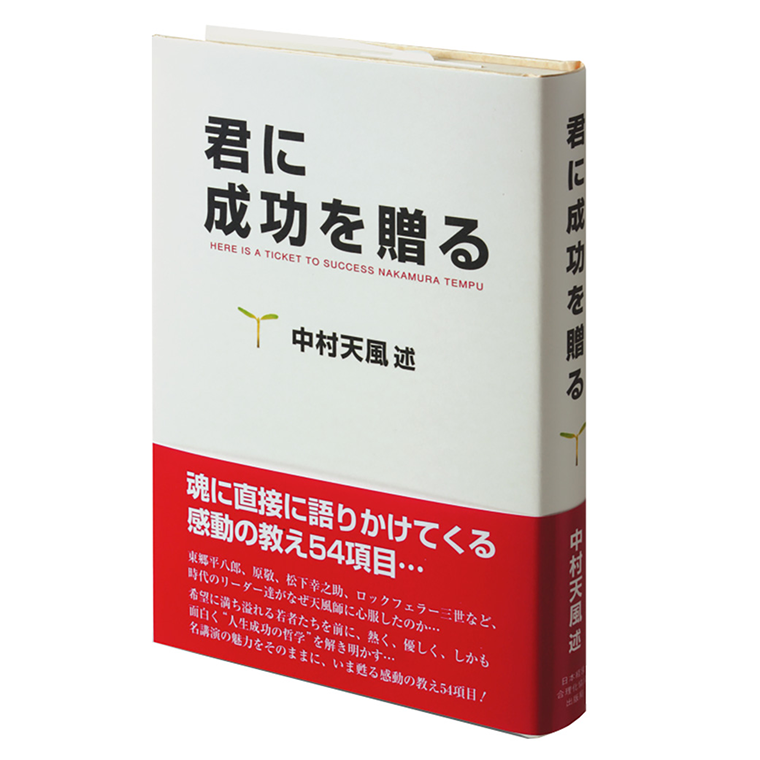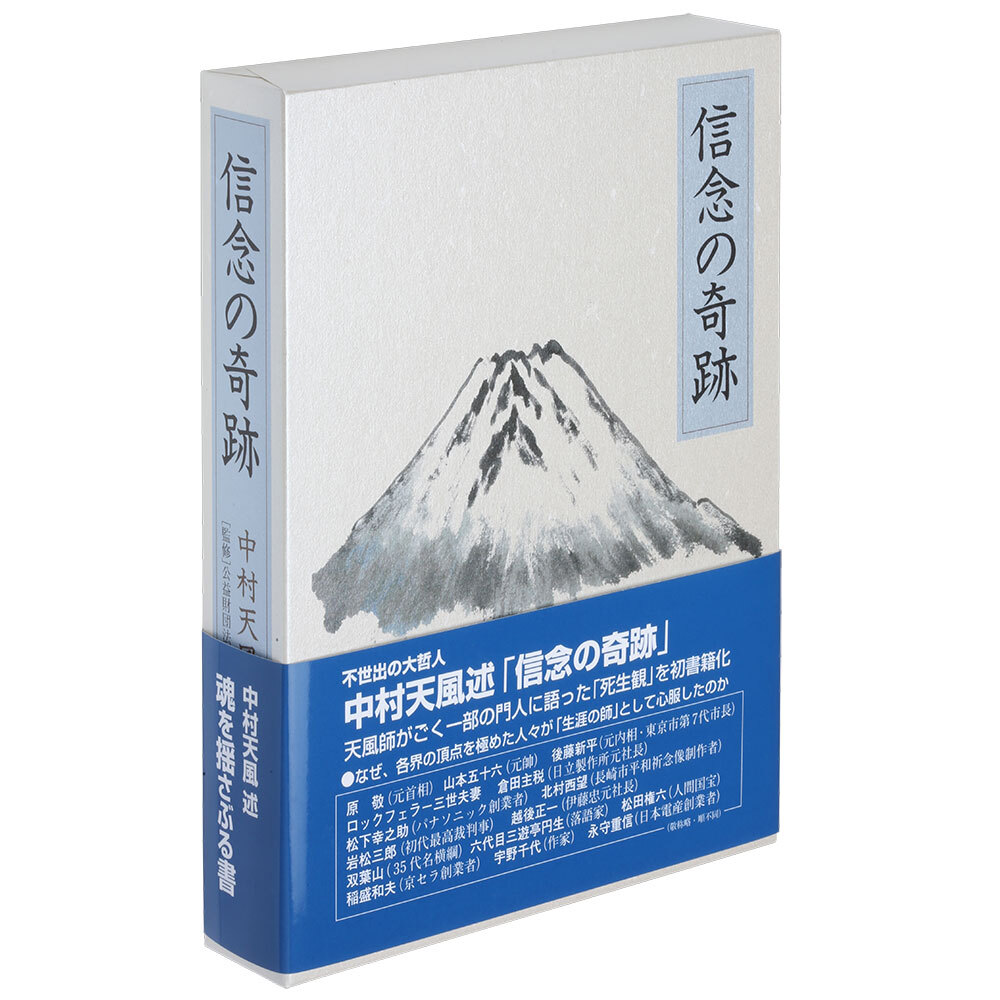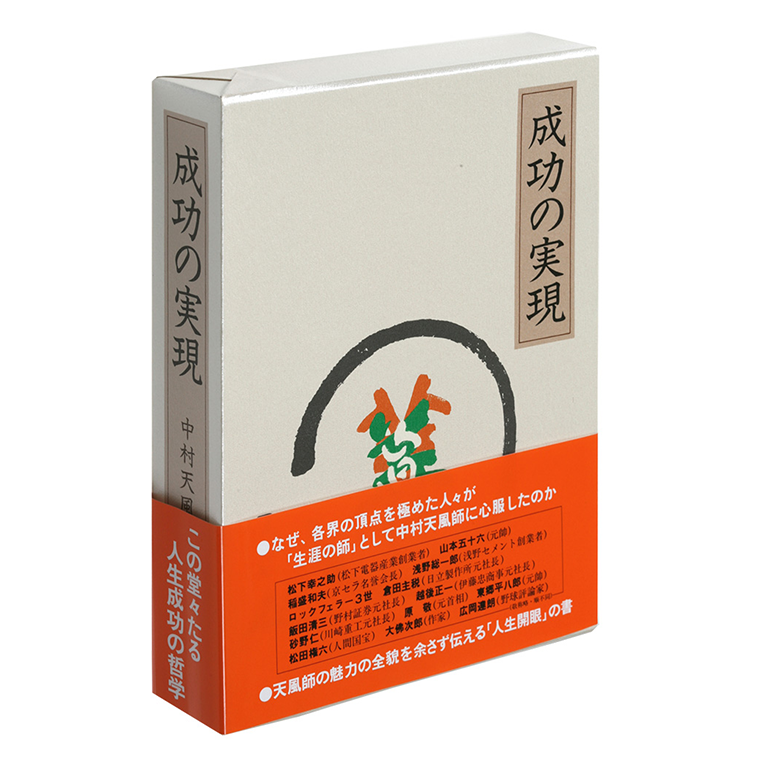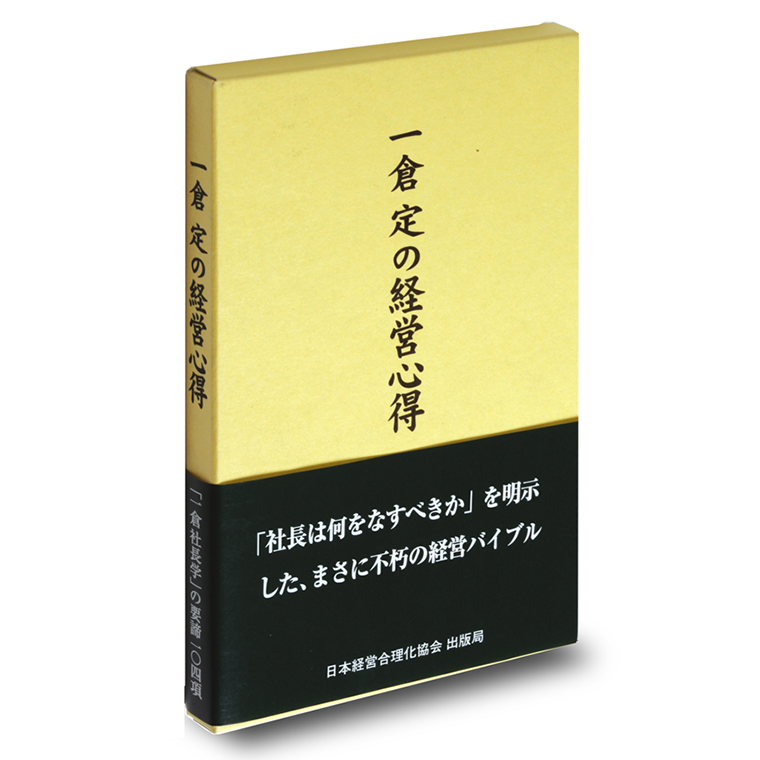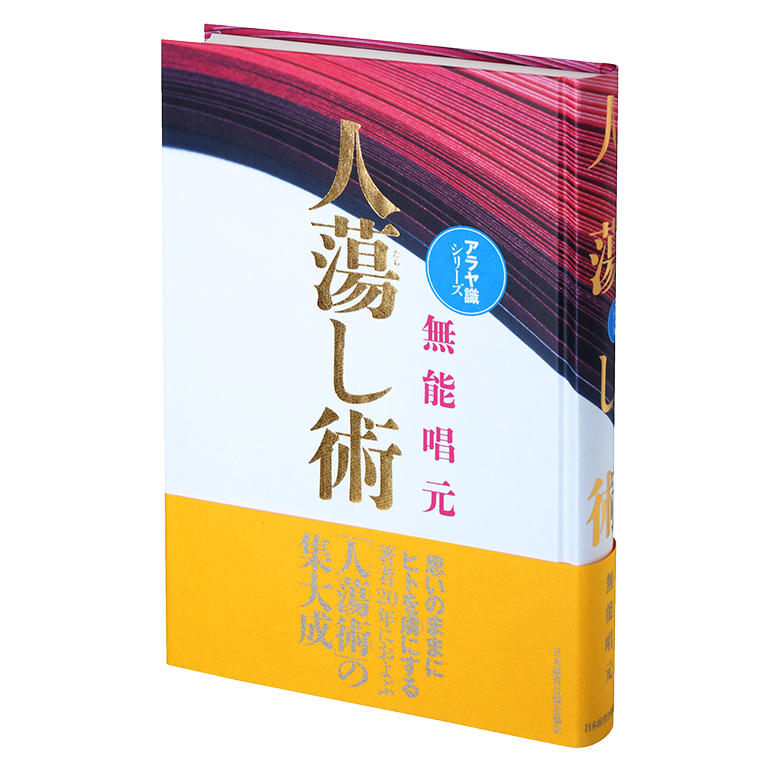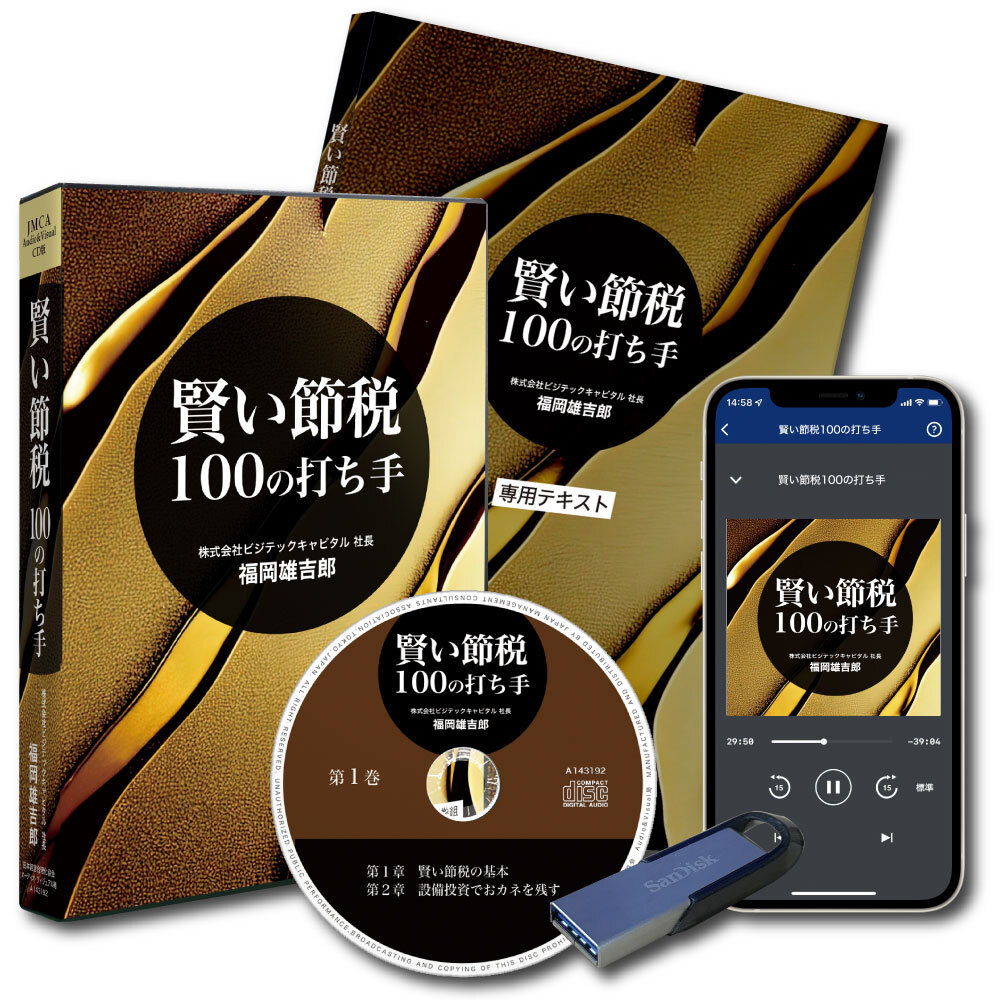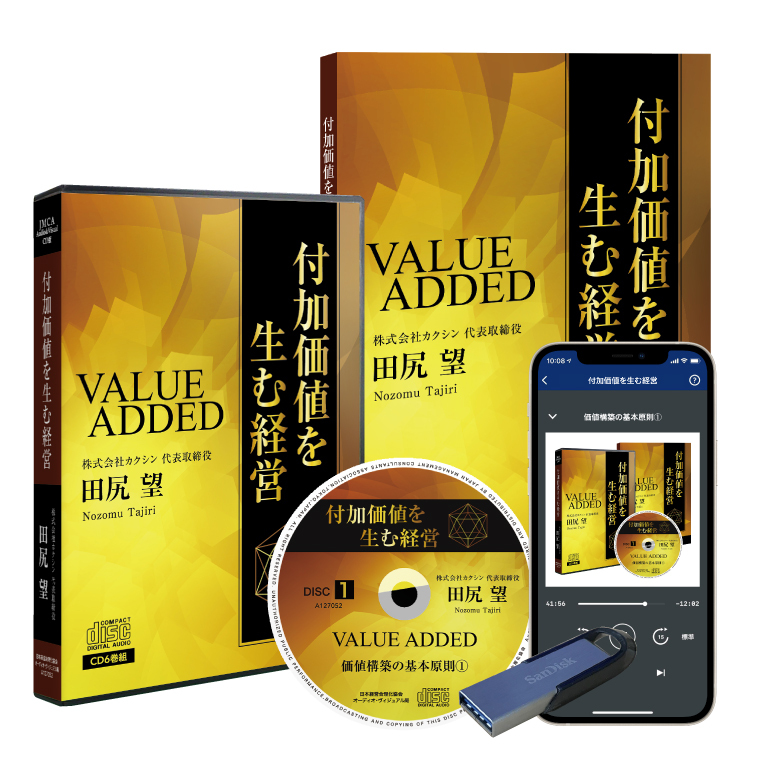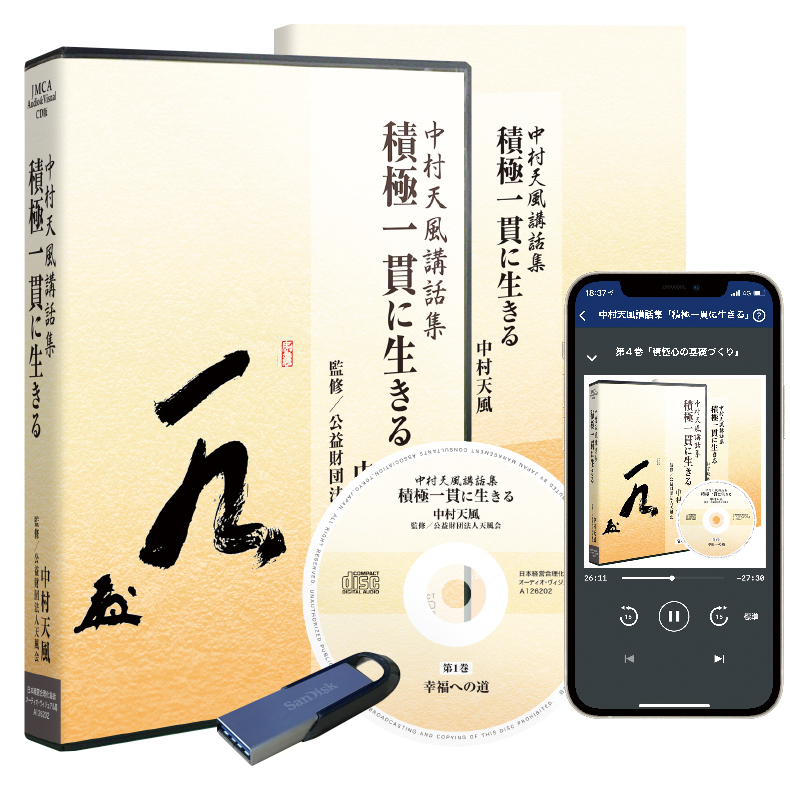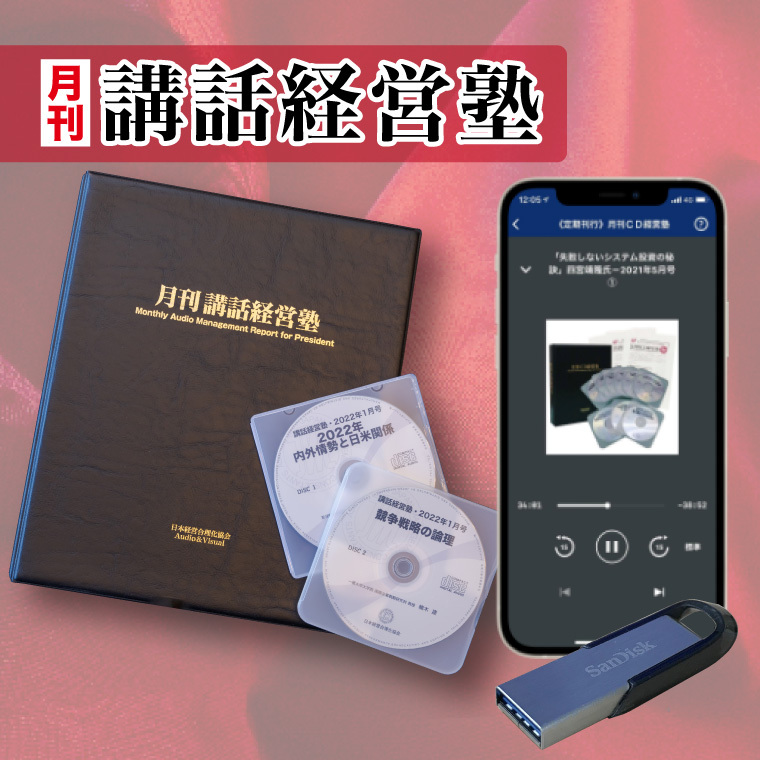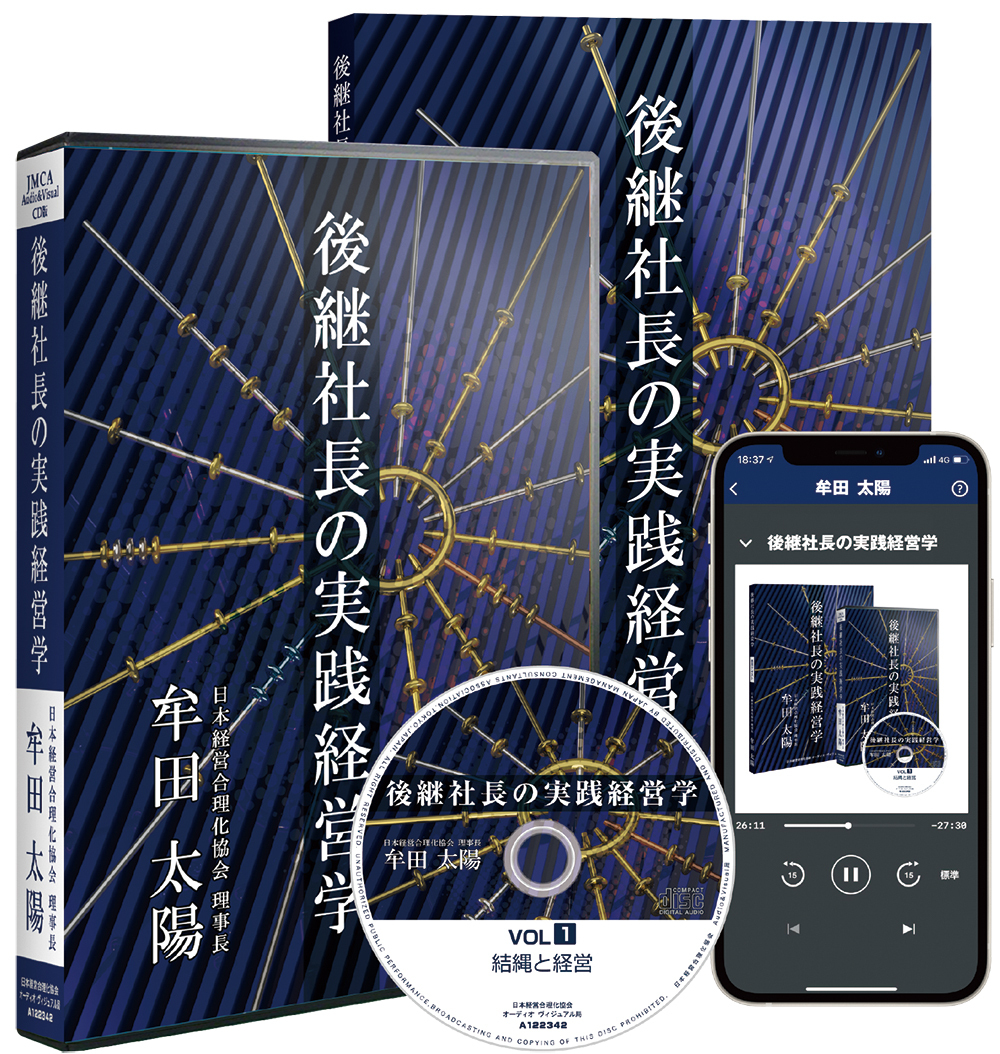2.コミュニケーション能力
「チャーチルが後年書き残した回顧録『第二次世界大戦』は、ノーベル文学賞を受賞している。『ガリア戦記』を書き残した古代ローマのカエサルもそうだが、危機の政治家はえてして書くことに長けている。それは名文家ということを意味しない。演説あるいは文章を通じて人を動かすことができる能力だ。自らの明確な目的意識を、部下に、仲間に正確に伝え、動かすコミュニケーション能力に長じていることを意味する。
コミュニケーション能力といっても、文章力だけではない。その存在を効果的に露出することによって、国家、あるいは組織のリーダーシップがどこにあるのかを示すことも重要だ。
チャーチルは、戦時中、忙しい戦争指揮の合間を縫って街頭に姿を現した。ドイツによる爆撃があれば、硝煙漂う中でも危険を顧みず現場を訪ね、国民を励まし鼓舞した。ロンドンのスラムに住む市民たちも、現場に顔を出すまったく身分も違う貴族のチャーチルを、「ウィニー爺さん」と呼んで慕い、ともに戦争に耐える決意を一つにした。
あるいは、戦況が厳しい中でも積極的に同盟国首脳との外交の場に顔を出す。会談のニュース映像を通じて、戦い遂行の意志を国民に伝えた。こうした露出は、国民に安心感を与え、継戦の意志を共有することに繋がる。
チャーチルの行動を列挙すれば、ウクライナ大統領のゼレンスキーがチャーチルの見せた危機リーダーシップの忠実な継承者であることが分かるだろう。