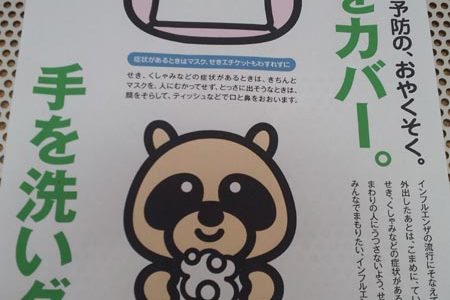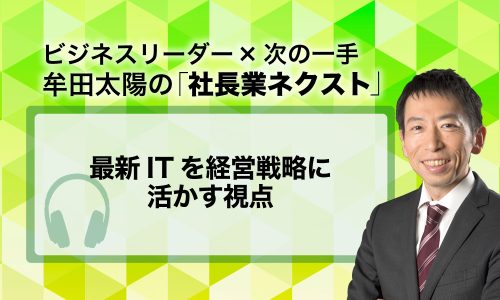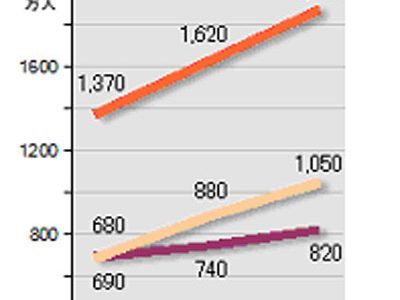心に響いた英国議会演説
昨年2月に突如隣国のロシアから侵攻を受けたウクライナのゼレンスキー(大統領)は、SNSを通じて勝利のための結束を国民に呼びかけて戦線を立て直したが、10倍以上とされる軍事力を誇るロシア軍を押し返すには、各国の軍事支援が不可欠だった。しかし、北大西洋条約機構(NATO)加盟の各国は、軍事同盟の外にあるウクライナ支援に消極的だった。ロシアを刺激したくない。
ゼレンスキーは直ちに主要各国首脳と電話会談を繰り返すとともに、各国議会にビデオメッセージを送り、支援を要請する積極的行動を起こす。
とりわけ侵攻二週間後の昨年3月6日に英国議会で流れたオンライン演説が劇的に事態を動かす。議場のスクリーンに登場したゼレンスキーは、鎮痛な表情で、子どもたちを含む市民たちの大きな犠牲を招いているロシア軍の無差別攻撃を非難した後、「私たちはあきらめない。負けません。最後まで戦います」。決然と勝利の日まで戦う意志を示し、英国民に支援を呼びかける。
「われわれは、海で戦い、空で戦い、どれだけ犠牲を出そうとも、われわれの領土を守ります。われわれは、森の中で、野原で、海岸で、都市や村で、通りで、丘で戦い続けます」
「そして、われわれはあきらめません。もちろんあなたがたの助けを借りて、偉大な国の文明の助けを借りて。皆さんのご支援を賜りますよう、お願い申し上げます」
議場は割れんばかりの拍手と興奮に包まれた。英国は本格的な軍事支援に大きく舵を切り、ウクライナ戦争は重大な潮目を迎える。一つの演説が世界を動かす。
組織の結束こそ勝利への道
この演説が、ジョンソン首相(当時)をはじめ英国民の心を打ったのには理由がある。第二次大戦当時、ナチス・ドイツが露骨に見せる世界制覇の野望に徹底抗戦を呼びかけたチャーチル首相の決意を思い起こさせたからである。
1940年5月。東部戦線に集中していたヒットラーのナチスドイツ軍は、西部戦線に電撃的に雪崩こんできた。英国政界内ではナチスとの妥協を目指す宥和(ゆうわ)論が根強かったが、戦時挙国一致内閣を率いることになったチャーチルは、徹底抗戦を国民に訴える。オランダ、ベルギー、フランスがナチスに蹂躙され、大陸に出兵していた英国軍も英仏海峡に面したダンケルクに追い詰められ、命からがら撤兵する。英国民には厭戦気分が横溢する。ダンケルクの脱出作戦直後、チャーチルは悲観論を払拭すべく英国下院で演説を行った。ナチス軍が圧倒的な空軍力を背景に英国本土上陸作戦を準備していた。1940年6月4日、チャーチルは、「われわれにはドイツ軍上陸に対抗できるだけの十分な戦力がある」と強調して国民を安心させた上で、次のように呼びかけた。
「(たとえヨーロッパ本土の国々がナチスの手に落ちたとしても)われわれはひるんだり、屈したりはしない。われわれは行き着くところまで行く。われわれはフランスで戦い、海や大洋で戦い、確信と力をもって空で戦う。われわれはいかなる犠牲を払おうとも本土を守り抜く。われわれは海岸で戦い、敵の上陸地点で戦い、野原や市街で戦い、山中で戦う」
ゼレンスキーはあえて、英国人ならだれでも知るこの部分を演説に忍ばせた。
さらに海軍大臣を兼務するチャーチルは、たとえ本土を占領されても海外領土を拠点に海軍力で戦い続ける意志を披瀝した上でこう結んだ。
「いつか必ず、新世界がその全力をあげて、旧世界の救援と解放に立ち上がる日を迎えるでありましょう」
そして彼の予言通り、この段階で参戦に躊躇していた米国は、やがて本格的な軍事支援から参戦を決断する。
外部世界を味方につけての反転攻勢
危機に際して必要なのは不屈の闘志と一丸となって難局に立ち向かう結束である。平時のリーダーに求められる卓越した調整能力だけではとても危機は乗り越えられない。組織を率いる強さこそが最も要求される資質である。
家族であれ、企業であれそうなのだが、国家の危機においてこそ指導者の強さと、即座に行動に移す瞬発力が事態を左右する。
ゼレンスキーがチャーチルから学んだのは、演説のレトリックだけではない。強い決意と行動が、国民の戦意を高め、外部世界の応援を引き寄せ、勝利に近づくという真理なのだ。
NATO諸国から長射程のミサイル、戦車の援助を受けることに成功したウクライナ軍が、ロシア軍の猛攻に耐えて、まもなく反転攻勢に転じる。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考文献
『第二次世界大戦2』W・Sチャーチル著 佐藤亮一訳 河出文庫
『ダウニング街日記(上)首相チャーチルのかたわらで』ジョン・コルヴィル著 都築忠七ら訳 平凡社
『危機の指導者 チャーチル』冨田浩司著 新潮選書