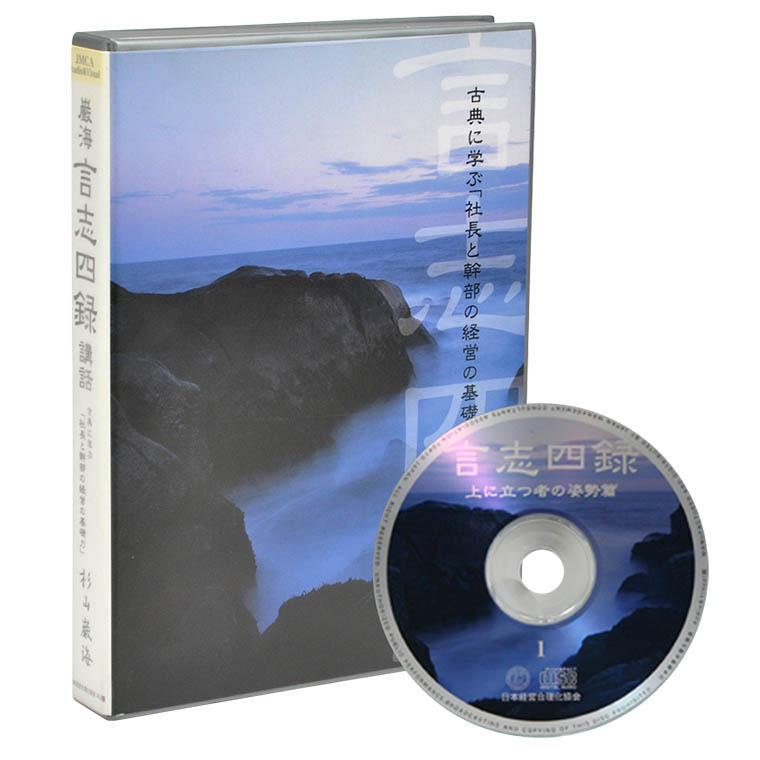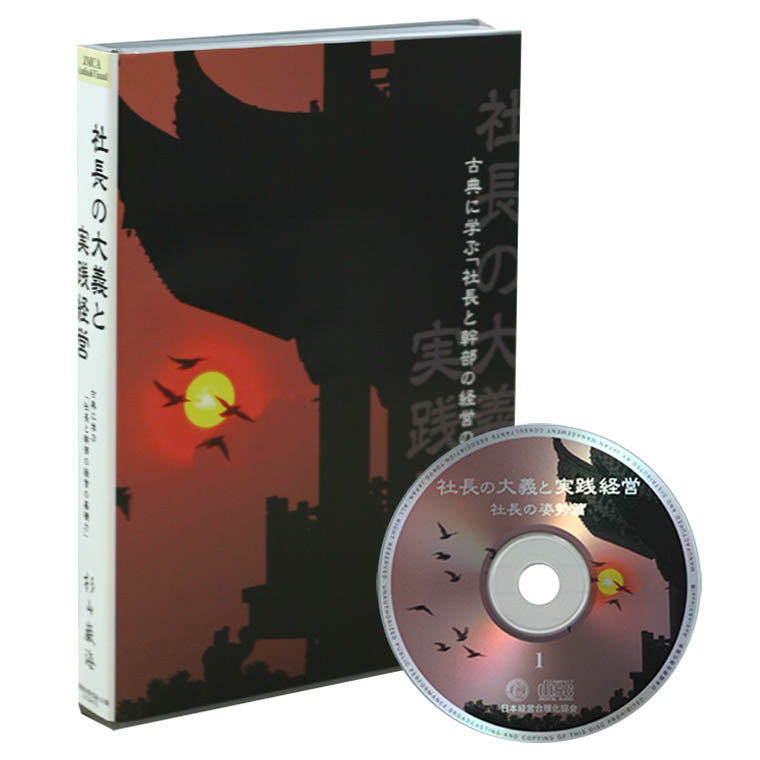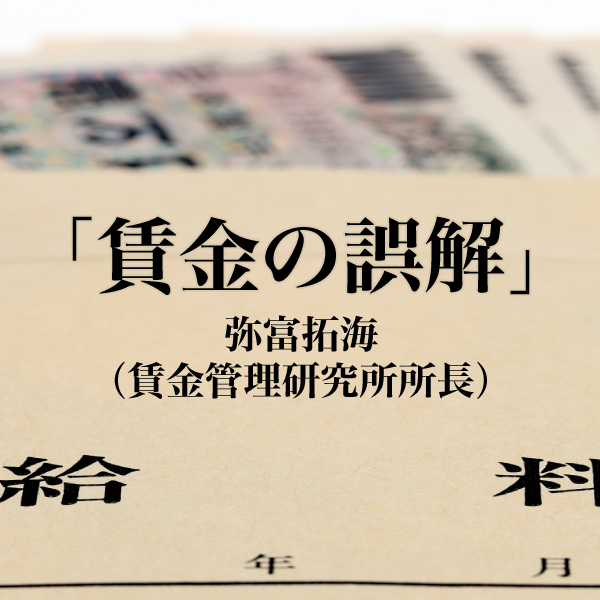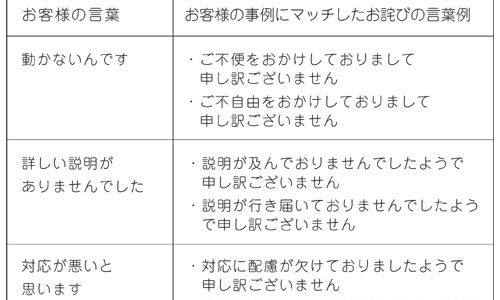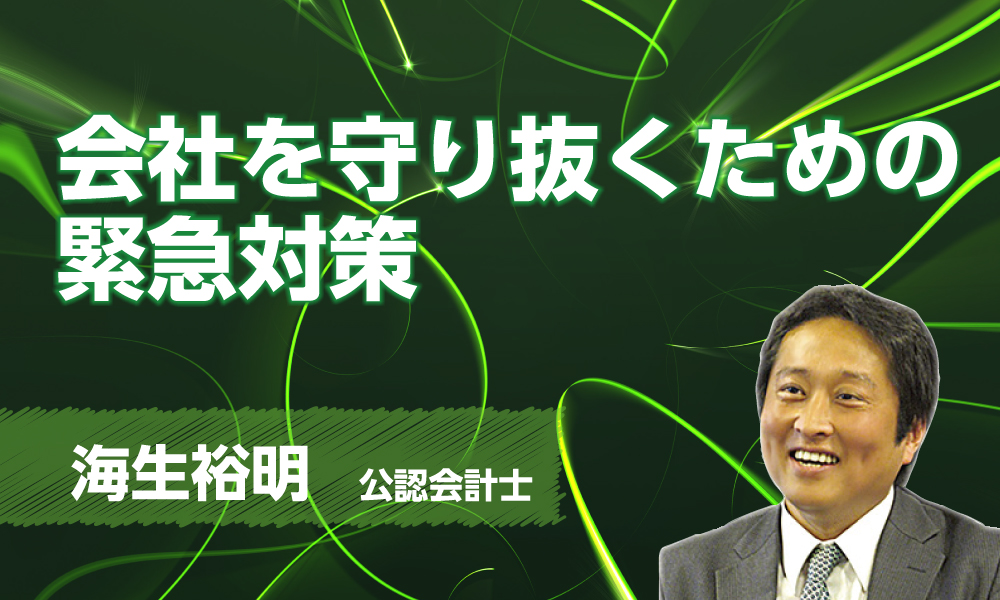【意味】
幅広く学んで、その志を強固にし、切実な問題として日常生活の中で実行する。
【解説】
学問を志すならば、
(1)学んだ者が学んだだけ幸せになる。
また、(2)学んだ者が多い社会は、学んだ者が多いだけより幸せな社会になる。
という学び方をしなければなりません。
これが学問の効用です。
掲句の「近くに思う」をなおざりにしますと、学問と生活とが遊離して、学びの成果が幸せに結びつきません。形式だけの机上の学問ということになってしまいます。
一般的には、学問の実践力を知識・見識・胆識の三段階としますが、更にその上に徳識を加えそのレベルを目標にしたいものです。
知識は、大脳皮質に記憶として焼きつけるだけのモノ。
見識は、多くの知識の中から、選択眼による判断意見を持てる段階をいいます。
胆識は、見識に勇気ある実行力が加わった段階をいいます。
ただ胆識の場合は、強制力を伴いますので一種の反発を生み、独裁者などの例のように一時的に成果が出ても持続しないという現実も少なくありません。
それに対して、徳識は自然に周囲の人々が協力して物事が成就してしまう段階をいいます。
論語には、「徳は孤ならず、必ず隣あり」という言葉もあります。
醜い様相を見せる世の中では、不道徳のモノが経済的に潤ったり道徳を心掛けている者が低い評価を受けたりすることがあります。
このような場合は、徳を守り我が道を歩もうと心掛けてはいても心が揺らぐものです。
そんな時、「あなたの尊い心掛けは、多くの隣人が見ていてくれますよ」と、励ましてくれる言葉は心強いものです。
この「徳は孤ならず 必ず隣あり」のように、その人の徳望に共鳴した人々が喜んで集りますから、自ずと成果はでますし、その成果は長く持続することにもなります。
「徳学とは、自他の幸せを念じて行う学問なり」(巌海)