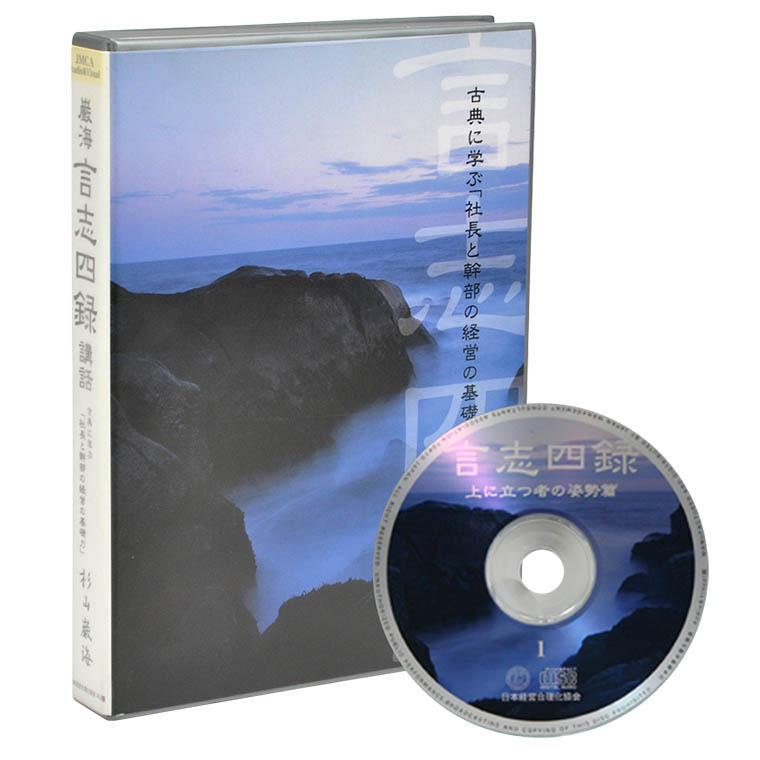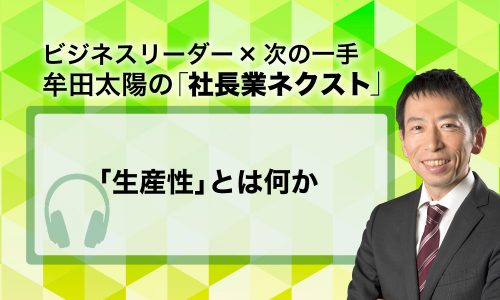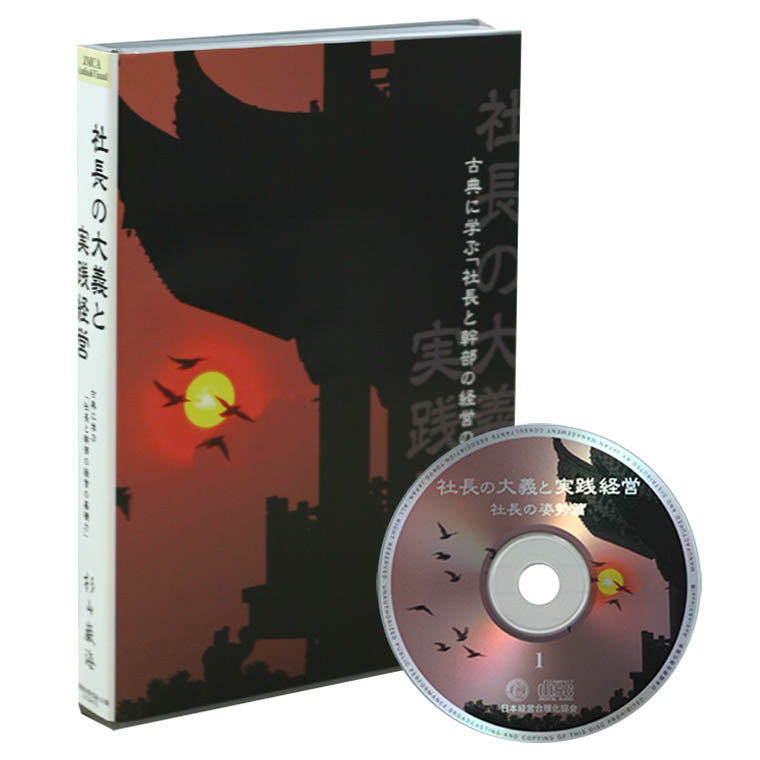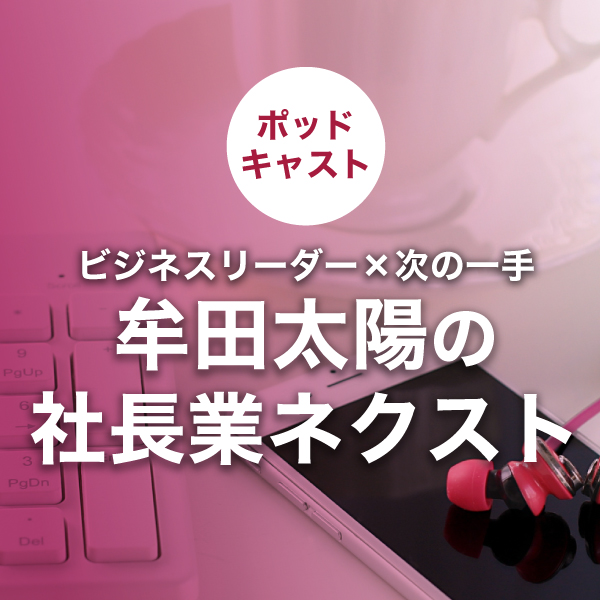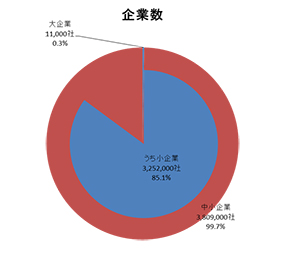【意味】
国の政治は、木を植えるが如し。根元が揺れなければ枝葉は茂る。君主が浮ついた生活をしなければ、人民も(君主の生活を手本にして)安定した生活が実現する。
【解説】
掲句は「貞観政要」のものです。「本根揺かざれば、枝葉茂栄す」とありますが、封建君主時代は「君主⇒領民の手本」となり、君主の姿勢が本根となります。民が君主である民主主義国家においては、「互いの個人⇒国民の手本」となり、我々国民が本根となります。
言い換えれば、昔は絶大な権限を有する君主一人が臣下人民の本根ですから、君主の成長が大切でした。現代の民主社会では国民が本根ですから、各人が互いの手本になる意識で生活することが大事です。この姿勢を「高貴なる相互民主社会を築く精神」といいます。
以下の文章は、私が主宰する「100万人の心の緑化作戦」の趣意書の一部です。
『100万人の心の緑化作戦』は、人心の砂漠化を防ぐ目的で大原学園グループが発足させたボランティア運動です。
「一年の計は作物を植え、十年の計は樹木を植え、百年の計は人心を育てよ!」といいます。土地の砂漠化には百万本の苗木で対応しますが、人心の砂漠化には「100万人の心の緑化作戦」によって対応しようとするものです。
この運動は、会員一人一人が『人間学読書会』において世界の名著を学び、生活規範となる自分流の「生き方ノート20条」を作成します。
そして、自分流の生活向上を目指す会員が100万人になれば、全国民12,700百万人の127人に1人の割合になりますから、この人々を核にして日本国の人心の砂漠化を防ぐというものです。
【人間学読書会のお知らせ】:『人間学読書会』は、名古屋・浜松・静岡の三都市で開催。誰でも無料で予約なしの参加が可能ですので別名『無門読書会』とも。・・・詳細はWebで!
掲句の考えに添えば、「君主⇒領民の手本」が人民の安楽になるならば、企業社会でも「経営幹部⇒社員や取引先の手本」が関係者の安楽を招くはずです。しかし関係者の現実の姿は、表面ではお金のために従順を装う一方、影では悪口という面従腹背の態度です。
この事実は、経営幹部の力量が会社の儲けを実現させても、まだまだ社員や取引先を安楽のレベルに導いていないことを物語っています。現代の平等社会では自意識過剰の指導者は敬遠されがちですが、そうかといって儲けるだけが幹部の役割と割り切っては、現代の企業社会の盟主たる者としては、目標の小さな経営ロマンと言わざるを得ません。
歴史は君主社会、貴族社会・企業社会と変わってきましたが、いつの時代でも世の指導者には「人民救済の社会貢献」が課されてきました。自社の儲けを挙げると共に社員や取引先の手本になる志を持つことこそが、真の『経営幹部の使命観』であります。
「本根揺かざれば・・」とありますが、歴史上の多くの指導者を育てた名著「貞観政要」や「宋名臣言行録」に真剣に取り組んでいただき、経営幹部としての本根を強固なものにすることをお勧めいたします。