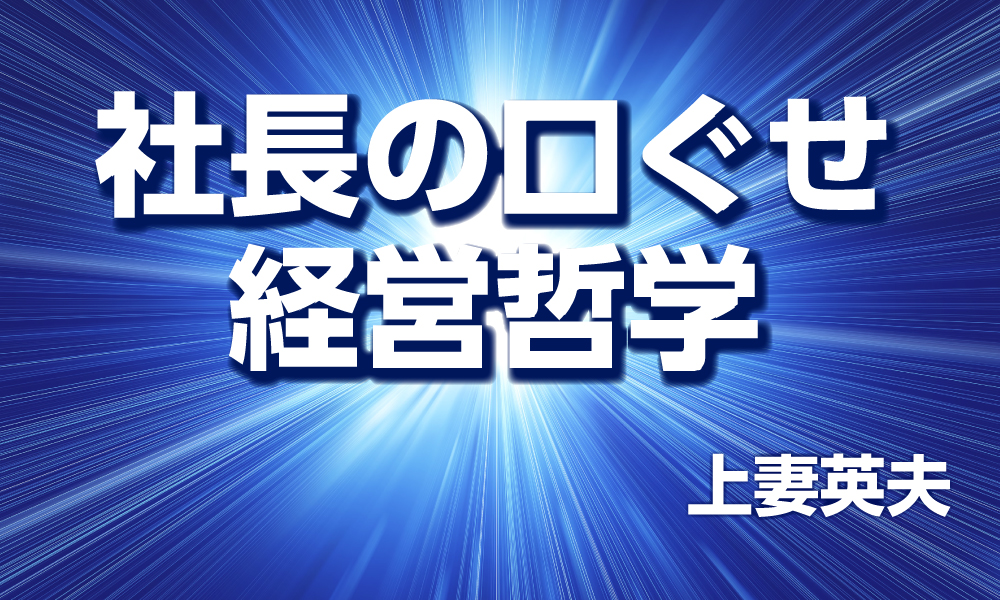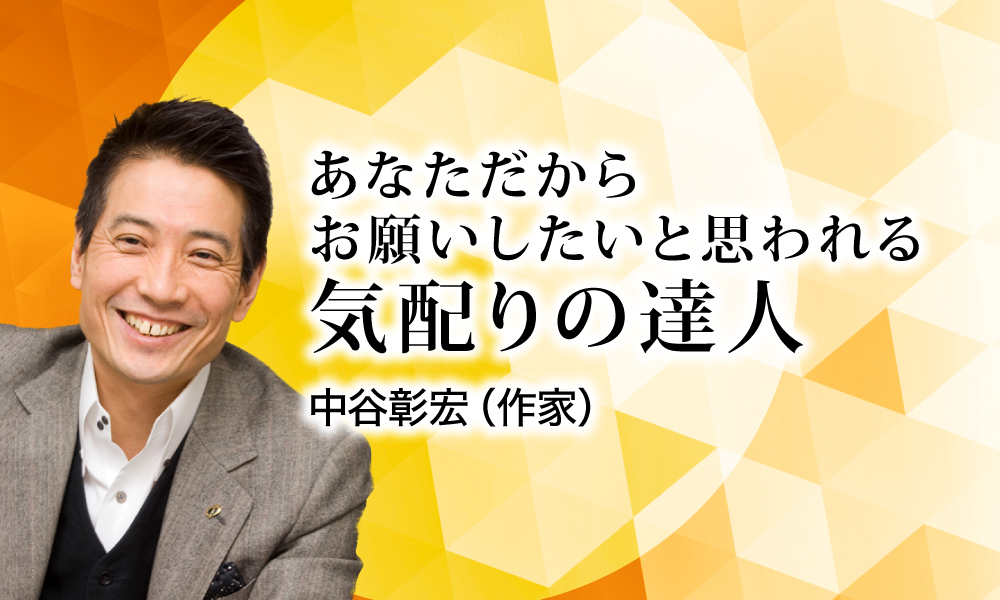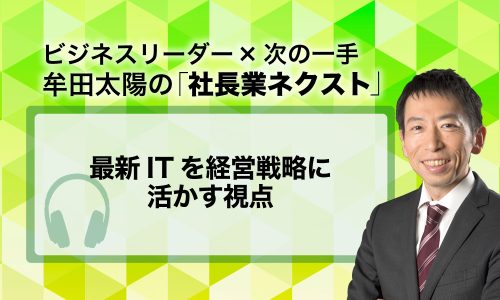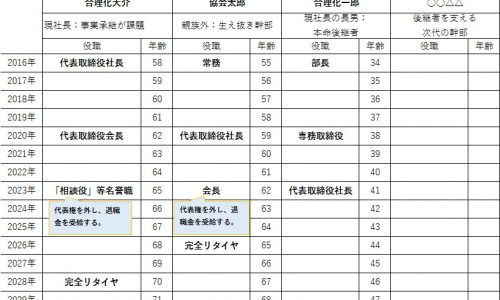■日本を代表する「共同浴場」
松山市のいで湯、道後温泉の歴史は古く、開湯は約3000年前。有馬温泉(兵庫県)、白浜温泉(和歌山県)とともに、日本三古湯のひとつに数えられ、「日本最古の温泉」ともいわれる。
道後温泉といえば、夏目漱石の『坊っちゃん』があまりにも有名だが、古くは『万葉集』『源氏物語』にも登場し、かの聖徳太子も道後の湯に浸かったという話も残る。そんな歴史ある温泉が枯渇することなく、湧き続けていることに感動を覚えずにはいられない。
ただ、温泉街を歩いてみるとわかるが、大型の旅館や高層ホテルが目立つ。温泉資源が少ない四国を代表する温泉地として発展してきたこともあり、団体客向けの大箱の温泉宿が林立する結果となった。
それでも道後温泉には、四国、いや日本を代表する共同浴場がある。高層ホテルや大型旅館に取り囲まれるように鎮座する「道後温泉本館」だ。温泉付きの宿に泊まっていても、ほとんどの人が立ち寄る、温泉街のシンボル的な存在である。

三層構造の情緒たっぷりの木造建築は、明治27年(1894年)に建てられたもの。国の重要文化財にも指定されている風格漂う建物は、まるでこの一角だけ明治時代から時が止まってしまったかのようだ。木材をふんだんに使った館内もまた趣があり、明治の時代に迷い込んでしまったかのような気分になる。
夏目漱石の『坊っちゃん』の舞台としても有名だが、建物は当時のままだという。明治32年(1899年)につくられた日本で唯一の皇室専用の湯殿「又新殿(ゆうしんでん)」も残されている。現在では、歴史の流れを感じさせるが、完成当初は、さぞかしモダンな建物だったことだろう。
■源泉かけ流しの「神の湯」
2019年からは本館保存修理工事が着工され、一部利用が制限される状態が続いていたが、2024年には全面営業再開に漕ぎつけて、新たなスタートを切った。
道後温泉本館は料金体系が少々複雑で、「神の湯」「霊(たま)の湯」という2種類の浴室がある。「霊の湯」のほうは入浴料金が高く設定されており、専用の浴室と休憩所を利用できる。
だが、多くの人が利用するのは「神の湯」。こちらは入浴だけなら700円。2階の55畳ある大広間で休憩すると1300円で、貸浴衣やお茶のほか、名物の菓子もついてくる。
「霊の湯」も「神の湯」も源泉そのものは変わらないので、初めて訪ねる人はポピュラーな「神の湯」を選択するとよいだろう。観光客だけではなく、地元の人も銭湯代わりに普段使いしているので常に賑わっている。本館の雰囲気を満喫したいなら、休憩付きがおすすめだ。
「神の湯」は石張りの湯船で、20人くらいは入れるサイズ。愛媛の伝統工芸品である砥部焼の陶板が壁を飾っている。『万葉集』で山部赤人が詠んだ歌を刻んだ円筒形の石の湯釜からは、透明のアルカリ性単純温泉が、なみなみと100%かけ流しにされている。加水、加温はされていない。行政の指導によって塩素殺菌のみされているが、臭いがまったく気にならない程度の量だ。「霊の湯」の湯も同様である。
湯船からあふれ出していく湯量が多く、ふんだんに新鮮な源泉が使われているのがわかる。泉質的には比較的シンプルな湯であるが、温泉の息遣いが聞こえてきそうなピュアな入浴感は、さすが天下の名湯である。毎日浸かっても、飽きそうもない。
■早朝6時の「刻太鼓」
ただ、いつ行っても混雑しているのが玉に瑕。そこで、道後温泉に宿泊した筆者は朝6時、宿を出て道後温泉本館をめざした。朝6時の開館と同時に入り、空いている浴室で一番風呂を浴びようという目論見である。
建物へ向かって歩いていると、「ドンッ、ドンッ」と太鼓の音が温泉街に響き始めた。道後温泉本館で6回叩かれる「刻太鼓(ときだいこ)」が開館の合図。なお、この太鼓の音は、「日本の音風景百選」に指定されている。
太鼓の音が響くと同時に、朝湯を楽しもうと、すでに並んでいた地元の常連さんや観光客が押し寄せる。少しの出遅れが致命的となり、浴室にはすでに10人以上の先客が朝湯を楽しんでいたのだった。常時、活気にあふれているのが「道後温泉本館らしさ」といえるかもしれない。