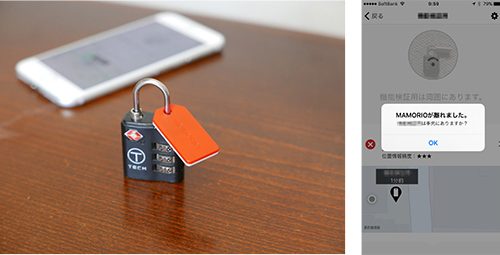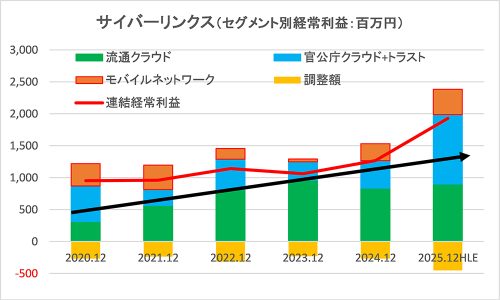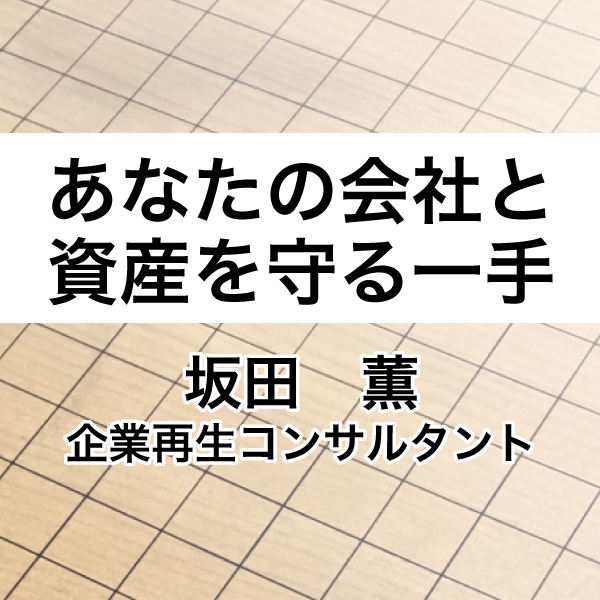超一流の経営者・美川英二
それほど広く知られていないが、バブル崩壊後の長引く平成不況の中で横川電機の社長として難局を乗り切った美川英二は超一流の経営者だった。
平成五年に社長になって以来、「社員は家族」という考え方を貫いた。確かに、計測機器の老舗メーカーである横川電機は、地味で堅実な社風で、家族主義の土壌があった。しかし、それ以上に、美川英二という経営者が果断な意思決定を繰り返し、儲かる商売と経営のあり方を貪欲に追求してきたことが家族主義の経営を可能にした。
経営者が自らの職責を果たし、儲かる商売をつくり上げ、そこに向けて従業員が力を合わせて仕事をすれば、稼ぐ力はますます強まる。従業員の給料も増える。結果として株価も上がり、株主も果実を手にできる。利益追求は今も昔も変わらない経営の王道だ。
営業利益にこだわる
美川は営業利益にこだわる経営者で、横川電機は高い収益性を誇っていた。当時の平均給与は製造業では第二位(一位は横川電機が25%出資していた日本ヒューレット・パッカード)。株主に対する配当も、高い水準で安定していた。
会社には順風のときもあれば逆風が吹きつけるときもある。美川が社長に就任したのは、バブル崩壊の直後。設備投資が一気に冷え込み、製造業の工場向けの製品を主力とする横河電機は大きなダメージを受けた。売上は20%、金額にして三百数十億円減少し、千五百人の余剰人員を抱えることになった。
こうなると、いちばん手っ取り早い解決は従業員の社員の解雇だ。千五百人を切り、内部留保を取り崩して退職金を支払う。そうすれば次年度からは利益が出る。しかし、美川は一人として切らなかった。しかも、給与にも手をつけない。余剰人員のクビを切らず、給与も賞与も人並み以上に払い、株主には安定配当、営業利益も黒字にする――無理難題に聞こえるが、そこにこそ経営者の本領がある。
利益を生み出すコストダウン「新幹線方式」
注文が二割減るのなら、残った八割の中から利益を絞り出せばいい。一億円かかった製品であれば、七千万円で作ればいい――コストダウンと言えば数パーセントを切り詰めるというのが普通だが、美川は最低で30%のコストダウンを指示した。彼の言う「新幹線方式」だ。数パーセントのコストダウンならば従来の路線上でできる。しかし、30%となると設計から変えなくてはならない。若手リーダーを決めて、48の機種ごとにプロジェクトチームを走らせる。それぞれに開発、設計、調達、製造の各部門からメンバーを集め、知恵を絞らせる。最終的に35%、三百億円のコストダウンを実現した。
千五百人の余剰人員についてはどうしたか。多くの会社では余剰人員を代理店や子会社、関連会社に押しつけるということをよくやる。美川はそれをせずに、新しい会社をたくさん作った。そこに、余った人間ではなく、若くてバリバリの社員を社長として赴任させた。その際、それぞれの仲間を連れて行かせた。自分の給料は自分で稼がなければならない。彼らは実に活き活きとして働きだした。出向といえば本社がいらない人材を出すことが多い。しかし、若くて一番いい人材を出した。本人にとっては責任範囲が拡がりやる気も出る。約千八百五十人、外へ出した。彼らはみんなよく働く。一方、会社では人件費が浮いた効果が約百三十億円出た。先程の三百億と合わせて計四百三十億円だ。
名経営者・美川英二の肉声に学ぶ
美川の経営スタイルははっきりとしたトップダウン。それでも社員がついて来るのには真っ当な理由があった。美川はこう言っている。
それは給料も賞与も退職金も待遇を厚くしているからである。それだけのことをしているから、「たいへんなことだけれど、みんな協力してくれ」と言えば、組合以下、「分かりました」と一丸となって即動いてくれる。(中略)節電しろ、紙一枚節約しろ、鉛筆一本節約しろ、といちいち言わなくても、当社ではみんなが節約する。なぜなら、賞与に関係するからだ。当社は、夏二・三、冬二・七の固定月数、それにプラスして営業利益の二十七パーセント分を、賞与として支給する。この利益配分方式はもう二十年近く実行している。
前回も話したように、経済のエンジンは企業、企業のドライバーは経営者。美川英二のような一流の経営者の肉声に耳を傾けると、会社は経営者次第だということをつくづく思い知る。在任中に65歳の若さでその生涯を閉じた美川は次の言葉を遺している。
最近、インタビューなどで「九十八年の景気をどう見ていますか」などと聞かれることがある。しかし、私はそんなことをいちばん最初に考えたためしはないのである。(中略)景気の良し悪しに左右されて会社がやっていけるだろうか。そんなものに振り回されない企業にしようと、我々は日々努力しているのだ。自分の身は自分で守る。それしかないではないか。だから私はこう答える。「当社は来年もきちっとやります。大丈夫です」と。(中略)喜びも悲しみも分かち合うのが家族だ。だから、会社が苦しければ、今まで白米を食べていたのをイモにしてでも助け合う。いい時は配分しあって喜ぶ。しかし、経営者としてはイモを食べさせたくはないし、食べさせはしない、と決意している。一度しかない人生、社員が一生を振り返った時は、人生の大部分を横河で過ごして幸せだった、と思ってほしい。そのためのあらゆる方法を考えるのが経営者の務めだ。
これぞ経営者。思わず拍手喝采したくなる。