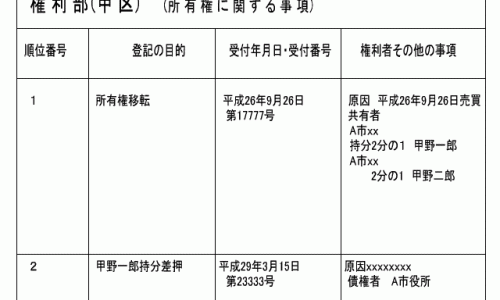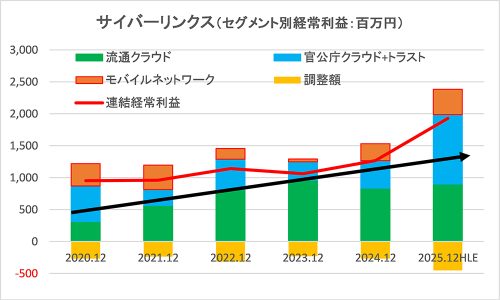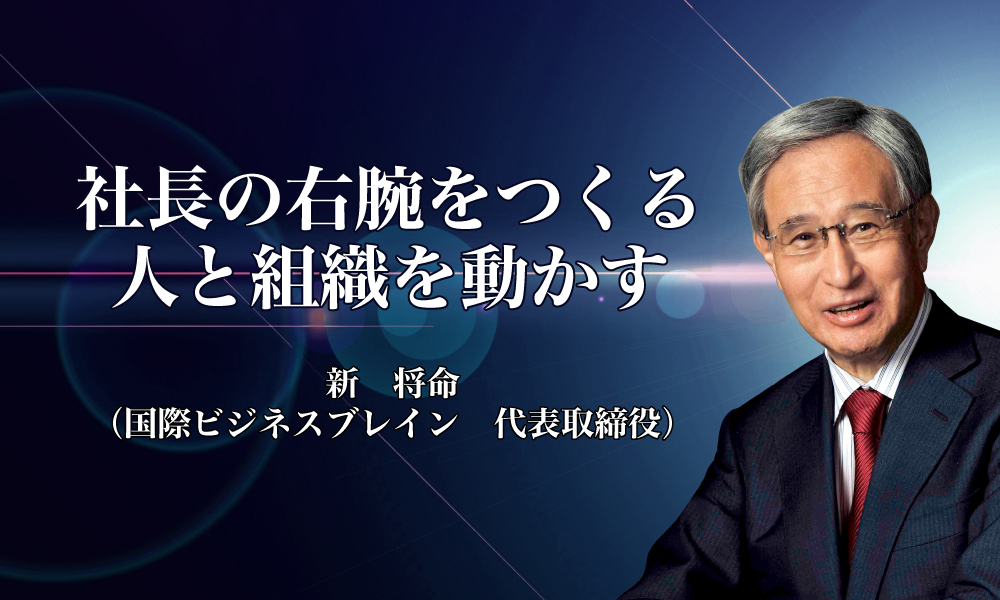ダイバーシティはそもそも「美味しいもの」
性別、国籍、宗教、性的指向などの多様性を重視したダイバーシティ経営が注目されるようになってきた。多様性の包摂は普遍的な価値観だ。しかしそれ以前に、経営の観点から見ると、多様性がないことは単純に「損」だ。例えば、女性の活用。人口のほぼ半分は女性なのだから、女性の能力を無視するということは人口の半分を見殺しにするということになる。経営にとって大損でしかない。にも拘らず、「やらなければいけない」などと言っている人がいる。経営にとってダイバーシティはそもそも「美味しいもの」。美味しいものを食べたいと思うのが普通で、「食べなければいけない」というのは奇妙な話だ。
雇用は本来、「価値の交換」である。雇用主は能力を買い、労働者は能力を売っている。経営はこの価値交換の基本に戻るべきだ。最近になって「ジョブ型雇用」(職務内容を明確に決めて雇用すること)への転換が叫ばれている。会社が仕事(ジョブ)の組織である以上、雇用は本来ジョブ型以外にはない。「ジョブ型雇用」というのは当たり前の話だ。
雇用制度は「文化」にあわせるのではない
日本人は狩猟民族ではなく農耕民族だから、ジョブ型雇用は日本の文化とは合わない、メンバーシップ型雇用(職務内容を限定しない雇用)こそが日本の文化であり、終身雇用と年功序列が日本的経営だ、などと言う人もいる。しかし、第二次世界大戦以前は、日本は終身雇用であるどころか、アメリカより労働市場の流動性が高いことが問題になっていた。当時の日本の経営者は、「日本人はちょっと給料が安いとすぐに他の会社に行ってしまう、アメリカに大企業ができるのは家族主義で経営しているからで長期雇用だから技術が蓄積し、大きな産業が育っている」と嘆いていた。当時、アメリカはデトロイトに自動車産業が出てきた頃で、それを見て「日本もアメリカのようにものづくりができる国にならなければいけない」、当時の日本は財閥支配だったので、「日本は金融資本が金融のロジックで商売をやっているから駄目だ」と現在とは全く逆のことを言っていたのである。
終身雇用、年功序列は、一度採用したら能力に拘らず雇用し続け年次に応じてポストと給与をあげていかなければいけないという仕組みだ。論理的には破綻している。ところが、高度経済成長期には、この仕組みに合理性があった。年功序列は評価の基準がオープンかつクリアだし、一人ひとりを評価するためにかかる莫大なコストが不要になる。それで社員が納得して働くわけだから、これほど効率的な経営はなかった。
ただし、この特殊な経営が成り立つには、猛烈な勢いで売上が伸びていかなければならない。終身雇用、年功序列は超論理的な「戒厳令」とでも言うべき人事制度だが、高度経済成長期という異常な状態にはマッチしていた、つまり得だったということだ。しかし、その外的な条件がなくなれば、当然のことながら戒厳令は引っ込めなければならない。いまでもそれを続けている会社は損をしているということだ。
ダイバーシティ経営のポイントは「年齢」と「欲」
もっとも重要なダイバーシティ経営のポイントは「年齢」だと考えている。日本企業はこれまで、年功序列制度のもとで、能力を年齢に〝強制翻訳〟してきた。若いというだけでポストに就けない、年をとっているだけで老害と言われる、定年になったら全員辞めるというように、何かにつけて年齢という物差しに寄りかかったマネジメントが出来上がっている。
もちろん、経験の長さは能力の基盤である。しかし、それは「能力」を言っているのであって「年齢」それ自体ではないはずだ。男女という性差で区別すべきでないのは、経営にとってその方が得だからだ。これと同じように、年齢も一切考慮しないことが経営にとっては得になる。これが結果的に多様性を高めることになる。
経営が本気で能力を評価しようとするならば、年齢を一切見ないようにするべきだ。年齢に拘らず、求められている能力がなく、成果が出なければ、「あなたはいまの仕事には適性がなく調子が出ないようなので、この4つのオプションのうちのどれかにかわってください」ということを率直に言い合うべきだと思う。どれもできないのであれば、「別の会社で働いてください」と言うしかないだろう。
その代わり、能力がある人には65歳になっても70歳になっても働いてもらう。それに見合う報酬を支払う。それが正しい仕事の組織であり、経営だと思う。事実、こうした会社は増えてきている。そちらの方がどう考えても得だからだ。
経営者の根底にあるのは、成果に対する「欲」だと思う。優れた経営者ほど能力のある人に働いてもらいたいと考えているはずだ。「ダイバーシティをやらなければ」「多様性が進まない」と言っている経営者は、成果への「欲」がなさすぎる。経営者は「欲」をもって欲しい。そうすれば、自然に多様性は出てくるはずだ。