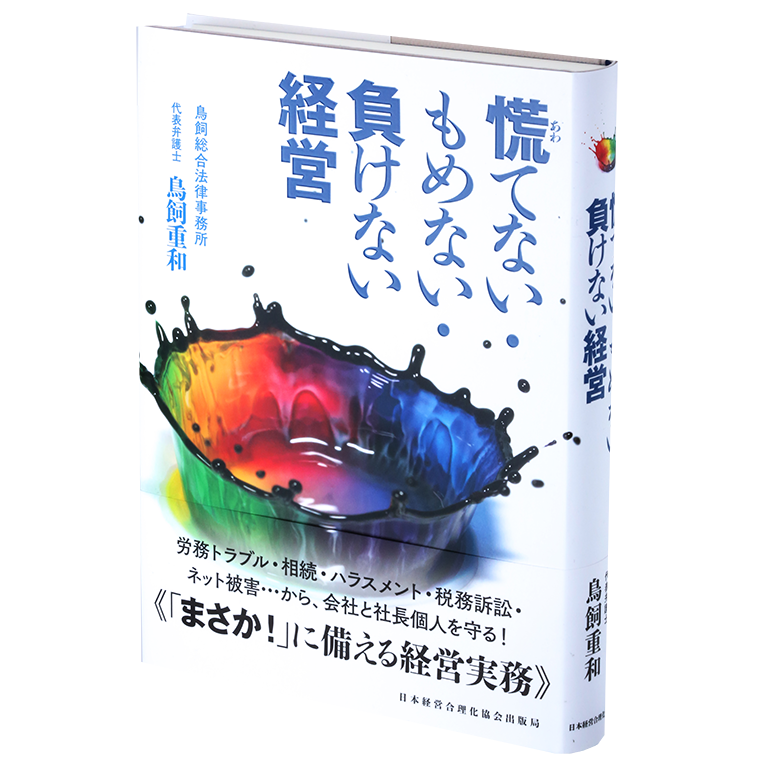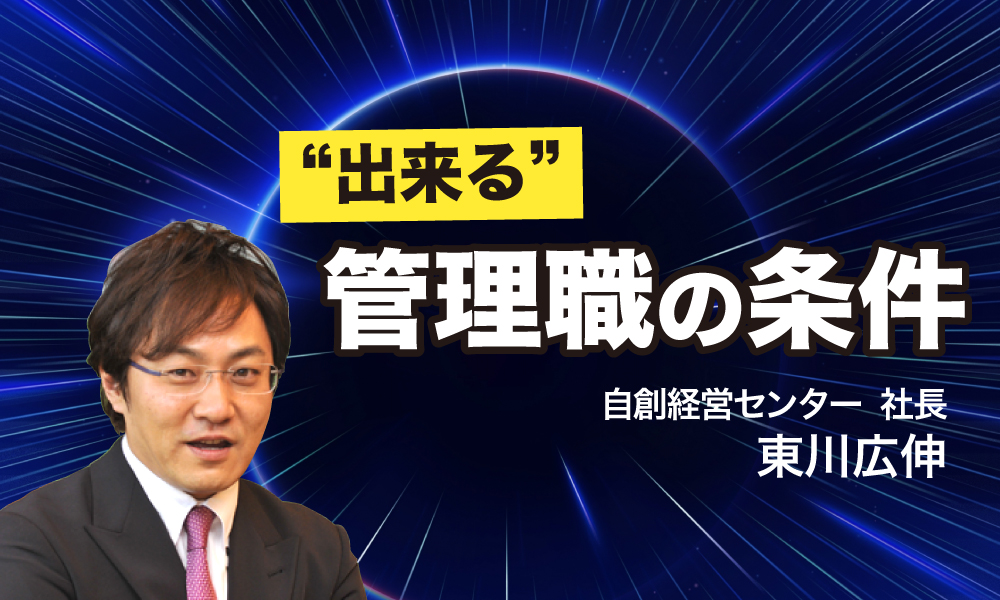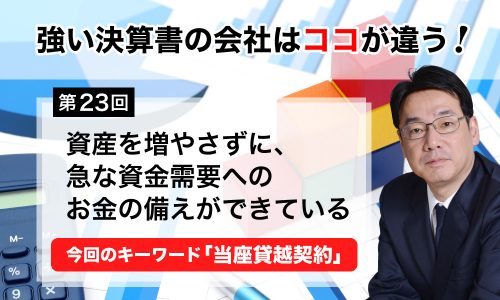高崎社長は、昨今の人手不足を解消するために、定年を迎えた従業員の再雇用を決めたようですが、再雇用した従業員から、待遇に不満がでるのではないかと不安な様子です。
高崎社長:先日は、被用者保険の適用拡大について教えてくださりありがとうございました。やはり我が社も対象となるようで、一通りの手続きは終えましたが、出費がかさむばかりです。ところで当社も即戦力を確保するために、定年を迎えた従業員に、再雇用で働き続けてもらいたいと考えているのですが、定年前までと同じ待遇を用意することは、難しい実情でして。
賛多弁護士:これまで一緒に働いてくれた従業員が定年後も継続して勤務してくれるのであれば、同程度の待遇で再度迎え入れたいというお気持ちでしょうが、なかなかそう簡単にはいきませんよね。
高崎社長:そうなのです。確かに、再雇用の従業員の仕事内容は、定年時のそれとほとんど同じで、当然これを考慮しなければならないのだろうと思います。再雇用後の待遇について、法的にはどう整理されているのですか?
賛多弁護士:御社で再雇用される従業員は、みなさん有期雇用労働者ですので、それを前提にご説明します。まず、有期雇用労働者と通常の無期雇用労働者の待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されています(パートタイム・有期雇用労働法8条)。ここでいう「不合理な待遇の禁止」の意味を具体的に理解することは難しいのですが、簡単に言えば「前提条件(待遇の目的や性質)が通常の労働者と同じなら同一に扱い、異なるのであればその違いに応じた取扱いをする」という意味で理解してください。
高崎社長:なるほど。そうすると、再雇用の前後で、前提となる待遇の目的や性質が通常の労働者と異なるのであれば、給与等を減額することも可能ということですね。
賛多弁護士:そのとおりです。ただ異なる取扱いをする場合に、その取扱いが不合理とされないか注意が必要です。不合理と認められる相違に当たるかどうかを判断するためには、職務の内容(業務の内容・業務に伴う責任の程度)、当該職務や配置変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮する必要があります。なお、定年退職後に再雇用された有期雇用労働者であるという事情は、「その他の事情」として考慮され得ることになります。このような考え方は、定年退職後においては老齢厚生年金の支給を受けることができることを理由とするものと考えられますが、結局のところ、不合理と認められるかどうかは、様々な事情を総合的に判断することになりますから、再雇用された従業員であることのみをもって、不合理でないと認められることにはなりません。
高崎社長:わかりました。待遇のうち、まずは基本給について、どのように考えればよいのでしょうか。
賛多弁護士:基本給であってもその性質や目的を踏まえた検討をすることが不可欠ですが、減額することができる可能性はあります。先ほど申し上げたように、職務の内容や配置変更の範囲を考慮することになりますので、例えば、たとえ定年退職後の業務内容が同一であったとしても、配置転換がなくなったり、権限の範囲が縮小されるということとされていれば、基本給を減額することにつき合理的に説明しやすくなります。
高崎社長:そうすると、定年後、再就職にかかる契約を締結する際に、それらの契約内容をしっかり検討する必要がありそうですね。あと、賞与を支給しないこととすることは可能でしょうか。
賛多弁護士:御社の賞与は、企業業績や、労働者の出勤率・成績評価を考慮した上で支給額が決定される形態だったと思います。こういった一般的な賞与の場合、その性質や目的は、賃金の後払いと企業業績への貢献に対する報償にあると理解されています。そうすると、通常の無期雇用労働者との間で、企業業績への貢献度に違いがあるのであれば、その違いに応じた支給をすることも可能となるでしょう。ただ、御社で再雇用する有期労働者の業務内容に、大きな変更はないと思いますから、賞与全額を支給しないこととするのは難しいでしょう。
高崎社長:なるほど。通常の無期雇用労働者との関係で、不合理とみとめられるかの検討には、賞与の計算方法や給付の実態を踏まえた考慮が必要であることが分かりました。
賛多弁護士:おっしゃるとおりです。なお、近時の最高裁判決では、当該待遇の具体的な性質や目的を明らかにした上で、労使交渉の結果のみならず具体的な経緯を勘案しつつ、不合理性が判断されるとしているものがあります。
高崎社長:そうすると、手当も項目ごとの検討が必要になるのでしょうね。
賛多弁護士:そのとおりです。例えば、業務の危険度や作業環境に応じて支給されている手当については、その業務の危険度等に着目して支給されることになるのですから、定年退職後の再雇用された有期雇用労働者であっても、同じ業務に就くのであれば、支給しない理由はないでしょう。通勤手当なども同様ですね。各種手当を支給する趣旨が、定年退職後の再雇用された労働者にも妥当するのか、という観点で検討する必要がありますので、例えば再雇用された労働者に、転居を伴う転勤が予定されていないのであれば、住宅手当を支給しない、あるいは減額することについて合理的に説明をしやすくなるでしょう。したがって、単に定年前後での年収を比較するだけで結論は導かれるのはないことに注意が必要です。
高崎社長:わかりました。賃金項目ごとに具体的に検討しようと思います。来週、事務所へお邪魔しますね。
定年退職後の再雇用された労働者の待遇については、退職前後での総額で比較されることも多いのですが、それだけでは検討として不十分な場合があります。そこで、基本給や賞与、各種手当に至るまで、その趣旨や目的を各種規程などで明確にしておく必要があるでしょう。
執筆:鳥飼総合法律事務所 弁護士 塚越幹夫