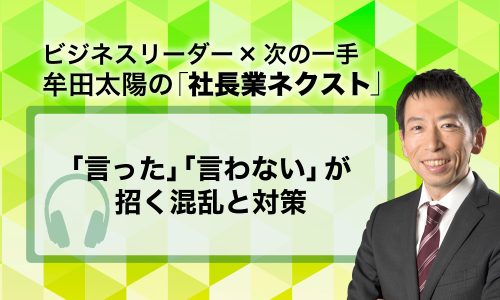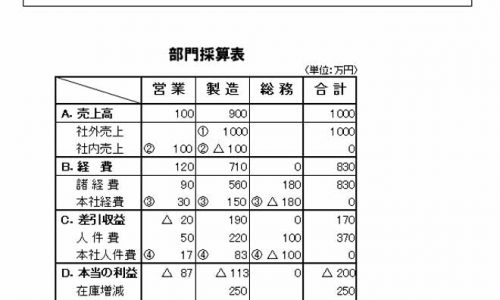鼻は顔の中心に存在しているパーツ
そのため、人に与える印象も非常に大きいと言えます。
その形や大きさ長さなどといった形状が、その人のパーソナル・イメージの中でも、個性を表す部分として
認識されています。これは、「いい」「悪い」というものとは違い、「堂々としている」「デリケートそうだ」などの、
人それぞれが持つ特徴や特性を想像させる印象。
これ以外にも、第一印象を左右する鼻に関するイメージがあります。
それは、ポスチャーと関連した「鼻」の扱い方と、そのエチケット。
無意識に行っていることの多いしぐさや癖、文化の違いからくる、イメージの受け取り方の違いがあるのです。
では、その一つ目を紹介しましょう。
鼻を触る
話しながら鼻を触る癖のある方をよく見かけます。
エグゼクティブの方であっても、ミーティングや会見の際に、鼻の辺りに手をやる方が多いものです。
しかし、このしぐさ、注意をしなくてはいけません。
欧米文化においては、 嘘をついている時のしぐさとみなされてしまいます。
日本の方がこのしぐさをするときは、少々照れていたり、恥ずかしいとき。
しかし、その恥じらいは相手に通じないまでか、嘘をついているのでは?と疑われる要素を
自ら作ってしまっているのです。ビジネスシーンでは信頼感が大切。これは避けねばなりせん。
また、顔の中心にある鼻を触るということは、顔の表情を手で隠してしまいます。
鼻に手をやると、当然ながら口元まで覆ってしまい、話をしていても、声がこもります。
自分の発言に自信のない人というイメージ相手に与えてしまうことは明白です。
もともと表情が堅かったり、あまりないと見られる日本人、さらにその表情を手元で隠してしまっては
何を考えているのか分からないと思われてしまいます。
また、鼻に限らず、顔をやたら触るしぐさは、決して清潔感があるとはいえません。
だらしがないイメージを与えることさえ多々あります。顔に触れるというのは、それが自分であっても
他人にされることであっても、かなりプライベートなイメージがあると言えるでしょう。
では、 なぜ鼻を触るのは嘘をついているしぐさと言われるか?
それは、欧米では「嘘をつくと鼻がむずむずするから」という説からきているようです。
私が目にする、日本人エグゼクティブがオフィシャルなシーンで鼻に手をやるしぐさをする状況をあげると、
しどろもどろの回答をしているとき、悩んでいるときなどです。
やはり、嘘とはいわないまでも、何らかの理由で自信をもって堂々と正解としての回答ができない時なのです。
これらのネガティブなイメージを相手に与えないようにする為には、人と話をしているときは顔をすっきりと上げ、
手で顔をやたら触るのは避けることです。
これが相手に与えるイメージとしても、エチケットとしても大変重要な事といえます。
顔の中心にある最も高さのあるパーツである鼻、そのエチケットは思いの他注目されていることを
是非意識してご覧ください。