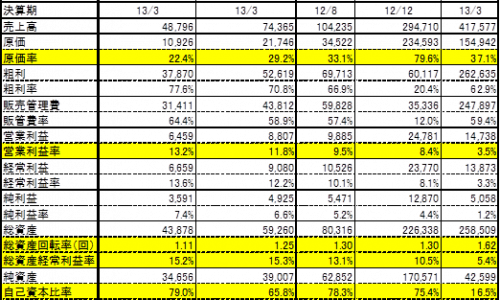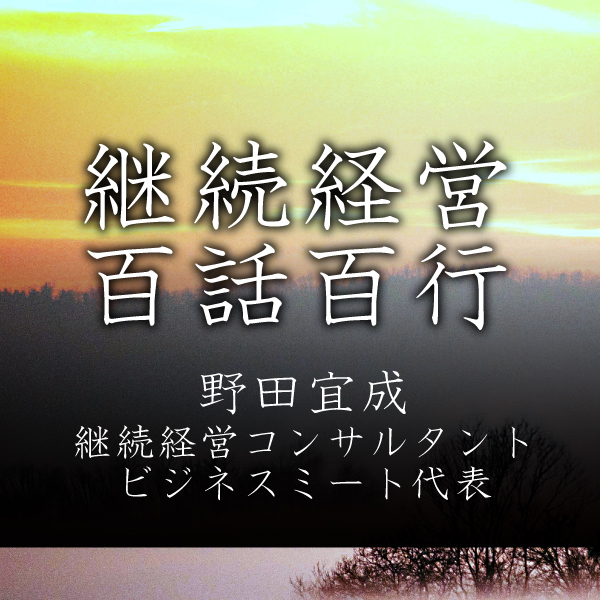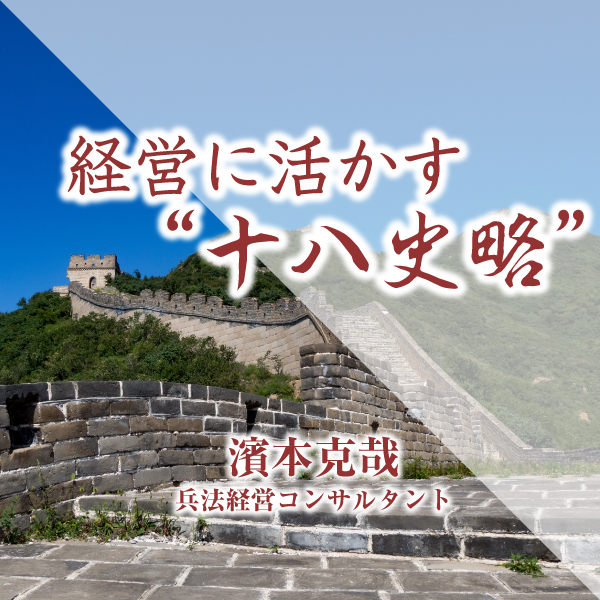- ホーム
- 指導者たる者かくあるべし
- 逆転の発想(3) 捨てる力(スティーブ・ジョブズ、羽生善治)
何かを捨てなければ前に進めない
IT企業の旗手、アップル社の共同創立者の一人であるスティーブ・ジョブスの経営術は、徹底した「選択と集中」の思想に支えられてきた。どこの経営塾でも真っ先にそれを教える。経営学の「いろはのい」ではあるが、ジョブズによれば、口で言うほど「楽な仕事ではない」という。同感される方は多いだろう。
選択と集中のためには、何を捨てるかを決断する必要がある。そこで成功するかどうかで企業の将来が決まる。
1985年にアップルを追放されたジョブズが11年後、同社に復帰したとき、アップルコンピュータは、次世代型基本ソフト(OS)の開発に行き詰まり、ウィンドウズ95の開発成功で波に乗るライバルのマイクロソフトに大きく差をつけられていた。
開発状況を点検したジョブズは、担当者を呼んで叱りとばした。開発チームは自社の開発を諦め、ジョブズが追放後に立ち上げた会社で開発したOSに、旧バージョンのインターフェースを載せようとしていたのだ。
彼は言った。「安易な方法をとるな。考え方をリセットしてゼロからやり直せ」。この叱咤によって、新時代の安定的なOSX(テン)を乗せたiMacが大ヒットし、アップルが先行するマイクロソフトを猛追することとなった。
やりかけたものを改良してもダメなら、それまでの開発費を惜しいと思わず、ゼロからやり直す発想だ。
成功体験にこだわるな
ジョブズの「常に何かを捨てて前進する」との方針は徹底している。彼は言う。
「特に、うまくいっているときや、(製品が)高い評価を得ているときに、それを打ち切るなど、普通の企業はやるはずがない。少しずつ改良し、長く売ろうとするだろう」
しかし、ジョブズの発想は違った。前に進むためには成功体験をもこだわらず捨てる。
たとえば、携帯型デジタル音楽プレイヤーiPodシリーズの開発でも、売れ筋のiPod miniの生産を打ち切り、薄型のnanoの開発に邁進する。これによる技術の蓄積がスマートフォンブームをリードするiPhoneの登場につながった。
普通なら、あるメガヒット商品が生まれれば、それに安住してよしとする。
「やったぞ、ここで失敗したら失うものが大きい」と考えて安全策を取りたくなる。「だが、これが一番危険な落とし穴だ。もっと大胆にチャレンジを続けるべきだ」と言うのがジョブズ流の逆転の発想だ。成功体験をも捨てる。
次の一手を産むために「捨てる」
「捨てること」が、次の一手を生み出すのは、将棋の世界でも同じだ。弱冠25歳で史上初の七冠を達成し、その後も将棋界の記録を次々と塗りかえ続ける羽生善治は、「ひとつの手を選ぶことは、それまで考えた手の大部分を捨てることだ」と話す。
確かにひとつの局面での選択肢は、過去の棋譜、相手の出方を考えると何万、何十万とある。その中からひとつの手を選ぶことは、膨大な数の手を捨てる作業だろう。
「山ほどある情報の中から、自分に必要な情報を得るためには、『選ぶ』よりも『いかに捨てるか』のほうが重要」と言い切る羽生は、「手は浮かぶものではなくて、消去して残ったものだ」と指摘する。
まさに名人の域にある羽生流だが、彼でも、捨てることには未練が残るという。
「たくさん時間を費やした手に対してはどうしても愛着が湧いてしまいます。いつもシビアにドライに割り切ることができればいいけど、そういうわけにはいかない」と正直に吐露する。
「別の手を選んでいれば、こんなに劣勢になっていないのに」と思うこともあるというが、「その手を選んでいたら優勢になっていたかと言うと、それはまた別問題だ」とも。
選択によって、よくも悪くもどちらにも転ぶ可能性がある。
ならば、「自分が選んだものに対して責任を持ちつつ自信を持つことが大事なのではないでしょうか」。
名人がたどり着いた境地は、「楽観論」である。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考文献
『スティーブ・ジョブス 神の仕事術』桑原晃弥著 PHP文庫
『捨てる力』羽生善治著 PHP文庫