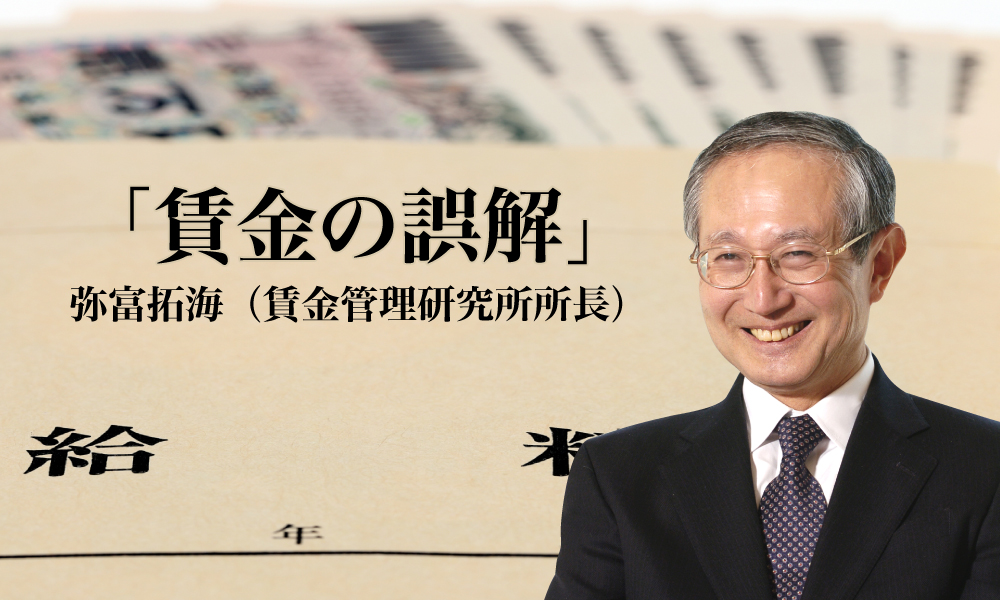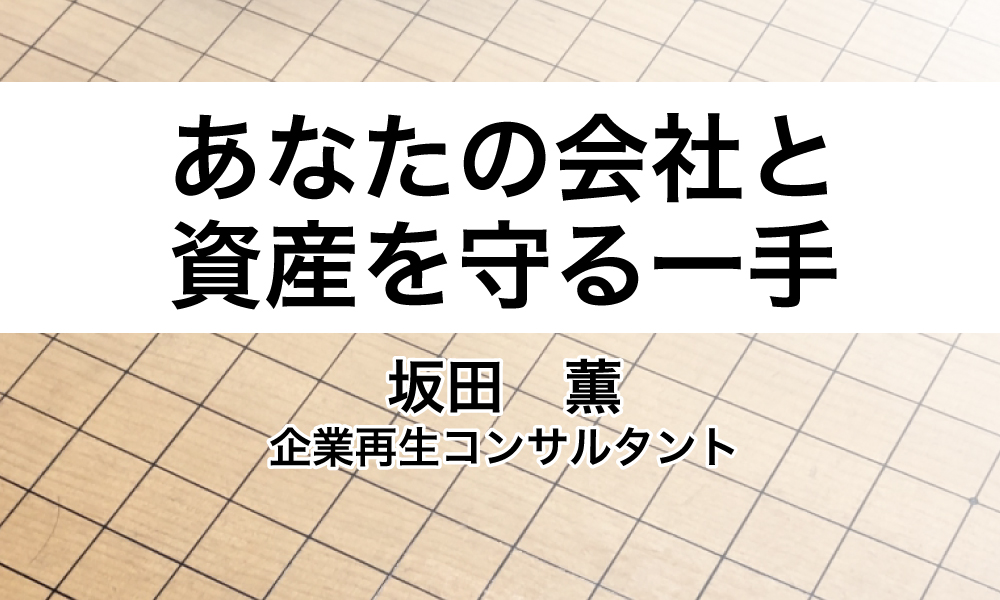賃金管理研究所が提唱する賃金制度の柱は「責任等級」であり、仕事一辺倒の「職務給」の考え方に「仕事力の向上」という属人要素を加えて、より高い納得性と長期繁栄の好循環の実現を目指します。それこそが「職制準拠の職能給体系」だと前回のコラム(第68話)で申し上げました。
*「職制」とは社長から始まる指揮命令が現場第一線まで速やかに、かつ正確に伝わるための総体構成の事です。
ところで「わが社はとっくに職能給を導入してきたが、年功運用に流されて、当初期待していた効果があがっていない」と職能給による能力主義の効能を疑問視する意見を聞くことがあります。そうした意見は「属人給」の立場で「職能要件」を設定し、広く能力の有無と習得・習熟に情意を加えて考課し、給料を決め、処遇に結び付けようとする「職能資格制度」を採りいれた企業に多いようです。
実はこの型どおりの「職能要件」の設定が不都合のモトと言ってよいでしょう。なぜなら「職能」とはきわめて属人的な要素であり、仕事にふさわしい能力の検証が難しく、ある程度の勤続・年齢になれば、習熟を根拠に上位の資格等級に昇格させる年功運用を当然の事とせざるを得ないからです。
さらに間違いを重ねることになったのは「人」に焦点を合わせて、やる気を高めようとする身分制度の宿命なのですが、昇格願望を満たすための階層区分を職制に関わりなく増やしていかなければモチベーションが維持しにくい。そのために階層数を7から9そして12へ、加えて中間的身分呼称を増やしていかざるを得なかったことです。
「人の処遇」を最優先すれば、時が経つにつれて階層数がひな壇のように増殖し、会社全体の仕事(報連相)の流れが、職制に関われない役付社員に阻害され、非効率で高コストな集団になってしまうのです。つまりトップからの指示命令と第一線からの報告がダイナミックに往来する本来あるべき職制構造が不透明になり、機能しにくくなってしまうのです。
これに対して「職制準拠の職能給」における賃金決定の第一義的要素は仕事、つまり求められる成果責任の重さであり、基本は風通しの良い精鋭組織の構築なのです。
従って、職制以外のもの、属人的な身分とか年功といった要素に惑わされて等級を設定してはならないのです。会社によっては、次長、部長代理、副部長、課長代理のような職制まがいの「職位」が設けられていたりします。これらの「処遇職位」は、そこに配属されている人の身分呼称ですから、職制区分の対象となるものではありません。なぜならそれらの身分には、仕事の条件としての明確な職務分掌が存在しないのです。
自社の等級を設定するに当たって大切なことは、現在の部長、次長、課長、課長代理、主任などの役職についている「人」から必要階層数を検討するのではなく、あくまで仕事の責任の重さ、仕事の難易度、つまり求められる成果責任の重さを中心に据え、過不足ない職制区分として「責任等級」を定めなければならないのです。