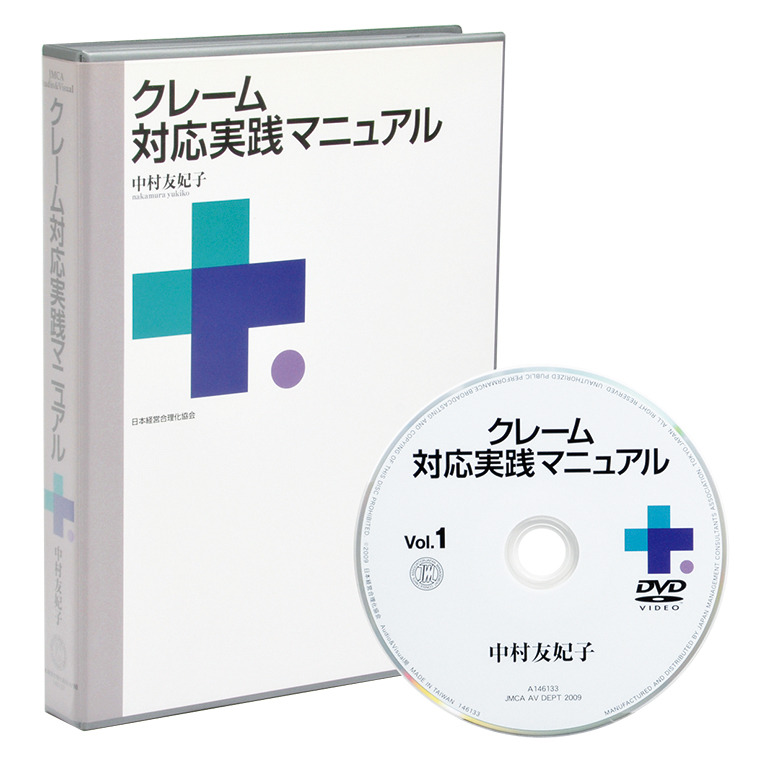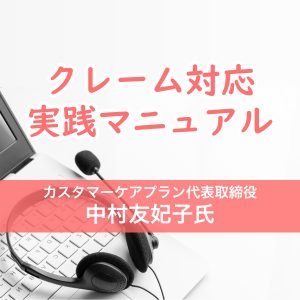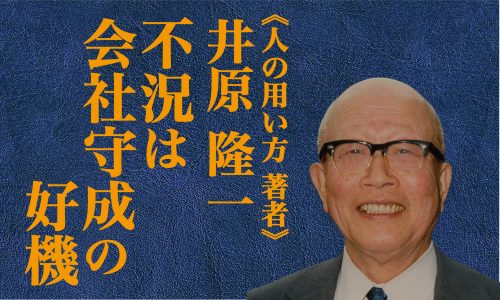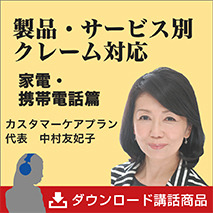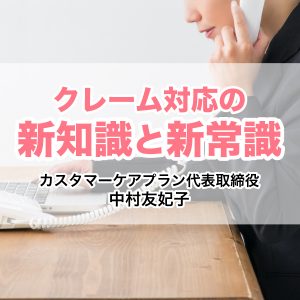クレーム対応のルールを間違って理解しているから失敗する(9)
お客様タイプ別の傾向とその対応方法を提案します
(※秀和システム刊 『ポケット図解 クレーム対応のポイントがわかる本』より、一部抜粋と加筆)
【その1】東北タイプ
あまり物の言い方が厳しいタイプではないので、企業としてはそれほど困難なタイプだとは思えない。しかし企業にとっておしなべて頭を悩ませられるポイントは、方言と言葉の訛り。そもそも方言や訛りがたいへん強いので、担当者に話しが伝わりにくいという難点がありながら、お客様本人はまったく訛っていないと思いこんでいる。だから、なぜ自分の話しが担当者に伝わらないのかわからない。きっと担当者の理解力の不足だと思っているので、担当者が繰り返す「もう一度お願いします」と言う言葉に、苛立ちが高まる。苛立ちと共に興奮も高まりさらに訛りは強くなり、特殊な方言が口から飛び出て来て、さらにお申し出内容を難解にさせる。
問題は、担当者が「もう一度お願いします」と言ったときに、自分の方言や訛りが通じていないのだとは思わないので、まったく同じ言葉で同じ話しを繰り返す。つまり訛りや方言を軽減して一般的な言葉に変えようとすることはない。そのために担当者はまた「もう一度お願いします」と言わざるをえなくなる。そんなことが3~4回繰り返されるので、お客様と担当者の溝はどんどん深くなり、和解の糸口は見つからない状態が続く。そして「なんで、わからないの!何度同じことを言わせるんだ!」と言う意味合いの捨て台詞を吐き、「もういい!」と言うような言葉で幕が引かれる場面が多い。そして、その後知人にこの企業の対応の悪さを吐くことになり、地域性からこの評判は瞬く間に、たくさんの人に広がる。
企業側の対応方法としては、「言葉がわからない」ということをていねいな言葉ではっきりと言う考え方を持つこと。その時のトークとして「たいへんおはずかしいことですが、私としましては初めて聞く言葉が多く、お話しの内容が理解に届かない状況でございます。せっかくこのようにお電話をいただきましたので間違いのない対応をしたいと思います。」と言い、言葉を交わしていても同じ場面が発生するだけなので「今から、FAXで問題をご記入いただく用紙をお送りいたします。それに主な事をご記入いただき送り返していただけますか?ご記入いただきましたFAXが私共に到着次第、私の方からお電話いたします。お手数をおかけいたしますがお願いできますでしょうか」と口頭だけで対応しない、書面で補助をする対応にする。
但し、この場面で口頭で教えていただくFAX番号の解読の難解さは免れることはできないことは考えの中に織り込んでおく必要がある。
【その2】関東タイプ
最初は感情的な態度はとらない。むしろ「感情的な下品な客にはなりたくない」と自分の感情を押さえながら不満の説明をする。企業にとっては一見、あまり怒っていないお客様のように感じるが、その落ち着きを支えているのはそのお客様に武装された理論に勝ち目がある自信である。なので鼻から論理戦に持ち込もうとする傾向が強い。
まずは担当者に対して質問で攻めでくる。それも回答するには担当者にとって悩ましい質問、回答するには権限外だとわかっている質問、回答できるはずがない質問、回答したからってどうなるの?という意味の無い質問、回答がわかりきった質問など、解決に導くためではない質問が始まる。うっかり担当者が軽々しい回答をしたならば、その回答の一部分の揚げ足をとりさらに質問を重ねる。その質問に対してまた、担当者は最適な返答ができないために、会話は堂々巡りになり、基本の話題からはどんどんずれて行く。そしてお互い、何が問題で何が最適なのかが見つからない会話の旅を続けることになる。
企業側の対応方法としては、お客様の質問にすぐに回答をしないこと。最適なのは相手の質問には質問で返すこと。お客様の質問にひとつひとつ回答や説明をする対応が誠実で好ましい対応だとおもっているとしたら、たいへんな間違いを信じていることになる。お客様の質問は、企業側の考えを知りたいから発生しているのではない。自分の思いや考えや状況をもっと深く伝えたいから、その前振りとして担当者に質問をなげかけるというのが本音。だから質問に回答がほしいわけではない。このことを頭に入れておかないと、対応は失敗する確率を高める。
なにしろ相手には、きちんとした企業を説得するストーリーが用意されている。それができるだけの商品知識や社会情勢や経済問題を手に入れる手段や機会がたくさんある。つまりお客様の方がある部分では担当者より一枚上手という事がありうる。
「この製品はなぜ**の部分を変えたんですか?」と質問されたら「はい、それはですね」などと回答をしない。「とおっしゃいますと、変更したことでなにか差し支えることが発生しておりますか?」と質問。また「その詳しい説明はどこに書いてあるんですか?」と質問されたら「はい、それはですね」と回答をすぐにしない。「恐れ入りますが、お客様はこれまでどのようなもので確認をされましたか?」と質問をする。質問をすることは、相手の本音が聞けることにつながる。お客様は製品やサービスのことを知りたいのではない。都会に住むお客様は「自分のことをわかってほしい」と無意識に願っている。だから、もっとわかって差し上げるためにお客様に質問をすることが大切。