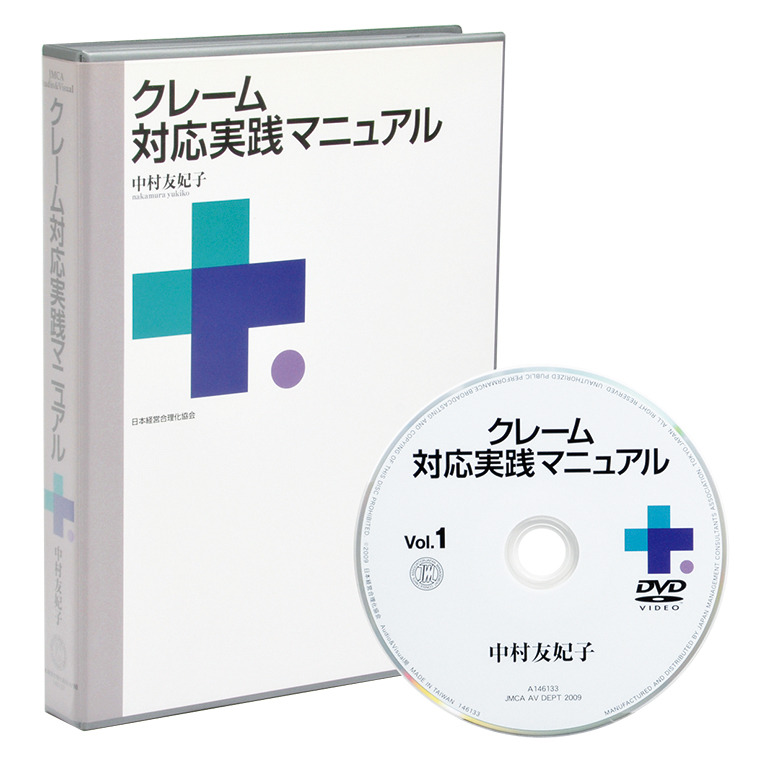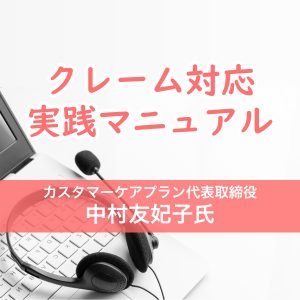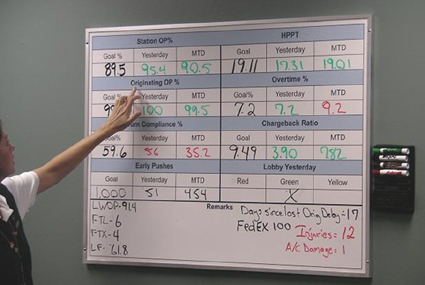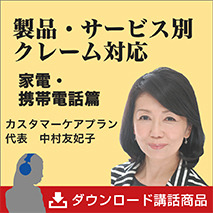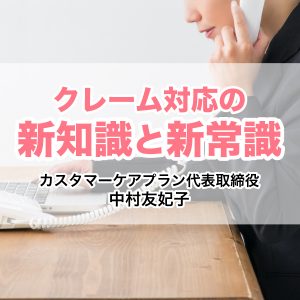クレーム対応のルールを間違って理解しているから失敗する(10)
さらにお客様タイプ別の傾向とその対応方法を提案します
(※秀和システム刊 『ポケット図解 クレーム対応のポイントがわかる本』より、一部抜粋と加筆)
【その3】中部タイプ
地域を限定して例えると京都から名古屋そして静岡までの地域に多く見られるお客様の傾向。とてもおだやかで、言葉も悪くないお客様が多い。だからものわかりのいいお客様だと安心をしたら、長引く対応になってしまう恐れが高いタイプ。「こちらの思いはこちらに言わせるのではなく、そちらが察するのが当たりまえ」だと思っている。だからひどいことは言わない、大きな声は出さない、感情的ではない態度で関わってくる。企業特有のうわべだけの説明、社交辞令のお礼言葉やお詫び言葉は大嫌い。だからと言って深い説明も、担当者の芝居じみた話し方も嫌い。「お互い表面上さわやかに」「お互い表面上すがすがしく」話し合いをし、自分の察してほしい結末になることを望んでいる。もし、自分の思う結末にならない場合は、上品な態度で執拗に関わり続け、あきらめようとしない。
企業側の対応としては、相手のおだやかさに油断をしないことがもっとも重要。まずは、お客様にたくさんしゃべらせて、言っていること以外に何があるのかを察する作業をしなければならない。言っていることだけを鵜呑みにしない、信用しない。言っている言葉だけを捉えてうっかり相手の質問に拙速に回答をしたりすると、いっぺんに機嫌を損ねる。一度機嫌を損ねるとたいへんやりづらい。不機嫌になりながらも本音は言わない。自分の希望を露骨に言わない。あくまでも担当者に察しさせようとする話しぶりが続く。だから本音や希望がさらにわかりづらくなる。たくさん話しを聞いた結果、企業側が必ずやらなければならないことは『提案』。「~~~ということをさせていただきましょうか」と企業から言うことが必須。「私が強要したのではない。企業側から提案をしてきたんだ」というスタンスを守らせ続けられるようにしてさしあげなくてはならない。
「決して自分は、厚かましい客ではない」というイメージを崩さないようにしてさしあげなくてはならない。担当者は自尊心の塊に対応しているという考え方を持つことが必要。提案も「これを提案すれば、あなたの気持ちが納まるんでしょ!」という雰囲気で提案を差し出してはいけない。「あなたにたくさん教えてもらった、気づかせてもらったので、私のお礼をしたい気持ちが収まらない。だから~~~ということを提案したいのですが、いかがでしょう」という表現で伝えることが大事。決してあなたのために提案をするのではなく、私の気持ちのために提案をしたいという意味合いを持たせることが、相手の気持ちに伝わる伝え方。そうでないと自尊心が傷ついて、「私はなにかの提案を求めるようながめつい客ではありません」というような意味合いの新たなクレームを言われることになる。
ちなみにクレーム対応担当者達にとって、困るお客様地域タイプのNO.2だと、担当者の間ではささやかれている。
【その4】関西タイプ
早速だが、クレーム対応担当者達にとって、困るお客様地域タイプのNO.1だと言っても異論を唱える担当者は少ないと思う。何が困るかというと、東北タイプとは異なる『話し言葉』の問題である。単に関西言葉を使っている、関西イントネーションで話しているということであるのにもかかわらず、他府県出身の担当者達には、恫喝や脅かしに聞こえてしまうという効果が関西弁にはある。その為に、担当者達は恐怖感に襲われて冷静に話しを聞けない、威圧感につぶされそうになって早く別れたいと思う、クレーム対応担当者としてあるまじき意識が高まる。そしてその担当者の事務的な態度にさらにお客様の怒りは高まるという悪循環が、和解を遠ざけるという状況に至らしめる。
そもそも関西タイプのお客様は自分の思いや考えをわかろうとしてほしいと思って連絡をしてくる。言いかえれば、企業側の考えや、故障の原因や、修理の方法などは知りたいとは思っていない。つまり、企業側のことは理解するつもりはない。でも自分の希望をかなえてほしいと思っているのでもない。自分の希望はかなえてもらえないかもしれないけれど、自分がなぜこんなに声高にささいなことを訴えているのかの、理由や思いをわかってほしいと思っている。だからしゃべっている間に、本音はどんどん言ってくれる。恥ずかしいくらいの素直な言葉を用いて自分の思いを言ってくれる。本音を言っているお客様の担当者への思いは、「もしかしたら企業としては解ってもらえないかもしれないけれど、せめて担当者にはわかってもらいたい」「自分の人柄を否定しない人が一人でも増えてほしい。」と無意識に欲求している。欲求通りの態度が担当者に感じることができれば、少し気持が納まる。担当者がどのような態度を見せてくれたら自分の気持ちが納まるか、自分で自分を知っている。だから一生懸命大きな声で、抑揚豊かに自分の状況を伝え続ける。しかし担当者が肯定的な態度を見せないとなれば、自分を否定されているように感じ、ショックをうけてどんどん興奮し、言葉がどんどん悪くなる。自分でも他人に使ってはいけない言葉だとわかっていながら、悪い言葉を言いたくなる。言ってしまう。
企業側の対応としては、とにかくしゃべらせること。そしてその会話の中で肯定をする態度を見せること。肯定をする態度というのは単純に迎合し、共感する言葉を言う事ばかりではない。相手の話しに質問をすることで、「あなたの考えに興味があります」と言う態度を示すことになり、肯定的な態度に見える。また相手の話しの一部分を短く復唱することで「あなたの状況をもっと知りたいです」という態度を示すことで肯定的な態度を感じさせることができる。そして本来はしなくても良いのだけれど、担当者がめんどうくさがらずに、めんどうくさいひと仕事するような提案をすること。その提案そのものは大した提案でなくてもかまわない。製品やサービスに想定外の現象が発生して混乱しているお客様に、担当者が手を差し出したかのような態度を表すことが大切。その態度が相手に「この担当者は私の考えを理解しようとしている」という気持ちを発生させることができる。そして冷静な気持ちにさせることができやすい。
関西弁の言葉の恐怖を味わいたくないのであれば、企業を気に入らせようと理論で理解させようとしないで、担当者を気に入ってもらうように意識を高めて、会話をすることがポイントとなる。
以上はこれまでの私の対応経験の中で培った意識であり、研究発表された正式なものではありませんことをあらかじめお伝えいたします。
また「**タイプ」と記載していることは「**地区に住んでいる人」と特定の方を指しているのではありません。現代ではその地域に住んでいる人がその地域で生まれ育ったとは限らない状況です。
ですのでその地域に現在住んでいるお客様だからといって、ここまで記載したタイプ分析や対応方法がマッチするとは限りません。ここで述べたタイプ別の説明は、クレーム対応担当者の考え方の一つとして、引き出しを作ってしまっておいた方が良いと思う考え方です。
しかし実際に引き出しを開けて、その対応方法を使った方が良いかそうではないかは、クレーム対応担当者のあなたが判断してください。何といってもクレーム対応はあなたのスキルと感性なしには、和解に到達することはできない専門職なのですから。