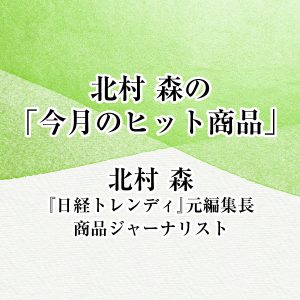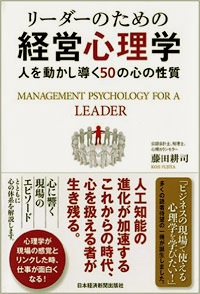緊急事態宣言が全面解除となっても、観光業はまだまだ厳しい状況であるとの声が漏れ聞こえてきます。私も微力ながらなんとか応援したいと思っていますが、都内に住む私が都境をまたいで移動できるのは、もう少し先のことになりそうです。
今回お伝えしたいのは、都内にある小さな家族旅館の話です。その名を「澤の屋」といいます。ああ、あの宿か、と思い浮かぶ方もいらっしゃるかもしれませんね。
東京・谷中にあり、客室数はわずか12。去年で創業70周年を迎えているのですが、1980年前後に存亡の危機を迎えます。それまでの主力客だったビジネス客や修学旅行の客が、一気に離れていったのです。各地に新しくできたビジネスホテルへと流れたのでした。家族経営の小さな旅館はもうダメ、とも言われていたなかで、澤の屋はひとつの決断をくだします。それは……「外国人観光客にシフトしよう」という判断でした。

それ以来、世界92カ国、のべ19万人以上の外国人観光客を迎え入れてきたといいます。バックパッカー向けというわけでもなく、あるとき、澤の屋がお客さんのことを調べたら、訪れる外国人客の平均年収は日本円にして1000万円超、なかには1億円という人もいたそうです。「日本の生活文化をありのままに感じられる」という口コミが世界を駆け巡った結果だったのですね。
そして澤の屋は、満室続きの宿となりました。
ここまでのお話は、メディアなどですでに多く取り上げられているところですね。絶滅寸前ともされた家族旅館が見事に復活した事例として。
今回お伝えしたいのは、ここからなんです。このコロナ禍で、澤の屋もまた大打撃を受けます。それはそうですね。昨年の宿泊客をみますと、外国人が87%を占めていたほどですから……。3月の終わりから4月にかけて、宿泊客ゼロという日が続き、もはやこれまでか、との思いもよぎったと聞きました。
澤の屋は、暖簾を下ろしたのか。いや、そうではありませんでした。
インバウンドのお客さんが来てくれるのは無理ならば、と、貸し切り湯のサービスを始めたのです。この宿には、それぞれ檜と陶器の湯船をしつらえた、2つの浴室があります。せめてそこを国内のお客さんに使ってもらえれば、と考えたのですね。大人500円と、貸し切り湯にしては手頃な料金としました。
また、リモートワークに使ってもらおうと、客室のデイユースも開始しました。9時から19時までの10時間利用で3300円。貸し切りのお風呂も使えます。
もちろん、売り上げはささやかな水準に留まりますけれど、できることをしようという考えだったわけですね。
で、そうした施策を打ったら、どうなったのか。

まずやってきたお客は、ほかならぬ地元の人たちだったんです。「そりゃそうだろう、貸し切り湯といったサービスだったら、最初に訪れるのが地元客というのは当たり前じゃないか」と思われるかもしれませんが、私がお伝えしたいのは、じゃあなぜ、地元客の来館が一過性には終わらず、次々と澤の屋にきたのかというところです。
「澤の屋が困っているらしい。だったら行ってやろうじゃないか」と地元の人たちが動いたらしい。「これまでずっと満室だったから行けなかったけれど、この機会だったら」とも……。
谷中の商店主の人たちだって、大変な困難にあるはずです。それが、なぜそこまで?
いろいろ話を聞いていくと、要はこういうことだったらしい。
今から40年近く前、澤の屋が外国人向けに舵を切ってから、この宿のご主人は谷中近辺の飲食店や小売店に、外国人のお客さんを送り続けていました。ただ単に客に周辺店の情報を教えるだけでなく、店の側に相談に通って、(当時は珍しく、しかも彼ら彼女らの習慣もよくわからない)外国人客を相手にするときにはこう対応していただければ、と丁寧に伝えていたと聞きました。店の入り口に「WELCOME」と小さく掲げるだけで外国人は安心します、とか、簡単でいいので外国人にもわかるメニューを作成してもらえないでしょうか、とか……。
澤の屋のご主人はいいます。
「当時、旅館というのは、地元の町との関係は必ずしも密接ではなかったかもしれない。町の店々と協力などしなくてもお客は訪れていましたからね。でも、ウチを外国人向け旅館とする際、夕食の提供はやめましたし、お客さんは町を散策したいと思ってやってくる。となると、地元との連携は極めて大事になるんです。だから動いたのです」
なるほど。澤の屋と、地元の商店主たちとの深い関係は、一朝一夕にできたものではなかったんですね。それだからこそ、澤の屋の危機に、今度は商店主たちが動いたわけです。
これ、参考になるところ、ありませんか。平時に関係を築くことが、いざというときに大事になってくる。もちろん、危機的な事態に陥る場面を想定して、普段から連携を取っておきましょう、という浅薄な話ではありません。これからは事業者単体で何かを成し切れる時代ではますますなくなってくる。だからこそ、ということです。
澤の屋は、来年に向け、経営を存続することを決めたそうです。ここにきて来春の予約が、それも海外から届いているらしい。「家族で話し合ったすえ、予約を受けることにしました」とのことです。もちろん、来年の今ごろがどうなっているのか、誰にもわからないでしょう。でも、先の予約を心の支えにしながら、そして地元からの声援を受けながら、澤の屋は踏ん張っていくという話ですね。