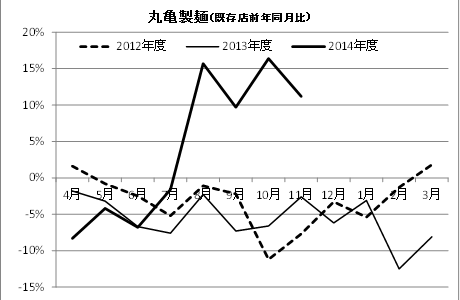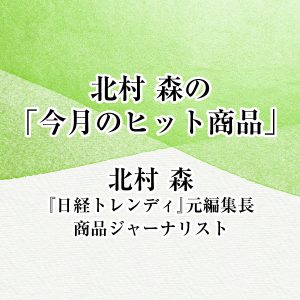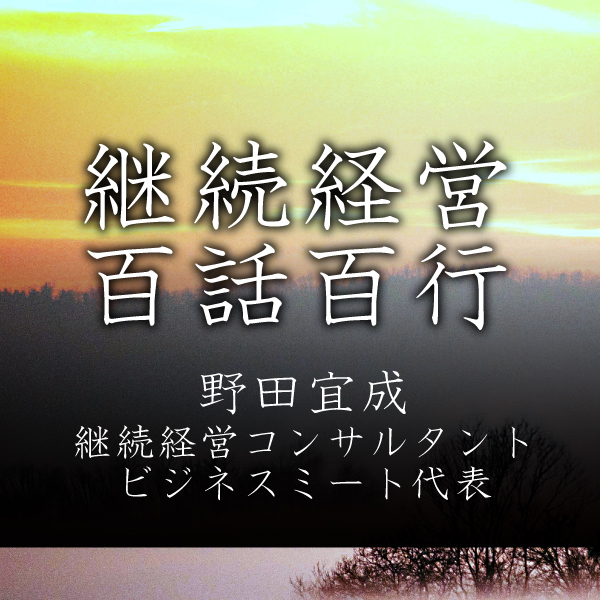地域マーケティングで大切な3つのこと
前回(2023年5月)の本コラムで、「必然性のある商品開発を!」と題して、「四万十川天然鮎のコンフィ」の話を綴りました。
ちょっとだけおさらいします。地域マーケティングで大事なのは次の3点だと、私はいつも考えています。
「足許にある宝物をきちんと生かすこと」
「必然性ある商品開発を心がけること」
「やってはやめて、ではなくて、長く続けること」
で、今回のテーマです。私自身がお手伝いしている事例の話であるのをお許しください。上記3点を目指している取り組みであり、読者の皆さんにご理解いただきやすいテーマと考え、綴りたいと思います。

鹿児島県の種子島は、さとうきびの生産地として知られています。さつまいもや米よりも作付面積は広く、島を訪れると、風に揺れるさとうきびの景色をいたるところで目にすることができます。
こうしたさとうきびは砂糖に加工されるわけですけれど、「それだけでいいのか」と地元の製糖会社が動きました。この島に根づくさとうきびをさらに違うかたちでも生かすことはできないか、それによって、島の未来に光を照らすことはできないか、という話です。
この製糖会社(大東製糖種子島といいます)は、考えに考えたすえに、ラム酒の蒸留所を立ち上げ、世界で勝負できる一杯をこの島から送り出そうと決断しました。
ただし、島で育てられているさとうきびは行き先がすでに決まっています。あくまで砂糖の原材料ですから…。そこで同社は畑を借り受けて、さとうきびを新たにみずからの手で栽培することにしました。製糖会社の社員が慣れない農業に従事するわけですから、大きな判断であったと想像します。
でも、この判断にはもうひとつの意味がありました。ラム酒づくりのためにどんな品種のさとうきびを育てるか、自分たちで決めることができるからです。検討を重ねた結果、黒海道(くろかいどう)という名の品種を植えることにしました。生産効率はさほどよくないのですが、ラム酒にするのに適した糖度が確保できるから、という理由でした。
そして2023年春、そのさとうきびは収穫期を迎え、第一号のラム酒づくりが始まりました。農業が初めてなら、酒づくりも初めてのことです。同じ鹿児島県の酒造会社がひと肌脱いでくれ、技術指導を買って出てくれました。また、そのブランディング戦術作成について、私(北村)に声がかかったという次第です。

第1号の蒸留を終えたラム酒は、いまタンクの中で眠り、この秋の出荷を待っています。長期熟成しないタイプのラム酒でも数カ月、眠らせることが必要だからです。
ラム酒の話を少しだけします。ラム酒は大きく2種類の製造法に分かれます。ひとつはインダストリアル製法と呼ばれるもので、砂糖をつくる工程から生まれる廃糖蜜を原料としています。これが世界のラム酒の95%ほどを占めるらしい。
では、残り5%は? それがアグリコール製法と称されるラム酒です。砂糖製造の副産物を用いるのではなくて、ラム酒をつくることを目的にしてさとうきびを搾り、その搾ったジュースを酵母の力でそのまま発酵させ、蒸留するというもの。
贅沢な製造手法であるアグリコールですが、そのぶん「ああ、ラム酒ってさとうきびからできているんだな」とたちまち実感できる甘い香りと味わいを得られます。
で、この種子島のラム酒ですが、アグリコール製法を全面的に採用しています。なぜか。島のさとうきびを生かしきるのがこの事業の目的ですから、当然、アグリコールの一択となるわけです。グラスに口をつけた瞬間に、さとうきびの存在感を知ってもらうには、もうこれしかないと踏まえたという結果の選択でした。

ここまでの話で、冒頭に挙げた2つのポイント、「足許にある宝物をきちんと生かすこと」「必然性ある商品開発を心がけること」をちゃんと大事にしながらラム酒づくりに臨んでいるところまではご理解いただけたかと思います。
では、「やってはやめて、ではなくて、長く続けること」については?
ラム酒好きといいますか、お酒好きの方なら、もうご想像に難くないと思います。ラム酒には、長期熟成をかけない透明な「ホワイトラム」のほか、樽熟成を経てボトリングする「ゴールドラム」や「ダークラム」があります。
蒸留所を一度立ち上げたからには当然、中長期熟成のラム酒を世に送り出すこととなります。何年、いや何十年と続く事業となるわけです。大東製糖種子島は、その意味で腹を括ったのだと感じています。始めたら簡単にやめられる事業ではないのですから。
ラム酒のブランド名は「ARCABUZ(アーキバス)」といいます。ポルトガル語で火縄銃の意味です。種子島は火縄銃の伝来の地ですから、こう名づけています。お手伝いしている立場としても、この「ARCABUZ」が地域マーケティングの好事例に育つことを願っているところです。
「ARCABUZ」のウェブサイトは下記です。もしよかったらご覧ください。