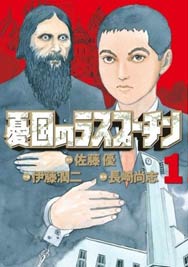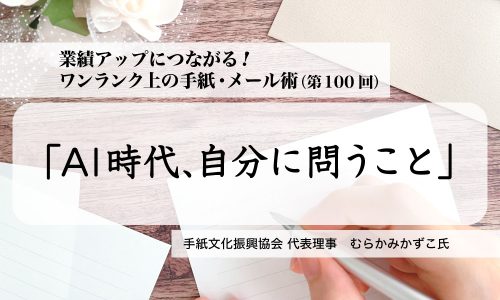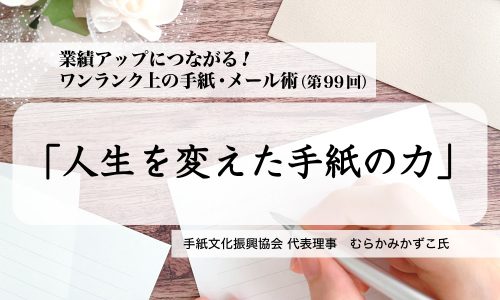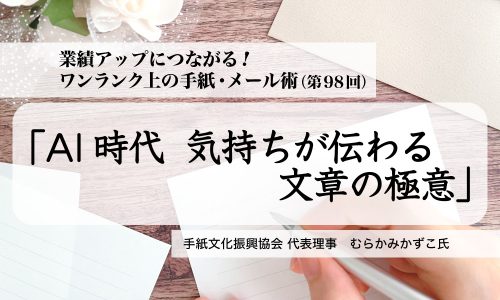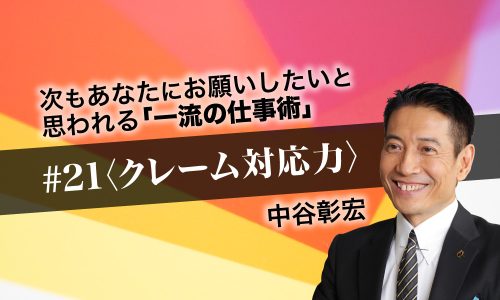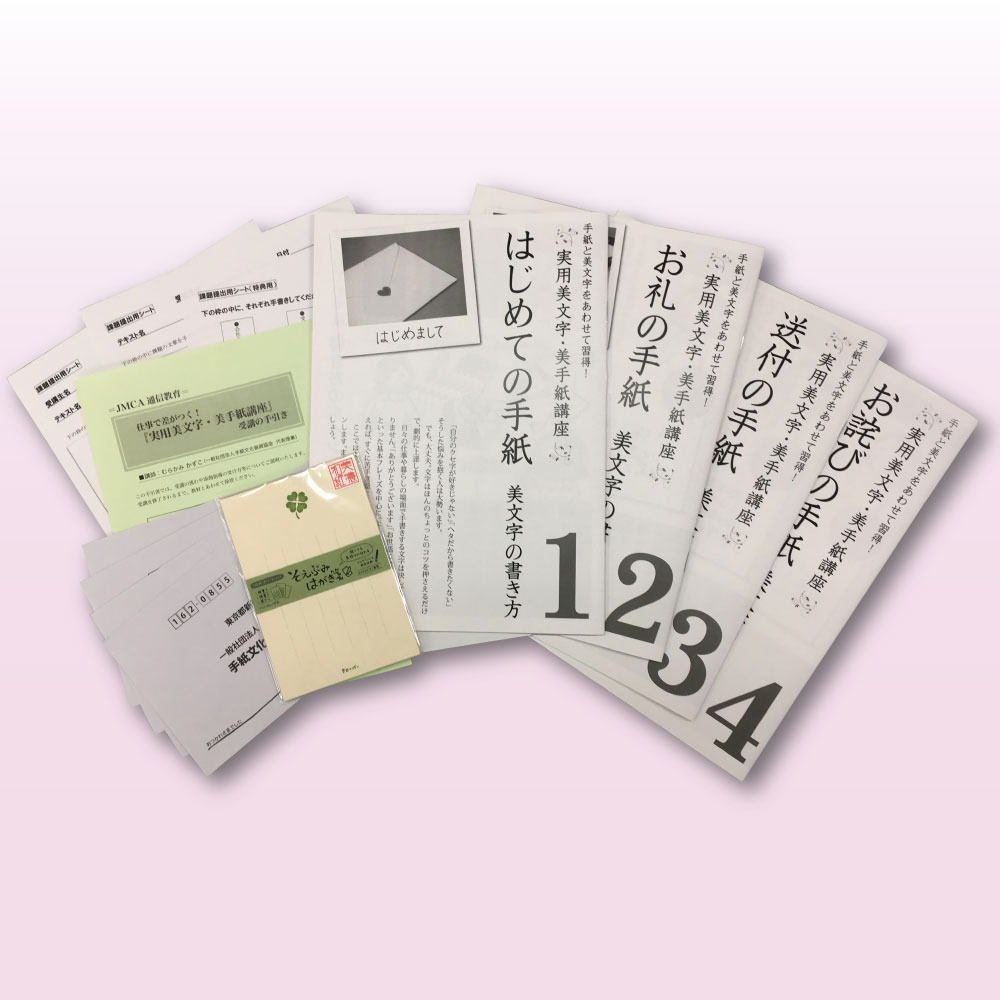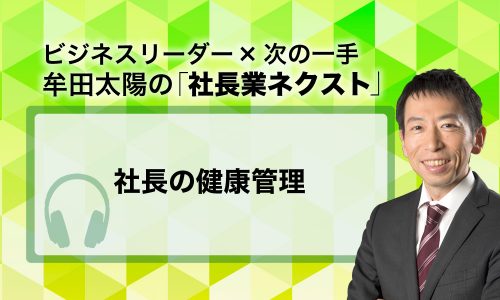スマホ時代、AI時代。
世の中がどんどん進化・変容していく今、そしてこれから、絶滅と思われている「手書き(ハガキ)」が、実はお客様との関係づくりの特効薬になりえます。
セミナーや書籍等を通してその価値に気づき、「お客様に宛てて手書きのひと言を送り、信頼関係を築く」ことを試みている企業は多くあります。
しかし、筆者や、筆者が代表をつとめる弊協会の講師たちが研修講師として企業に訪問すると、そのほとんどが「実際に書きはじめたものの、継続できない」という悩みに直面していることに気づきます。
それもそのはず。手書き(ハガキ)を継続して実践するためのノウハウは、世の中にほぼゼロに等しいのです。
手書き(ハガキ)を継続するには、
1. 書き方(スキル)
2. 仕組み
3. マインド
以上の3つの面から問題点を解決していく必要があります。
1の書き方(スキル)は拙著『お客の心をつかむ 売り込みゼロの3分ハガキ術』(日本経済新聞出版社)にくわしいので、よろしければご参照ください。
2.仕組み、3.マインドについては、今後、このコラムでも随時、紹介してまいります。
今回は1つ、以下の悩みにお答えします。
Q.一人のお客様に何度もハガキを送るのは失礼にはならない?
A.失礼にはなりません。
書く側と受け取る側には大きなギャップがあります。
書く側は相手(お客様)を思って夢中で書きますから、そこに強い思いがありますが、受け取る相手はいたって気楽なものです。
相手はそのハガキを受け取るとき(=たとえば、家庭の主婦が自宅の郵便受けを開ける瞬間だとすれば)、今夜の晩ご飯のおかずとか子どもの塾の送り迎えとか、まったく違うことをボーっと考えていたりするわけです。
自分宛てに届く手書きのハガキは、月に何通あるでしょう?
印刷のみの機械的なダイレクトメールならさておき、手書き文字でメッセージが書かれているものは、普通の人であれば多くても月に1通~2通です。
思いがけないときにポストに届いた手書きの1通は、案外うれしいものです。
“自分のことを覚えていてくれたんだ。何かあったら〇〇さんに声をかけてみよう!”と感じるのが普通の人の感覚です。
書く側は一度に大勢のお客様にハガキを送ります。すると、一人のお客様に何度も何度も書いているような思い違いをすることがあるのです。
そう考えると、実際には、相手が「不快に」感じるほど多くを送っていないことに気づくでしょう。
自信をもって続けてください。