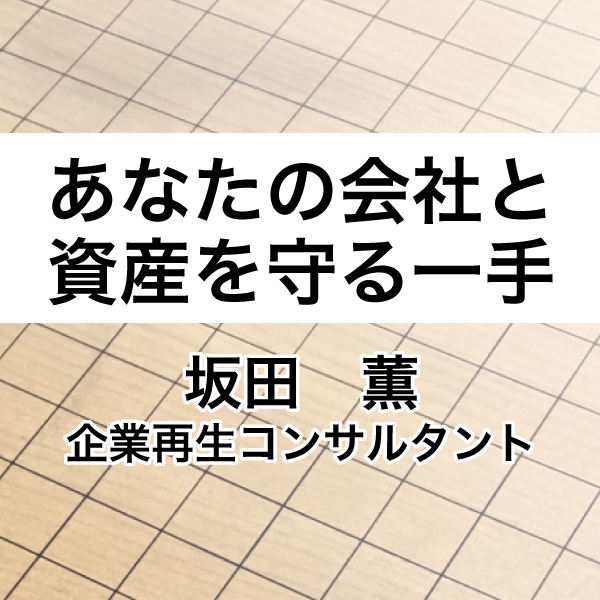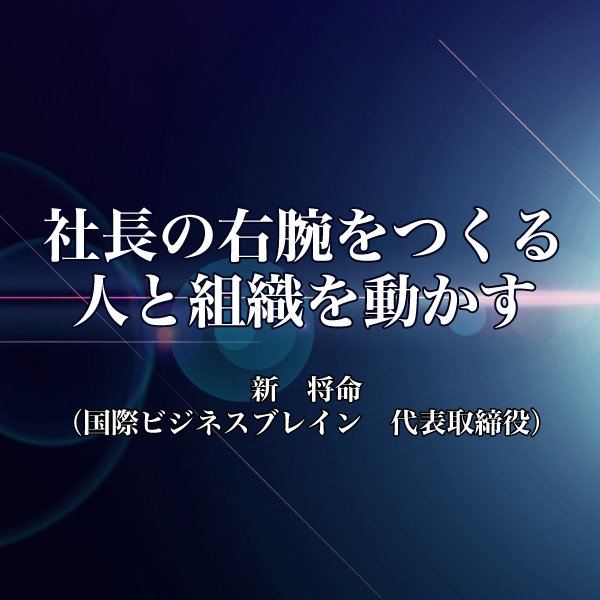忠臣蔵の主人公である大石良雄のリーダーシップは、泰平の世の徳川中期の頃には、比類なく目立っている。武家のリーダーシップを考える場合、血統が物を言うことは源頼朝や足利尊氏の例でも明らかであったが、大石良雄の場合もそうである。
赤穂の浅野家の中において、大石家は代々重臣である上に、殿様のお姫様をいただいた者もいる。つまり大石良雄は、家老であると共に、殿様の親類筋でもあった。
他にそういう重味のある家系の者がいなかったのであるから、彼がみんなにリーダーとして仰がれ易いのは当然であった。大石以外の人では、浪人になった他の武士たちを多くまとめることは不可能であったろう。これが封建時代というものである。
しかし名門というだけでは、お家断絶という非常時にはリーダーになれるわけはない。ふだんは大石は昼行燈(ひるあんどん)と言われるくらい冴えない男だった。それにいかにも元禄武士らしく遊び好きでもある。
殿様の浅野内匠頭も大石のような人物を好まず、大石は年に何回も家で謹慎するよう命じられたとも言われている。奥さんも子供を連れて実家に帰ったことが何度もあると言うから、今で言えば、オーナー社長に出社停止を言い渡された同族の専務みたいなものである。
幕藩体制の下での本当に平和な日々においては、人の器量はなかなか分からない。同じ家老でも大野九郎兵衛のような日常事務の得意な者が殿様に重用される。
ところが一旦緩急あると、突如として人間の本当の器量が現れる。大野は早々に退散する。大石は泰然として万事を非のうちどころなく見事にこなす。赤穂開城の際のリーダーシップの見事さは大名の間でも評判になり、大石を召し抱えたいと申し出た大名が十人近くもいる。
これはどういうことか。佐々淳行氏の本でも、東京空襲の時に、慌てふためいたのは防空班長などで平生は威張っていた人で、冷静だったのは、いつも本ばかり読んでいた佐々さんのお父さんとか、近所の数学の女教師だったそうである。
大石は遊び人ではあっても、山鹿素行の学問を身につけ、東軍流で剣術を磨いていた。特に、平生から組織的に思考する訓練をしていた。だから殿様の切腹から、吉良邸討ち入りまで、今からみると整然として筋が通っているのである。
先ず、殿様の弟による浅野家再興を第一と考える。しかしそれが駄目な場合も考えて仇討ちの路線も、表には出さないが捨てていない。浅野家再興の望みが断たれた時点から「亡き殿の無念を晴らす」ことに全力をそそぐ。
大石が偉いのは「お金」を重視したことである。まず藩札を実際のお金と引き替えることをやって領民を完全に静かにした。お城にあったお金を上に薄く、下に厚くなる割合で配分して家中の者を沈静させた。
自分は分配金を辞退している。浅野家再興費として残した一万両や殿様の未亡人の持参金などの用途も明快である。そこからは浪人した同士の生活援助費も出ている。
討ち入り四十七人のうち、四十二人は直接、大石からお金を受け取っている。面白いことには浪士たちから一々受領書を取っていることだ。未亡人関係のお金は約六九〇両あったのだが清算すると七両ぐらい計算が合わない。
その分は大石が自分で出して、残金とその帳簿を未亡人のところに討ち入り前にとどけている。当時の武士で「お家断絶」という大変事に当り、一両まで領収書つきで帳簿で明らかにするような人がほかにいたであろうか。
お金についてもこれほど正確にやっているのだから、他の手配が萬全だったのは当然と言えよう。特に討入り直前にみんなに誓わせた文章は感激的である。
解り易く要点を記すと、その第二条には「吉良家に討入りした場合の功績は、任務によって差はない。上野介殿の首をとった者も、門の警戒に当たっていた者も、同じ手柄とする。」
その第三条には、「お互に平生は仲のよい人も悪い人もあろうが、この際はお互に助け合い、勝利の全きところを専らにして働くこと」としてある。
「勝利之全所を専に」というのは古今の名言である。目的達成のためには、私情も捨てよというのだ。この前の日本の高級軍人たちがこの精神であったならばと思わざるをえない。
何しろ責任者の出ることを怖れてミッドウェイ敗戦の検討もやってなかった。勝利をうるよりも上官のメンツなどの方が重要だったような場合があまりにも多かったことを、今更ながら残念に思う。
渡部昇一

〈第17人目 「大石良雄」参考図書〉
「大石内蔵助を見直す
勝部 真長著
学生社刊
本体1,800円