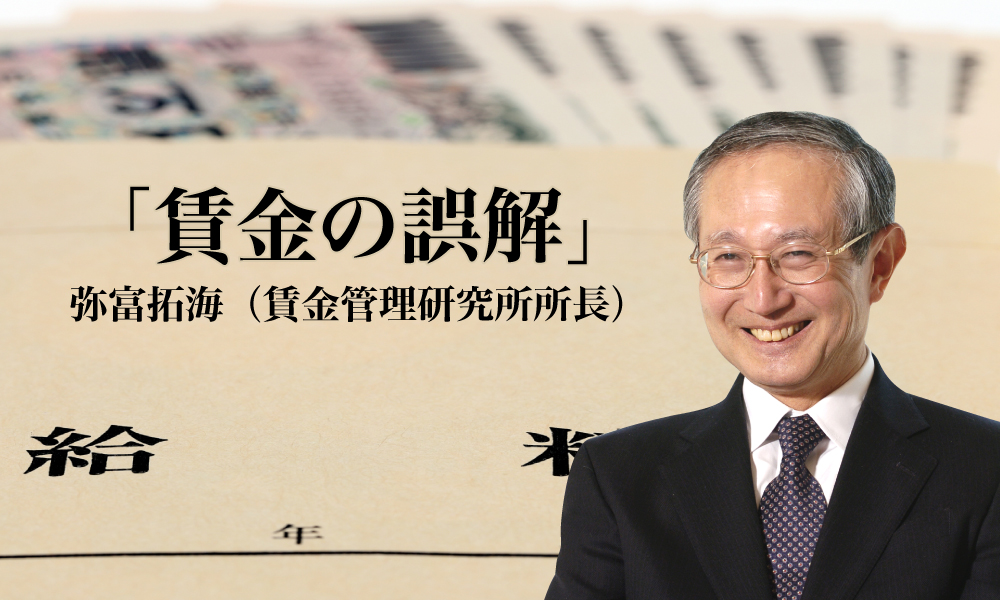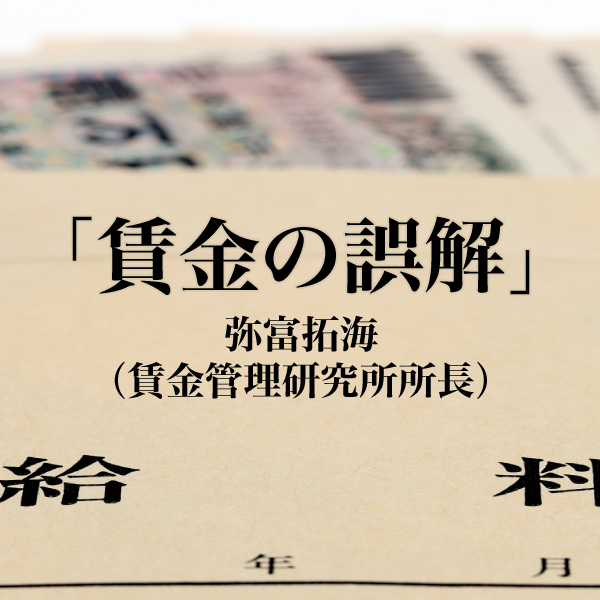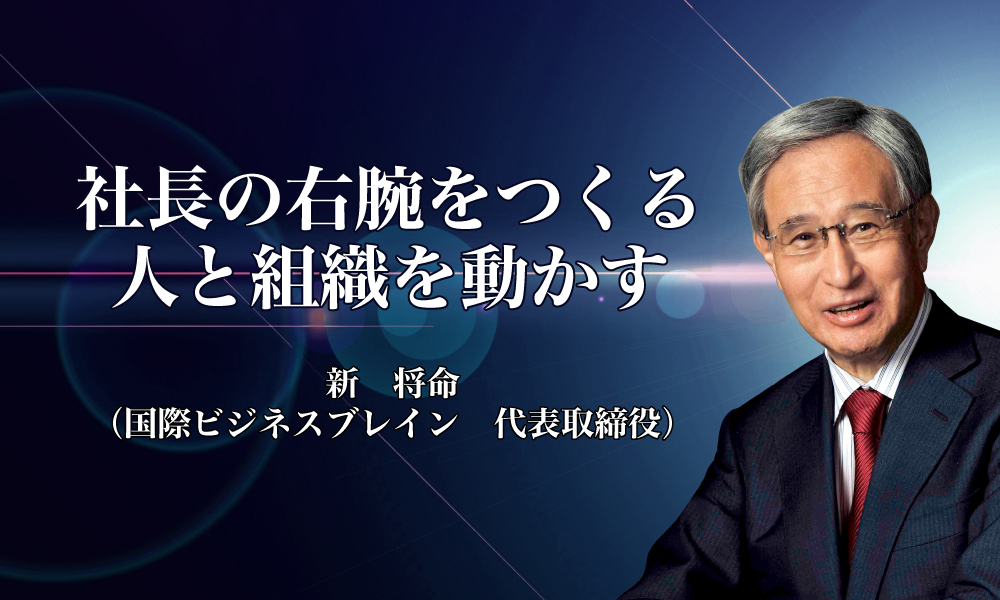明治維新は経済的に言えば、日本が自由主義経済国、あるいは資本主義の世界に入ったことを意味する。徳川時代は町人の勢力が徐々に発展してきていたとは言え、政治権力にはなっていなかった。このことを体験して討幕を志した青年が今の埼玉県の村に生まれた。日本の経済を維新後に軌道に乗せたリーダーの渋沢栄一である。
彼の生まれたのは農業と共に養蚕や藍玉製造もやっている富裕な家であった。ところが当時の領主が金に困って富裕な家に寄付金を強要する(冥加金と言った)。ところがその金を献上する側が代官の前に跪いてペコペコしながら差し出すのだ。こんな情景を見て少年栄一は「こんなバカな話があるものか」と憤慨する。
そして江戸に出て―金がある家だから学資に困ることはない―漢学を海保塾で学び、剣術を千葉道場で学ぶ。そして文久三年(一八六三)―薩英戦争があった年―同志を集めて攘夷を決行し、その手始めに高崎城を占領する計画を立てたが、親類にとめられて中止した。
ところが妙な縁でその翌年、平岡円四郎の推薦で一橋家の家臣になった。そして財政的にすぐれた才能を発揮したのが認められ、勘定頭に抜擢され、更に慶応三年(一八六七)には将軍徳川慶喜の弟の昭武が日本政府代表としてパリ万国博覧会に出席する時に、財布を預かる役目としてヨーロッパに渡った。
そしてフランスはじめヨーロッパの先進諸国を廻り、すぐれた工業技術や経済制度を直接に見学して、将来の日本のあるべき姿をはっきり頭の中に焼き付けた。途中で幕府は潰れたが、彼は当時の留学生たちの経済的配慮も落度なくやって帰国し、一時、慶喜のいる静岡藩に仕えた。
しかしこのような有用な人材を、富国強兵を目指していた―つまり欧米先進国に追いつき追い越すことを目指していた―明治政府が放っておくわけはない。
新しい貨幣制度、租税制度、国立銀行制度など、彼が関与しないものはない。しかし健全財政主義―入るを量って出づるを制す―を奉ずる彼の意見は政府に容れられず、三十四歳の時に退官。以後、死ぬまで民間人として日本の経済界に盡すことになる。
まず第一国立銀行を立て、更にその他の銀行の設立、手形交換所、製紙会社(王子製紙)、主要紡績会社、日本郵船、民営鉄道、造船会社、肥料会社、電力会社、ガス会社、東京株式取引所、帝国ホテル…など、その後の日本の株式市場の重要銘柄になった多くの会社の設立の推進力となった。
しかし彼は三井、三菱、住友、安田のような財閥を作らなかった。作ろうと思えば簡単であったろう。しかし私欲を捨てて、日本に株式会社という資本主義の基本的制度を普及させ、根付かせようとしたのであった。
岩崎弥太郎が渋沢と手を組んで日本の経済を支配しようと申し出た時、渋沢は、「それは日本のタメにならない」と言って断ったと伝えられる。渋沢は自分が関係し設立した銀行や会社の株の一割以上は持とうとせず、それを欲しがる関係者に渡したが、利益の上がらない株だけを手許に置いたとも言われる。
渋沢のこの清廉さは誰でも知っていたから、財界・経済界の大御所としてみんなに尊敬された。大臣になるようにすすめられても一切ことわり、民間経済人の向上のみに心懸けた。「論語と算盤」は両立すると唱え、自ら実践し、経済人の道徳心を覚醒しようとした。
また東京高商(今の一橋大学)はじめ多くの実務の学校を建て、孤児院などの社会事業にも熱心であった。特に民間による国際親善に努力し、彼の邸宅を訪ねた外国人要人は千人を超え、また彼自身も老躯をかえりみずアメリカに渡って日米親善をすすめた。
しかし大正十三年(一九二四)にアメリカが排日移民法を成立させた時は、落胆、かつ憤慨して、次のような趣旨の演説を帝国ホテルでやっている。
「自分は日米の親和に努力してきた。日本が移民をアメリカに送り、日本がアメリカから物資を購入するのは両国のために良いと思っていた。しかし今やアメリカは日本から移民を入れない、土地を相続させない、というようなことをやりだした。これを見ると、私は青年時代に攘夷をやろうしたが、あの時の志を捨てなければよかったと思うくらいだ」と。
温厚、無欲な八十五歳の渋沢がこれほど怒ったのだ。昭和天皇も「日米戦争の遠因はアメリカの対日移民政策であり、近因は石油禁輸である」と言われた。これが歴史の本当のところであろう。渋沢はその七年後、九十二歳で病没した。民間人としては珍しく子爵も授けられている。
渡部昇一

〈第26人目 「渋沢栄一」参考図書〉
「公益の追求者・渋沢栄一 」
渋沢研究会 編
山川出版社 刊
本体2,500円