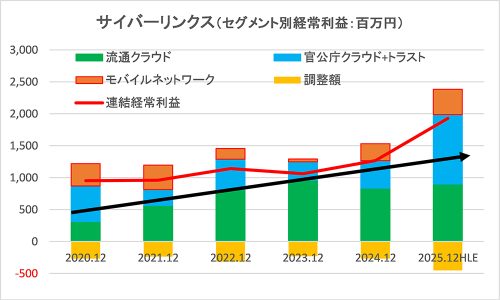経営者の使命は「長期利益」を創出し続けること
34年ぶりの日経平均最高値は企業の稼ぐ力の重要性を改めて浮き彫りにしている。株価回復の一義的な要因は企業の収益力の向上にある。米国と比べてまだ低いが、上場企業の平均ROEは10%に近づきつつある。経営者の使命は長期利益――資本コストを上回る持続的な利益――の創出の一点にある。
企業価値だけではない。顧客満足も結局のところ長期利益に反映される。企業の社会貢献の王道は社会的目的のために使うことができる原資を創出することにある。利益を出し納税する。そこに企業の社会貢献の本筋がある。喫緊の課題である賃上げにしても根本は同じだ。元手がなければ労働分配できない。稼ぐ力こそが持続的な賃上げを可能にする。長期利益はすべてのステークホルダーをつなぐ経営の王道だ。
業界ごとに異なる儲けやすさと「事業ポートフォリオ」
1989年の日経平均最高値は不動産バブルの追い風によるところが大きかった。多くの企業がレベル1にとどまっていた。そもそも当時の上場企業の平均経常利益率は現在の半分の3.7%でしかなかった(23年は7.1%)。地価が急騰する中で、東京湾周辺の工場跡地など巨額の不動産の含み資産を保有する「ウォーターフロント銘柄」が株価を牽引した。多くの上場企業が特定金銭信託やファンドトラストの資産運用に走り、その運用益が事業からの利益をしばしば上回った。世の中はバブルに浮かれていたが、肝心の企業の稼ぐ力は低水準にあった。
成長性や収益性が高い業界もあれば、そもそも儲かりにくい競争構造にある業界もある。日本の大企業は儲からない事業を抱え過ぎていた。この10年間の事業ポートフォリオの組み換えが収益性の改善に貢献したのは間違いない。
事業ポートフォリオ戦略の次の戦い方へ
ただし、儲からない事業の切り離しによる構造改革はマイナスをゼロに近づけることにしかならない。レゾナックは構造改革を実行した企業だ。前身の昭和電工時代に時価総額で2倍の規模だった日立化成を買収し、その後採算性の低い事業を次々に売却、半導体など成長が期待できる事業立地に集中した。しかし、同社の高橋秀仁社長は「事業ポートフォリオ戦略はコモディティ」と言い切る(「日経ビジネス」3月4日号)。
魅力的な事業立地は誰にとっても魅力的だ。化学メーカーの中期経営計画を見ると、どこも「機能性化学品・ライフサイエンス分野に注力する」とある。将来性がありそうに見える市場ほどレッドオーシャン化する。遅かれ早かれ、その業界の競争の中で差別化された価値を出せるかが問題になる。
金融危機で巨額赤字を出した日立は日立金属や日立建機などの上場事業子会社の売却を進め、ITとインフラと産業設備に集約した。ポートフォリオの半分が入れ替わり、15年にわたる構造改革は一段落したと言ってよい。長期利益創出の焦点は構造改革の空中戦から競争戦略の地上戦へとへとシフトしつつある。
「ベター」ではなく「ディファレント」へ
競争戦略の要諦は業界のなかで独自のポジションを確立することにある。言い換えれば、顧客から見て、「ベター」ではなく、「ディファレント」な存在になるということだ。品質や機能の点で他社より優れていても、持続的な競争優位にはならない。比較級の差別化では、一時的に優位であっても、すぐに追いつかれてしまう。一時的な利益は獲得できても、長期利益はおぼつかない。日立の事業でいえば、DX支援の「ルマーダ」、洋上風力発電などの再生エネルギーの長距離間の送電を得意とする高圧直流送電(HVDC)システムなど、独自のポジショニングを持つ事業が利益の源泉になりつつある。
日立が売却した企業のその後はさらに注目に値する。2017年に投資ファンドに売却された日立国際電気(現KOKUSAI ELECTRIC)。事業立地は以前から半導体製造装置だったが、独立した専業企業となってから日立グループの一事業としてのしがらみや調整から解放され、半導体デバイスの性能を左右する成膜技術に競争の武器を絞り込んだ。投資を加速した。かつての非中核事業が今では20%以上の営業利益率をたたき出す高収益企業となっている。KOKUSAIの果断な意思決定はもちろん、半導体製造装置事業に十分な競争力があるうちに切り離した日立の判断も秀逸だった。
今年に入ってからの急速な株価上昇は半導体企業の好業績に引っ張られた面がある。特定の事業立地に追い風が吹いただけならば一過性の現象だ。しかし、2000年のITバブルとは様相が異なる。当時のソフトバンクやNTTドコモの株高は戦略よりも事業立地によるところが大きい。これに対して、今回の主役となったアドバンテストやディスコ、東京エレクトロンなどは、以前から独自の戦略で長期利益を実現している企業だ。
株高は良いことだ。しかし、考えてみればこれまでが低すぎただけ。「失われた30年」の一義的な責任は、バブル崩壊だ、円安(円高)だ、少子高齢化だと、マクロ環境他責の無為無策に明け暮れてきたJTC(日本の伝統的大企業)の経営者にある。
「結果」が「原因」の前にくることはない
原因と結果を取り違えてはならない。日経平均の最高値更新は上場企業の一部が、利益の源泉のレベルアップを着実に進め、稼ぐ力を取り戻した結果に過ぎない。企業価値向上の原因は企業の稼ぐ力にある。それは、ひとえに経営者の高い目標設定と果断な意思決定にかかっている。
目先の小さな損得に流れず、将来に向けた戦略ストーリーを構想し、攻めの投資に踏み切れるか。厳選した経営チームで戦略を断行し、その中から次世代の経営者を育成できるか――すべては経営者次第。長期利益の創出に正面から向き合う気概と自信がない経営者は今すぐ他の人に代わってもらった方がいい。