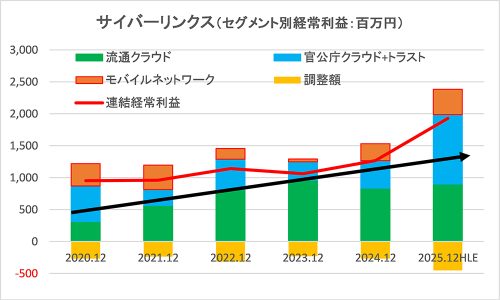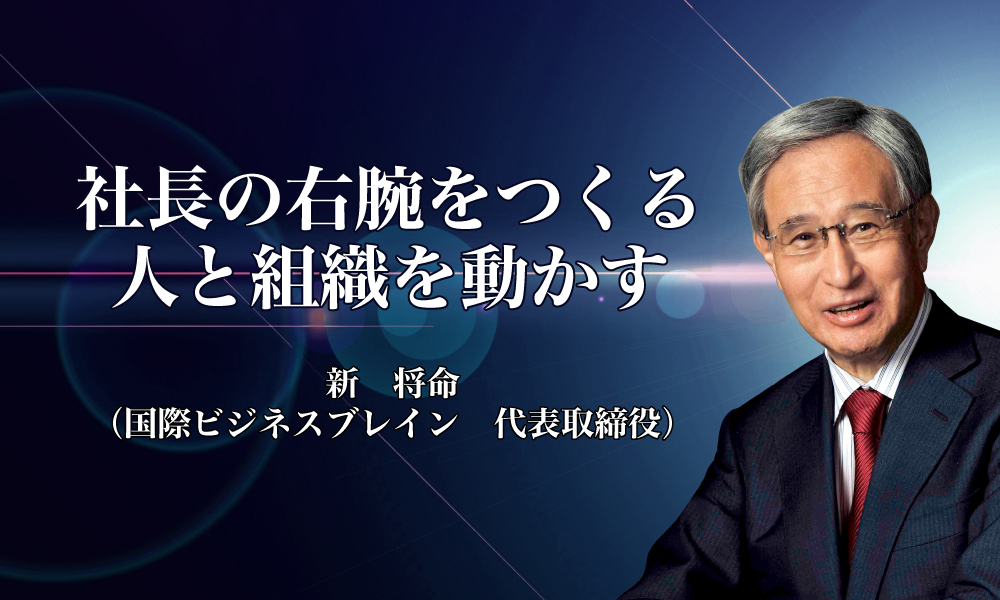若さは企業変革を「自分事」にする
CEOに就任した時、ウェルチは弱冠46歳だった。この若さは変革の成功にとって極めて重要な意味を持っていた。若さによって決定的に変わってくるのは、未来についてのリアリティのありようだ。企業変革が未来志向の仕事であることは言うまでもない。若いCEOであれば、未来をリアルに構想し、意思決定し、実行できる。
なぜか。言われてみれば当たり前の話だが、未来のそのときに、当の本人がまだ「生きて仕事をしている」からだ。46歳でCEOになったウェルチにとって、変革を果たした後の新たなGEは、自分の目で見て、自分の手で触れるリアルな存在だった。変革に成功すれば自ら成果の果実を味わえる。失敗すればすべてが自分に跳ね返ってくる。ウェルチにとって企業変革は徹頭徹尾「自分事」であった。「子孫に美田を残す」という類の悠長な話ではなかったのである。
「過剰にシンプル」にして「正しさ」よりも「やり切る」実行力を
変革のリーダーとしてのジャック・ウェルチの凄みは、打ち出す施策が過剰にシンプルであるということだ。「過剰にシンプル」というのは、「正しさ」を半ば意図的に劣後させるということを意味している。
その好例が、いの一番で表明した「ナンバー1、ナンバー2戦略」だ。すでに話したように、ウェルチが下したこの方針は、その後長きに渡るGE改革の劈頭であり、一連の創造的破壊の、とくに「破壊」の部分の起爆剤となった。
「ナンバー1、ナンバー2戦略」、これは論理的には「選択と集中」という話であり、それ自体はとくに目新しい方針ではない。構造改革に臨む多角化した大企業のCEOであれば、だれもが考えることだ。にもかかわらず、普通のCEOは、なぜ「選択と集中を、ウェルチのように徹底してやりきれない場合がほとんどである。
その理由は、普通の(優れた)CEOが「正しい」ことをやろうとすることにある。逆に言えば、ウェルチは「正しさ」を犠牲にしても「シンプルさ」を優先する。組織のメンバーの多くが怯み、無意識のうちに回避したくなるのが破壊活動である。だから、変革のためのアクション、とくに破壊に向けたアクションは徹底的にシンプルで解釈の余地がないほどわかりやすくなければならない。そうでなければ、破壊を実行できない。この基本姿勢が「ナンバー1、ナンバー2戦略」の根底にある。
最初のステップは「壊しすぎ」くらいでちょうどいい
ウェルチはこの一つの基準に忠実に事業の選別を断行した。ごく客観的に考えれば、「ナンバー1、ナンバー2」は意思決定の基準として「正しい」とはとうていいえない。事実、振り返ってみれば、ウェルチの「ナンバー1、ナンバー2戦略」には間違いもたくさんあった。例えば通信事業からの撤退。80年代当時から、コンピューティングとコミュニケーションの融合はメガトレンドとしてその重要性が叫ばれていた。ようするに現在のインターネットである。GEの通信事業は、その方面の技術を社内で唯一蓄積していた事業部門であった。当然、撤退には反対する人が多かった。しかし、ウェルチは、例によって「ナンバー1、ナンバー2でないから」といういつもの基準であっさり撤退してしまう。
教科書的に言えば、選択と集中の基準は「ケースバイケース」であるべきだろう。それは正しい。だから普通の(優れた)CEOは、構造改革に際して「多角的・総合的に判断する」というスタンスをとる。しかし、である。GEのような巨大かつ複雑、長い歴史を持つ大企業が、「正しい」ことだけで動くだろうか。「正しさ」を追求すると、どうしても話が複雑で分かりにくくなる。判断にも実行にも時間がかかる。だから「正しさ」を犠牲にしても、判断と実行の上での「わかりやすさ」を優先する。ここに超現実主義者のジャック・ウェルチの変革リーダーとしての真骨頂がある。
これに対して、普通のCEOは、「優れた人」であるがゆえに、「正しいこと」にこだわり、「間違い」を回避しようとする。「残すべきものを残し、壊すべきものを壊す」というスタンスだ。しかし、そんな悠長なことをいっていては、変革はできない。
どんな変革のケースでも、既存の体制や構造に多少なりとも良いところが残っているはずだ。全部が全部を壊さなければならないということは稀である(そんな状態になっていれば、とっくに会社は潰れている)。しかし、さまざまな理由をつけて例外や聖域を設け、そうした「残すべきところ」をちまちまと選り分けてしてしまうと、結局のところ既存の構造を引きずってしまう。
創造破壊の最初のステップは、「壊しすぎ」くらいでちょうど良い。そして、そのためには、多少の間違いを含んでいたとしても、方針や判断基準は「過剰にシンプル」でちょうどよい。