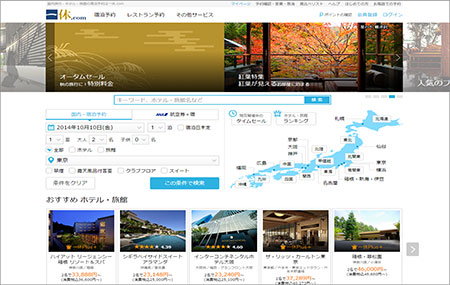- ホーム
- 指導者たる者かくあるべし
- 挑戦の決断(22) 有事の必勝法は「機先を制する」(承久の乱と鎌倉幕府)
倒幕に立ち上がる後鳥羽上皇
1219年(承久元年)2月2日早朝、鎌倉幕府三代将軍の源実朝(さねとも)が鶴岡八幡宮境内で暗殺された。これが波乱の幕開けとなる。初代源頼朝が朝廷から全国の守護・地頭の設置権を認められて武家政権をたてて(1185年)からわずか34年、まだ鎌倉幕府の権力は確立されていない。政権の財政基盤である農地支配も、東国は幕府に帰していたが西国は依然として朝廷のもとにある。日本は実質上、東西分裂の情況である。
さらに実朝に子はなく、武力支配の権威を朝廷から委ねられた将軍も不在の状態となる。鎌倉政権は執権・北条義時による権威なき運営に任された。朝廷の権威を経済面で支える荘園の経営は、武力を備えた地頭を派遣する幕府に侵食され、米・土地の上納寄進も滞りがちとなっていた。有力荘園からの地頭の撤退に応じない幕府の対応に不満を募らせていた後鳥羽上皇は、1221年(承久3年)5月15日、義時追討の宣旨(命令)を全国に発出する。〈今なら幕府から権力を取り戻せる〉と倒幕に立ち上がったのだ。経済利権を背景にした権力闘争の始まりである。
防御より攻撃
上皇の情勢判断は楽観的だった。「宣旨を目にすれば、各地の武士たちも朝廷側につく。謀反人の義時に従う御家人もいない。程なく義時の首が差し出されるだろう」。
実際、宣旨が鎌倉に届くと御家人たちは動揺した。朝廷の権威あっての武家政権である。朝廷軍が鎌倉に攻め下って来れば、弓を引くわけにはいかない。これが当時の武士の考え方である。しかも対抗権威の将軍職も空白のままだ。初代頼朝の未亡人である北条政子は御家人たちを集めて、涙ながらに演説した。
「今は亡き右大将軍(頼朝)以来の恩顧を思い出し立ち上がれ」
しかし、対策会議では消極論が支配した。「箱根、足柄の関を守り徹底抗戦すべし」との意見が多数を占めた。空気を変えたのは頼朝以来の幕府顧問、大江広元(おおえ・ひろもと)の鋭い一言だった。
「そのご意見ももっともだが、防御に専心したのでは、東国武士の中にも動揺がおこる心配がある。運を天にまかせ、さっそく京都を攻撃すべきだ」
政子もこれを支持し、出撃体制をととのえる。遠江、信濃以東の東国15か国の武士たちに動員令を発する。
執権義時の長男、泰時(やすとき)が鎌倉を発ち東海道を西に向かった。その数、主従合わせてわずか18騎に過ぎない。依然、鎌倉御家人の間には消極論が根強かった。まさに運を天にまかせての進軍だったがこれが奏功する。
様子見勢力をいかに取り込むか
有事に際しては、まずは方針を決め素早く動くことが肝心なのだ。有事とは先が見えないからこそ有事なのだ。先が見えないからと言って事態を見極めていたのでは出遅れる。この場合も、時が経てば経つほど、朝廷が出した宣旨の威力が増し、各地の武士団は朝廷方に寝返ってしまう。
体勢を整えた幕府軍は、東海道、東山道、北陸道の三方面から京都を目指す。進軍しながら土地土地の武士団が合流し、軍勢はふくらんでいく。
一方の朝廷軍は、鎌倉での寝返りを期待してか、軍事行動は出遅れる。美濃・尾張の防御線を破られると京都の拠点防衛に戦略を切り替える。その間に幕府軍は怒涛のように琵琶湖口の瀬田に到達した。泰時が鎌倉を出発したのが5月22日だったが、6月14日には、瀬田を渡河して朝廷軍を撃破し、京都へ雪崩れ込む。出発時にわずかだった手勢は19万騎に膨れ上がっていた。
先の見えない動乱、あるいは組織内の権力闘争が起きたとき、リーダーとして心得ておくべきことがある。大半は、敵味方の立場を標榜せず自己保身のため様子見に走ることである。
この時も「どちらが優勢か、優勢な側につく」と観望を決め込んでいた甲斐の武田氏は、幕府軍西上の情報を聞くや幕府軍の先鋒を買って出る。東山道の要衝を占める諏訪氏は朝廷との交流から態度を保留していたが、幕府軍が近づくや、神官を務める諏訪大社の神意を占い朝廷を裏切る。占いとは方便で、裏切りの正当化の儀式だった。
有事においては、素早く、一貫した方針に基づく行動こそが、大多数の様子見勢力を味方につけ勝利に近づける。
宣旨という権威に頼り行動が遅れた後鳥羽上皇は隠岐に流され、朝廷はこの後、明治維新まで武家政権に抑え込まれてしまう。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考文献
『承久の乱』坂井孝一著 中公新書
『日本の歴史7 鎌倉幕府』石井進著 中公文庫