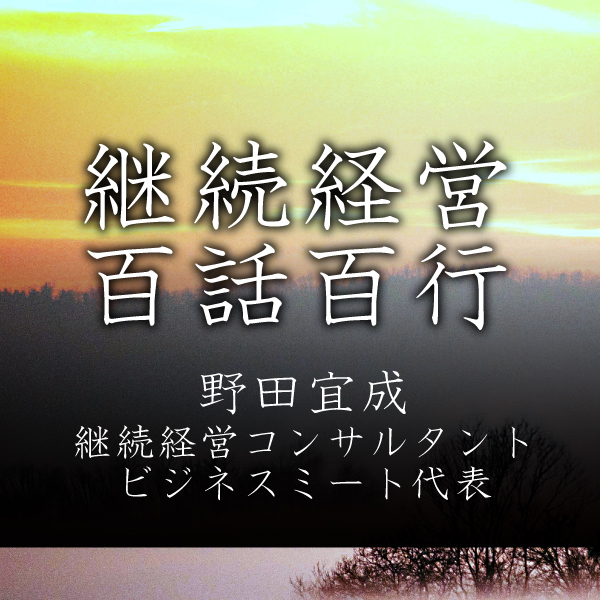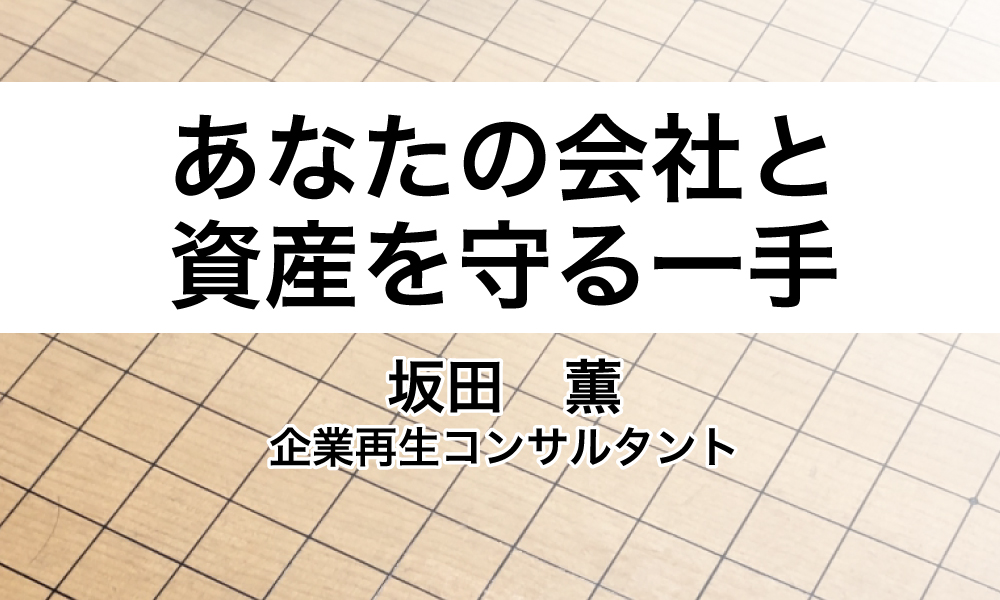【意味】
未だ人間としての生き方が解らないのに、どうして死のことが解るだろうか。
【解説】
天下の孔子様も死後の世界はよく解らなかったようで、このような句を残しています。解らないところは解らないままで、超能力的な態度を取らないところに好感を持てます。現実の人間社会での生き方を説いた大道徳家だからでしょうか。
「自分の命だけを考えて、我が死を捉えると、闇路に迷い込む」(巌海)とありますが、確かに我が死は自分の命の終わりで、死んで何処に連れて行かれるのか解りません。だから誰もが不安を感じ闇路に迷い込むのです。
それ故に宗教家はあたかも死後の世界(来世)が存在するように説き、現世の信仰生活のレベルに応じて極楽行や地獄行が決まると強調します。そして死が近づくと、立派な墓を建て盛大な法要を勧めてくれます。
しかし彼の有名な沢庵(タクアン)和尚は、「我が死に望んで法会を営んではならず。墓標を建ててはならず、亡骸は野に深く埋めよ」と云っています。
自然界から生まれた人間族、その人間族の中の一つの命が我々の命ですから、我が命は「自然界の一微粒子」となり、その生死は自然界全体の細胞分裂程度のことです。
諸法空想を説く般若心経に「不生不滅(生まれもせずに死にもせず)」とあります。自分の命を人間種族の細胞分裂と考えれば、「不生不滅」も解かるような感じがします。
一方現代社会では、相互博愛主義から「人間の命は地球より重い」などの名言も生まれています。自分の命の根源を憲法の自己権利に求め過ぎると、かえって自己愛が優先し執着の悪心に悩まされます。憲法で保障された国民の人権は「人為社会の産物」ですが、自然人である個人の生死は「大自然の領域」ですので微妙に食い違いが生じます。
現代人は、人為的な人権意識からの我が死を捉えて闇路に迷い込む傾向があります。700万年前に誕生した「人間種族の一微粒子」や46億年前に誕生した「地球生物種族の一微粒子」という視点から自分の命を考えてみると、一味違った自分の生死が見えてきます。
「死」については誰もが体験することですが、体験すればこの世からの消滅ですから、死の体験者が「死とは何たるか?」を後世に伝えることはできません。だから自ら進んで「我が命は何処より至り、死して何処に至るか?」を考えることは大変興味深いことです。
筆者の主宰する『人間学読書会』では、これを「我命の根源を問う?」と云ってしばしばテーマにしていますが、色々な意見が出てきます。
掲句について云えば、孔子様は現実主義者ですから、「死の探求」の暇があるなら自分がこの世に生を受けた意義、つまり「天命を捉え、生存中に天命を全うすることに心血を注げ!」ということ強調したかったようです。
読書会の会員が「葬儀に金を使うより、生きているうちに旨い酒を飲め!・・という教えでしょうか?」と語り掛けてきました。「そうですよ。今晩これから如何ですか。『我命根源』のつまみで・・」となり、有名な豆腐料理店で美味しい酒をいただきました。