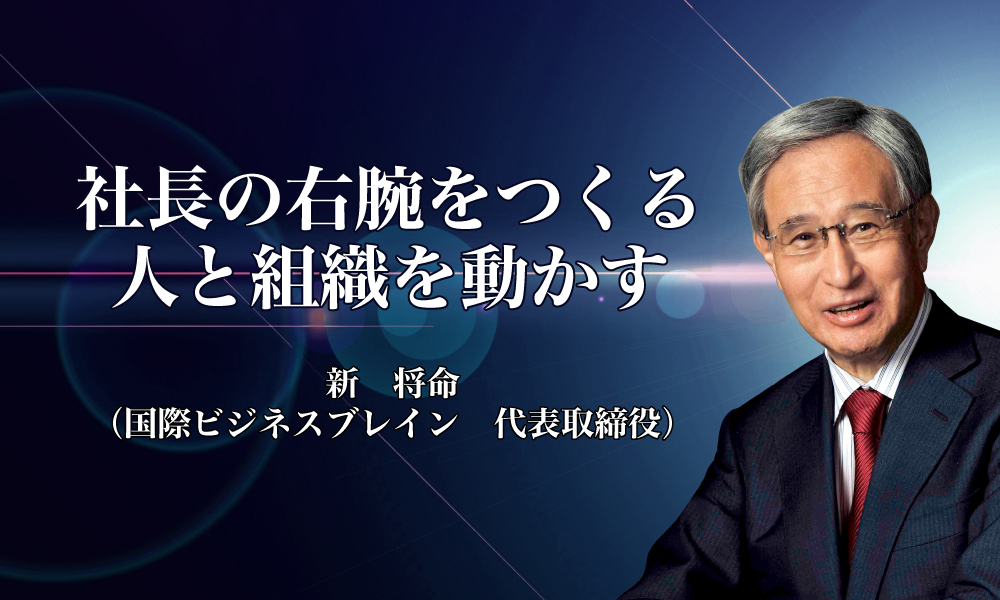大阪市の迅速な震災救援対応
1923年(大正12年)9月1日に関東大震災が発生すると、第六代大阪市長の池上四郎(いけがみ・しろう)は、ためらうことなくその日の大阪市電の収入金を被災者救援のため助役の一人に持たせ、10人の職員とともに船で横浜へ送った。急を要するとの判断から市会(現市議会)の承認を得ずに独断で行ったという。
4日には、臨時救援部を設置し、既存の各部署に役割を分担させて本格的に救援に動き出す。社会福祉事業を担当する社会部では、運営する共同宿泊所に震災被災者を優先的に受け入れる。実際に活動に従事したのは、大阪での震災を想定して組織した町内会連合だった。全て準備されていた。こうした危機管理体制は、市長の池上と筆頭助役の関一(せき・はじめ)が数年かけて組み立ててきたもので、遠隔地での被災にも迅速に機能した。関は2か月後に第七代の大阪市長に就任している。
「煙突を数えるだけでなく、労働者の状態を見よ」
明治末から大正初期にかけての大阪は、第一次大戦の戦争特需もあって商工業が急速に発展し、人口流入が続いた。都市整備が追いつかず労働者の居住区はスラム化しつつあった。池上は、市域の郊外への拡張や道路、交通機関、都市公園の整備などに取り組んでいたが、限界があった。都市計画には、ハードの整備に加えて福祉、教育など広範な社会事業が必要だと痛感する。白羽の矢を立てたのが、都市計画の専門家で東京高等商業学校(現・一橋大学)教授を務めていた関だった。学内政治に嫌気がさしていた関は、「象牙の塔での理論ではなく、実地に識見を生かしたい」と、1914年、求めに応じて大阪市助役となる。ここから池上と関の二人三脚が始まる。
二人の、とくに関の発想は独創的で視野が広かった。欧州への留学、視察経験から、都市計画には、経済基盤とハコモノの整備だけでなく、住民の福祉向上が重要であると考えていた。彼の言葉が残されている。
「上を見て煙突を数えるだけでなく、下を見て労働者の状態を見よ」
二人が取り組んだ事業を見れば、都市計画の方向性が見える。全国初の市立結核療養所開設(1915年)、わが国初の公設市場を四か所開設(1918年)、労働者の共同宿泊所、労働紹介所開設、全国初の児童相談所、公共託児所を開設(1919年)、市営産院開設(1920年)と、数え上げればキリがない。
また、震災直前には、市内の全小学校に養護教員各1名を常駐させる三カ年計画を打ち出している。計画通りに跡を継いだ関の市長時代に公約は達成された。これは欧米にも例を見ない画期的なものだ。児童の健全な発育を見守る先駆的な福祉政策は、全国区に波及し、今では当たり前にその果実を享受している。
中央の発想にとらわれない自律的思考
ハード面でも、二人は大阪市内を南北につながる御堂筋の拡張とその下に市営地下鉄を走らせることを計画したが、当時、市会議員からも、「滑走路でも造るつもりか」と揶揄された。やがて関市長時代に完成し、今では美しい銀杏並木とともに大阪のシンボルとなっている。
当時の市長は、市会が候補を決定し、内務省(戦後の自治省を経て現在の総務省)の承認を得て就任する事実上の「官選」だった。予算も政策も中央のコントロール下にあった。当初、池上が大胆な都市計画を内務省に持ち掛けても、「都市計画は、東京がモデルだ。地方都市はそれを真似ればいい」とにべもなかった。それを二人は粘り強く扉をこじ開けて、全国に先駆けてモデルを築いてゆく。
そして無秩序に拡張していった東京は震災に沈む。その間に、「大大阪」と呼ばれるまでに発展した大阪が第二極として国を支えることになる。
震災後の東京も帝都復興院長の後藤新平(ごとう・しんぺい)が、根本的な防災都市への改造を計画したが、政府・内務省はこれを却下して握りつぶす。そして今も、「直下型地震の被害想定におののく」ような無防備都市としての東京がある。
先を見ないで、目先だけで帳尻を合わせる。これが官僚的思考の悪い癖である。危機へのリスクテークは特に不得手だ。地方には、中央に対して「それは違う」と物申す気概と自律的思考が必要なのだ。
なんだか都市計画だけの問題ではないような気がする。右往左往する政府による現今の経済政策を見ていてそう思う。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考文献
『「大大阪」時代を築いた男 評伝・関一』大山勝男著 公人の友社