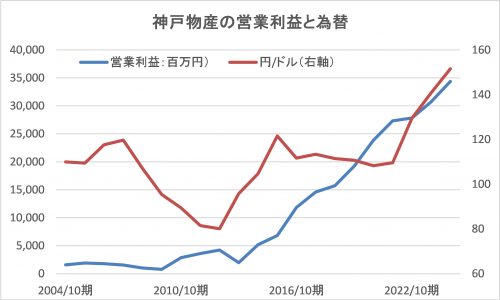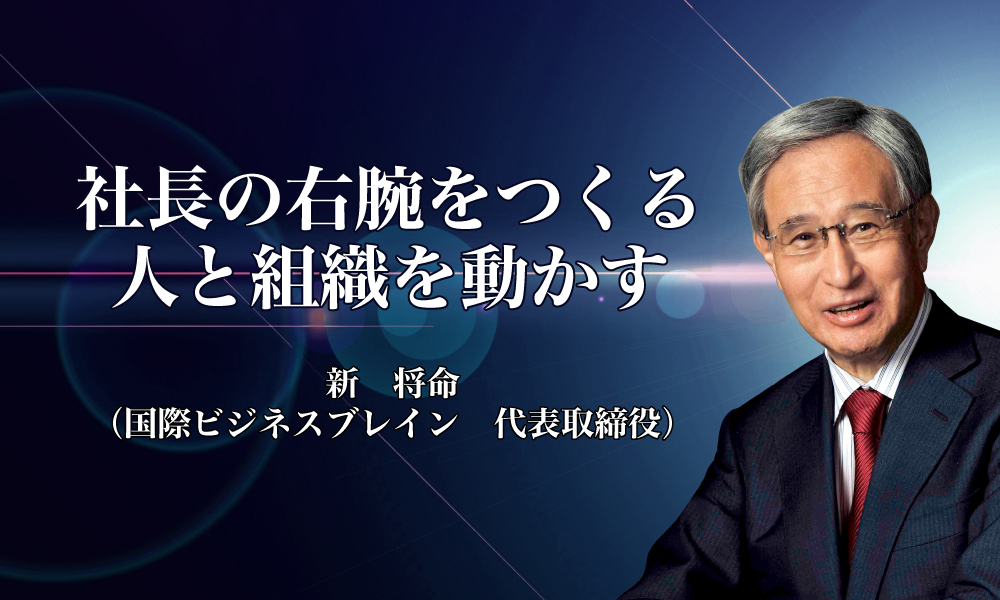征韓論をめぐる西郷隆盛との決別
岩倉使節団による長い米欧歴訪の旅に副使として同行していた参議・大久保利通(おおくぼ・としみち)に、留守政府から、至急帰国せよとの電報が届いたのは、出発から一年半になろうとする明治6年(1873年)3月のことだった。大久保は視察を切り上げて5月に帰国した。
留守政府では、主流派の西郷隆盛(さいごう・たかもり=薩摩)・板垣退助(いたがき・たいすけ=土佐)と、官僚派の井上馨(いのうえ・かおる=長州)、山縣有朋(やまがた・ありとも=同)との対立が深まっていた。官僚派の重鎮である大久保を呼び戻して事態の収拾をはかろうとしたのだ。
大きなきっかけの一つは、板垣が主張する「征韓論」にあった。維新直後から、明治政府は、日本の政体が変わったことを朝鮮王朝に伝えようとしたが、朝鮮側は通告国書に、天皇の「皇」の文字があることに強く抵抗し受け取りを拒否した。「皇」とは、朝鮮が信じる華夷秩序外交構図では、中国皇帝以外使用できないことになっている。板垣は、頑迷固陋な朝鮮を懲罰するための派兵を強く主張した。西郷は、板垣を抑えるために「私が国書を持って行く、決裂すればその後に派兵を考えればいい」と折衷案を出した。
征韓論は、そうした外交軋轢が本質ではなく、留守政府が発した徴兵令によって失職する士族の不満の吐け口を外に向けようとの政治工作の側面が強い。
帰国して状況を把握した大久保は、維新後まもない脆弱な日本が海外派兵などすれば、欧米諸国の介入を招き、政府は崩壊すると危機感を持つ。ここに大久保は幼なじみで、維新を成功に導いた盟友である西郷との決別を決意し、天皇への上奏を工作し、西郷・板垣の追放を実行に移した。(明治6年の政変)
友を諌める論理
西郷というのは不可思議な政治家で、士族を切り捨てる近代軍制を推進した張本人だ。ところが、士族たちから、利益代弁者としての期待が高まると、それに応えようとする。論理的というより、信頼を第一に考える「義」の政治家だ。義に殉じる行動の行き着く先が自殺行為とも言える西南戦争での憤死だ。
対して大久保は合理的精神の持ち主だ。帰国後の閣議で、征韓論の愚を七か条にまとめて主張した。
要点をまとめるとこうなる。①政府の基礎もできていないのに朝鮮で戦争はすべきではない ②政府財政は火の車で多額の戦費出費は経済を破綻させ国難を招く ③無用の戦争は国民を苦難に陥れ国民反乱の引き金となる ④輸入超過の貿易構図はさらに苦しくなる ⑤戦争はロシアに漁夫の利を与える ⑥英国からの多大の債務の返済が滞り、さらなる内政干渉を招く−―そして大久保が真に主張したかったのは、最後の一点にあった。
⑦日本は欧米諸国との不平等条約下にある。
いまだに英仏軍の駐屯を余儀なくされ属国のようである。早く条約を改正し、「独立国の体裁を全うする」のが先決である。そしてこう結ぶ。「今、国家の安危を顧みず、国民の利害を計らず、好みて事変を起し、あえて進退取捨の機を明らかにしないのは、まことに了解できない」。西郷、板垣にさっさと辞めろと厳しく通告した。
鉄血宰相ビスマルクのアドバイス
論理に一点の揺るぎもない。大久保という男は、米欧視察後に、政治姿勢、たたずまいが一変した、と部下の一人が書き残している。視察後の彼からこう聞いたという。「この世界に独立して国を建てるのに必要な富国強兵を実行するには、まず殖産興業から着手すべきだ。建国の大業は、議論弁舌だけでは行かない。やりくり算段だけでもだめだ。恐喝まがいの脅しあるいは権謀術数では進まない」。
大久保の最後の訪問国となったプロシア(現ドイツ)でのことだ。「鉄血宰相」と異名をとる、ドイツ発展の基礎を築いたビスマルクは、遠来の客を邸に招きいれて、欧州の後進国として強国に取りまかれる中で、独立を維持することの困難と苦難の発展史を熱く語りかけた。
ビスマルクの言葉に、日本の将来を重ね合わせて激励の言葉と受け取った大久保は大きな感銘を受けて西郷に手紙を書いた。
「幕末以来の自らの苦難の経験を思い起こし、発展した大プロシア帝国の現状に、日本の前途の希望を見出す」
義の人、西郷はその手紙にしたためられた興奮気味の文面を、どのように読んだのだろうか。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
(参考資料)
『大久保利通』毛利敏彦著 中公新書
『日本の近代2』坂本多加雄著 中公文庫
『日本の歴史 20 明治維新』井上清著 中公文庫