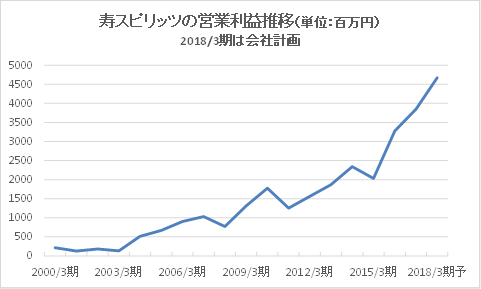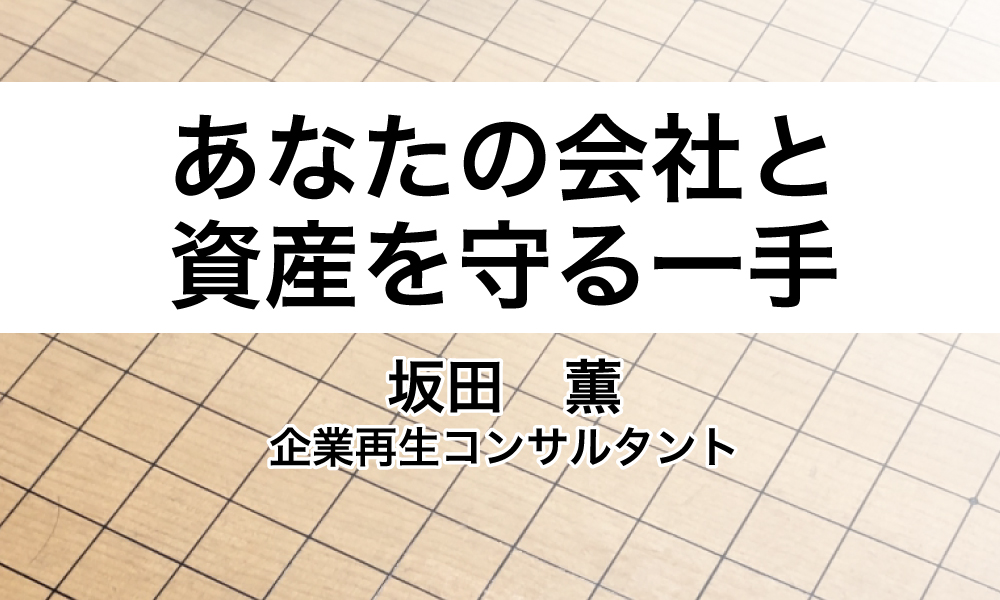下の画像、2017年に撮影した1枚です。3年前の東京モーターショー、本田技研工業のブース風景でした。

この年の東京モーターショーで、ホンダは2台の電気自動車(EV)のプロトタイプ(試作モデル)を展示しています。画像の右側に写っているのは、当時「Honda Urban EV Concept」と名づけたプロトタイプモデルです。
こうしたプロトタイプというのは、そのまま市販できないような現実離れしたデザインであることも少なくないのですが、それにしてもこの一台、とても強い存在感を放っていたのを覚えています。クルマのオールドファンであればご存じかと思いますが、1972年に登場した、初代の「シビック」をどこか彷彿とさせます。前席のメーターまわりのデザインもそうで、インスツルメントパネルなど、液晶モニタを多用した未来型のものでありながら、どこか初代「シビック」のモチーフを用いている印象もありました。
で、東京モーターショーの現場で、担当デザイナーに尋ねました。すると、返事はこうだった。
「EVにおいては、抱きしめたくなるような可愛らしさが必要でしょう」
私、とても納得しました。どうしてか。EVって、冷たさというか得体の知れなさが、どうしてもつきまといがちです。エンジンを搭載した既存の車種に比べると、温かみが薄いんですね。
担当デザイナーの言葉に膝を打ったのは、「それを解消するのは愛嬌だ」という発想に合点がいったからなんです。
クルマに限らず、日本のものづくりにおいてはは元来、無機質である機械に愛嬌を付加されるのはお手の物なはず。ソニーのイヌ型ロボット「アイボ」の例を引くまでもなく、それは間違いないと思います。
そういうお家芸を生かせれば、米国などの新興メーカーに比べて開発で遅れを取っているともいわれがちな日本発のEVの世界で、 独自の存在感を誇示できるかもしれない。2017年の東京モーターショーで、私はそう感じていました。

次の画像です。これは先月8月27日に日本で発表されたばかりの「Honda e」です。念のため、同社にも確認したのですが、「2017年のプロトタイプから、基本的なデザインは変えていません」とのことでした。ほぼそのまんま市販化したのですね。つまりは、担当デザイナーが主張していた愛嬌も、そのまんまということです。
車両本体価格は451万円からと、安くはありません。ただし年間の販売計画は1000台と控えめです。おそらく、このモデルを市販することで、今後のEV本格普及に向けて、実地での学びを得るとともに、同社のアイデンティを知らしめるのが主目的と考えられます。
もうひとつ、お話ししますね。私、いろんな場所で常々お伝えしていることがあります。商品開発って「何をして、何をしないか」を決めること、だと思うのです。「何をするか」と同じくらい大事なのが、「何をしないか」を見定めることであると…。
ホンダは、このEVニューモデルを登場させるにあたり、「したこと」はここまでお話ししてきた通り、冷たい印象をもたらしがちなEVに愛嬌を加えた部分であると私は解釈しています。それが他社のアプローチとは異なるという点も注目に値します。
では「しなかった」ことは何か。航続距離の優先です。EVって、ここまでほぼすべてのメーカーが、一回のフル充電で走ることのできる距離を競ってきました。まあ、それはわかります。充電切れになったら、ユーザーにすると目も当てられないから。
でも、この「Honda e」は、他メーカーのEVに比べると、5〜6割の距離しか一度のフル充電で走れません。またなぜなのかと推測すると、答えは簡単です。航続距離優先だとバッテリーは重くなるので何かと負荷がかかりますし、車載用のバッテリーはいまだ高価ですから車両本体価格に跳ね返ります。ホンダはそこをスパッと切った。で、その代わりに急速充電の性能を高めた。「これでいいじゃないか」と言いたげでもありますね。
どちらのメーカーの開発思想が正しいか…。言いたいことはたくさんありますが、今回のコラムの主旨と外れるので、ここでは省略させてください。ただ、ひとつだけ申し上げたいのは、「業界の常識を疑うことから、拓ける道もある」という話です。航続距離が短いこと一点をもって、このEV は消費者に受け入れられない、と断言していいとは、どうも私には思えません。
まとめます。無機質な存在に情緒を与えることは、日本のものづくりの得意領域であり、そこに商品開発のひとつのヒントがあること。そして、「何をなし、何をなさないか」の峻別が、尖った商品づくりには不可欠とも考えられること。
これはクルマ業界、あるいは大手メーカーの商品開発に限った話ではないと、私には感じられます。