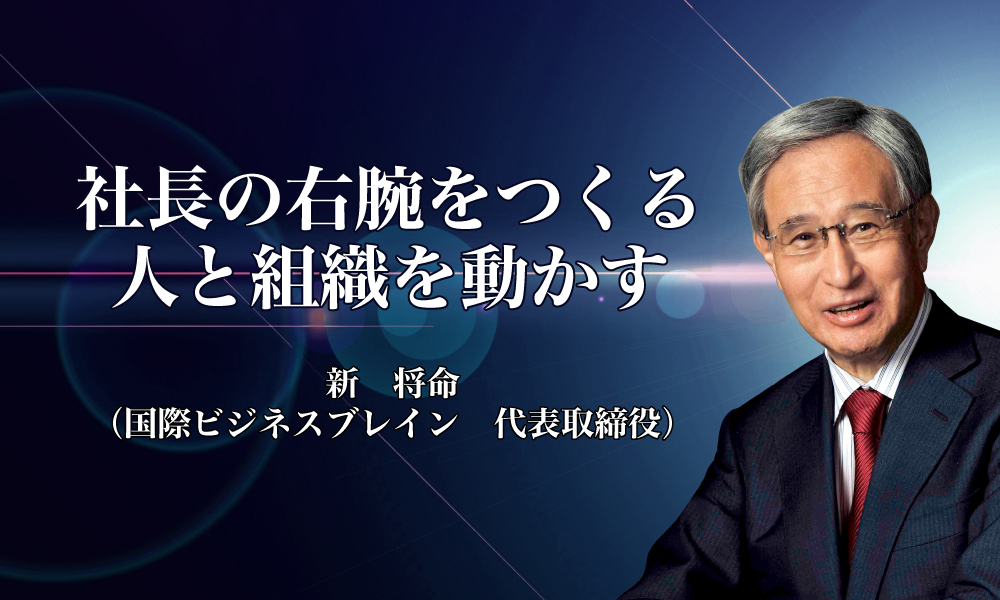昭和46年(1971年)7月5日の内閣改造で、時の総理、
当初、用意された官房長官、外相のポストを田中はいずれも蹴り、
「なる気はなかったが、引き受けたら、日米繊維交渉がある、
日米繊維交渉には、前々任の大平正芳、
日米間の繊維摩擦は、1950年代に“ワンダラー(1ドル)
その後の日米貿易摩擦につながる難題であった。
「おまえ、ひとつ、これを片づけてくれ」
この難題に佐藤は、
田中にしてみれば、大平、
通産省に乗り込んだ田中は、「みんな集まれ」
「第一番の仕事に日米繊維交渉をやる」
座はざわつきはじめる。「
田中は一同を睨め回す。そして言った。
「ダメだ。お前らが辞めても、オレは絶対に辞めないよ」。
官僚は失敗が予想される課題には手を出さない。
「まずは、そこからだな」と田中は考えていた。 (この項、次回に続く)
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※ 参考文献
『早坂茂三の「田中角栄」回想録』早坂茂三著 小学館
『田中角栄の資源戦争』山岡淳一郎著 草思社文庫
『日米貿易摩擦―対立と協調の構図』金川徹著 啓文社