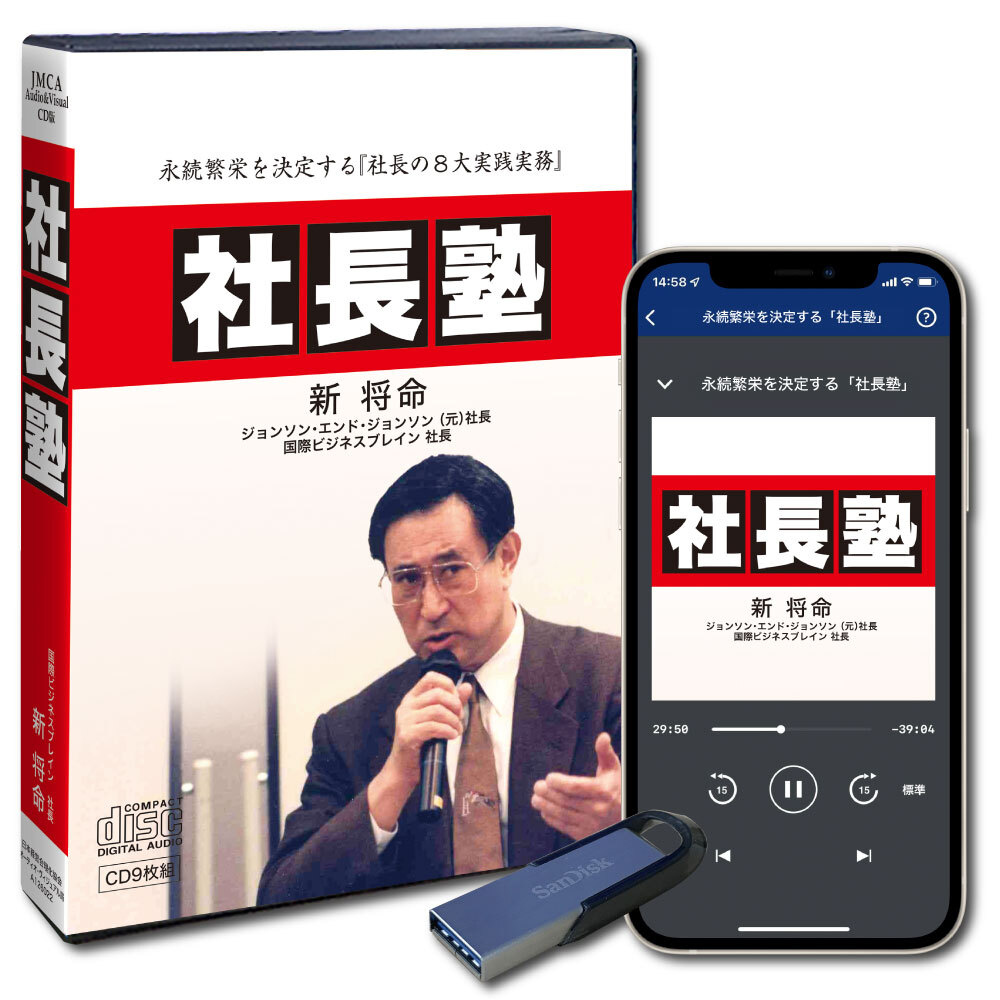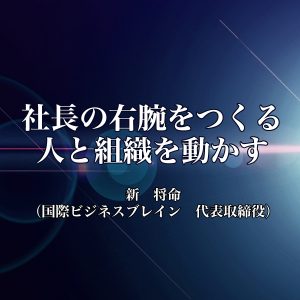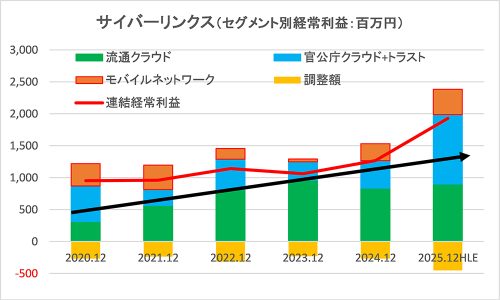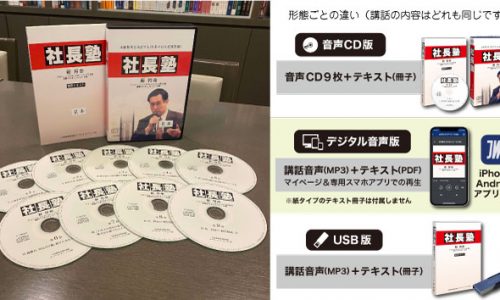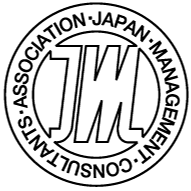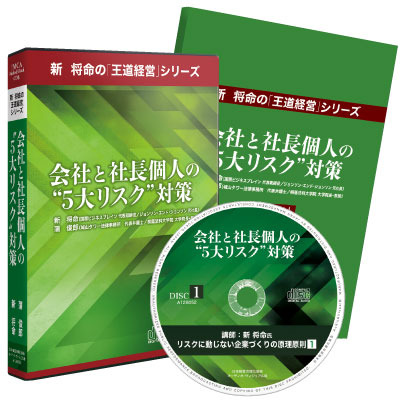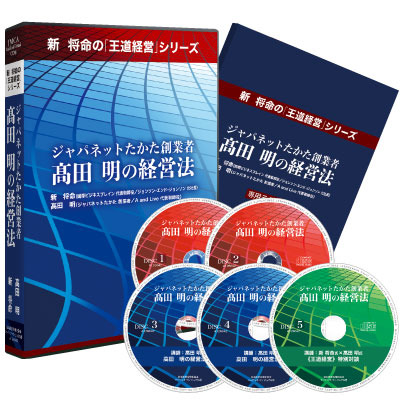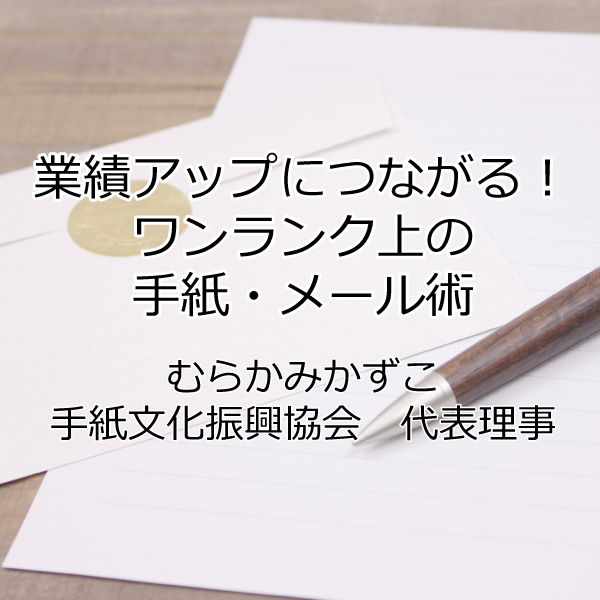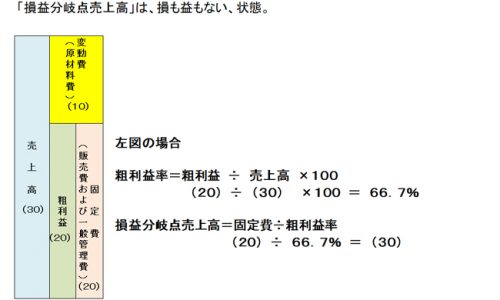- ホーム
- 社長の右腕をつくる 人と組織を動かす
- 第155回 『ゼネラリストという名のスペシャリスト』
英語に、
= Jack of all trades and master of none. =
何でも浅く知っているが、何ひとつ深くは突知らない・・・
何でもやれるが、人に秀でた芸はない。
という表現がある。
ゼネラリストはよろず屋で、
全てのことについてよく分からなくてもいいのだ、
分からないからこそゼネラリストなのだ、
と思われがちだが、これは明らかに誤解である。
ゼネラリストというのは、本来的には、
複数の専門分野を卒業して、
その延長として初めてなるべきものである。
換言すると、
何らかの自分の専門分野を底辺に持ったうえで、
ゼネラリストになるわけだ。
たとえば、広告・デザインや販売など、
いくつかの専門分野をカバーして、
専門家ではないが、いろいろな〈機能〉を包含して
マネジメントを行うという点では、
ゼネラリストという名前の専門家(スペシャリスト)でなければならない。
単一の機能という土俵においては、
ノン・スペシャリストである部分があっても、
それを含む全体をマネジメントする面では、
一種のマネージャーとしてのスペシャリストでなくてはいけない、
という理屈になる。
だから、クドくなるが、
ゼネラリストという名前がついたからといって、
いかなる意味においても、
「スペシャリストである必要がなくなるための免罪符」には一切ならない、
ということを強調したい。
一方、スペシャリストとか、スペシャリスト・スタッフというのは、
ゼネラリストが手を焼く難しい問題の解決を助けるために、
いわば社内のコンサルタントとして、存在するはずである。
先日、アメリカの本を読んでいたら、スペシャリストを定義して、
「ただ放っておけば簡単なことを、困難かつ複雑にする特殊技能をもった人間」
と皮肉ってあった。
中味の濃い人ほど、簡単なことを難しく表現する傾向があるようだ。
本当のプロのスペシャリストは、
非専門家のゼネラリストにも分かりやすく物事を表現できる。
また、どんな立派なことを言っても、相手に分かってもらえなければ、
本当の意味でのサービスを提出したことにはならない。