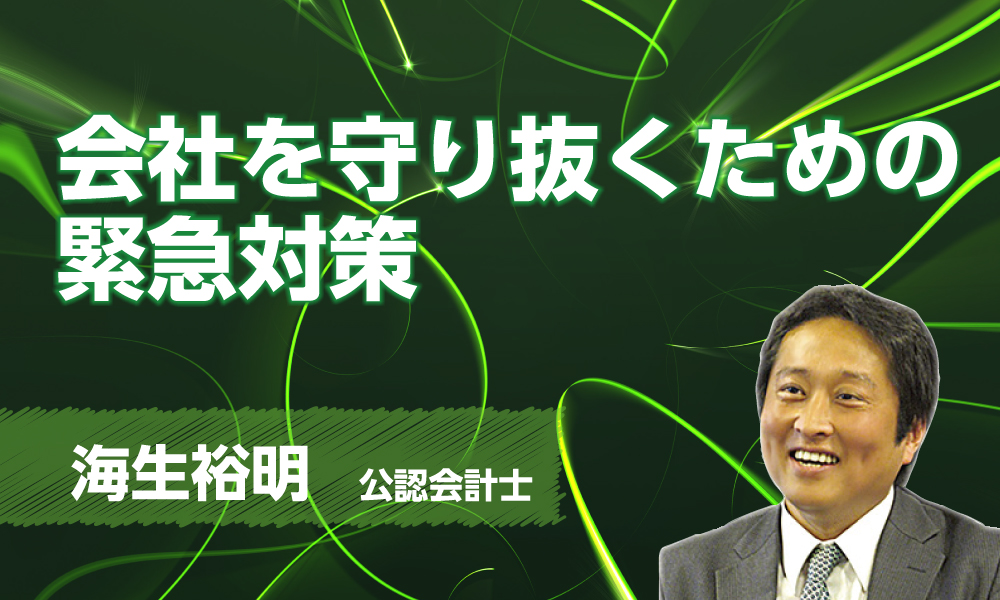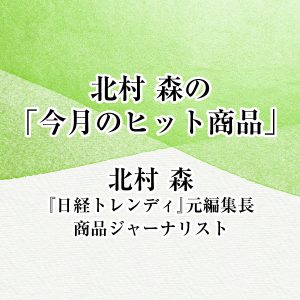商品のヒット現象って、どのようなプロセスをたどって生まれるものなのか。まあ、いろいろな経緯があると思いますが、そのなかのひとつに「商品の作り手側も想定外だったニーズが出現したからでは?」と感じさせるケースがあります。
古くはトヨタ自動車の初代「ソアラ」。1981年に登場した、2ドアの高級パーソナルクーベですね。仕事を長年頑張ってきた大人に向けたご褒美を、ともいうべき位置づけで開発されたと聞いたことがありますが、この「ソアラ」の流麗なフォルムと先進的な装備に、若年層までもが飛びついた。その結果、日本国内のクルマ市場に「ハイソカー(ハイソサエティ・カー)」ブームが巻き起こりました。その後の日産「シーマ」の爆発的ヒットにつながる流れを築いたのは、トヨタ「ソアラ」だったというべきかもしれませんね。
1990年代前半でいうと、ポケベルでしょう。ビジネスパーソンの緊急呼び出し用ツールだったのが、いつしか10〜20代のコミュニケーションツールとしても脚光を浴びました。その現象を受けて、90年代に入ると、以前からあった無骨な形状のポケベルだけでなく、かわいいデザインの商品が数々登場しています。
最近では「ワークマンプラス」が筆頭格といえます。「ワークマン」は現場仕事に携わる人のために、堅牢で、かつ耐風耐寒性能に長けた衣類を販売していましたが、そうした特徴に注目した若い母親層、あるいはバイク乗りといった一般消費者も店舗を訪れ、商品を買い求めるようになっていた。同社はそれを見逃さず、一般向けの新業態店をオープンさせるに至った、という話ですね。
で、ここからが今回の本題です。この商品、皆さんはもう購入していますか。

微アルコール飲料です。例えば、アサヒビールが今年(2021年)発売した「BEERY(ビアリー)」は、アルコール度数0.5%のビール風味の商品です。その後も、さまざまな商品が登場している状況。
こうした微アルコール飲料を各社が発売し始めたのには、もちろん理由があります。日本国内のみならず世界的にも、酒離れが一定にみられること。いやもちろんジャパニーズウイスキーブームなどは続いているのですが、その一方で、酒の飲み過ぎを避けようとする消費者が増えているのですね。だから、スマートなかたちでアルコールをたしなもうという人に向けた商品が必要になった。また、今後の人口減を考えると、そもそも酒類をさほど手に取らない消費者層をも振り向かせられるような商品を展開することは、メーカーにとって必須の策ともいえますね。これまで顧客としていなかった人たちも取り込まないと、市場は先細りとなってしまうわけですから。
そうした背景から、「ごくちょっとだけ酔う」といった感じになれる微アルコール飲料が続々と登場しているとみられますが、私、この夏から先月にかけて、「あっ、こんなところでも微アルコール飲料が!」という場面に何度も遭遇しました。どこか……。飲食店のメニューに微アルコール飲料が加わっていたんです。
9月下旬まで多くの地域で、飲食店での酒類提供が中止を余儀なくされていましたね。こればかりは致し方ありません。そのため、大半の飲食店は営業を止めるか、酒類を出さないかたちで店を開けていました。
暖簾を掲げていた飲食店にとって、酒類を提供できない事態が相当に厳しいというのは想像に難くありません。そうしたなかで、いくつもの店が微アルコール飲料を料理と一緒にメニューに並べていたという話です。
私、最初見たときは驚きました。「これ、店内で出していいんですか」と……。

いや、大丈夫だったようです。というのは、微アルコール飲料は商品カテゴリーのうえでは酒類ではなくて清涼飲料になるのですね(「ビアリー」の場合、缶を確認すると「炭酸飲料」と記されています)。
こうした動きには異論もあるかもしれません。コロナの感染拡大を防ぐための酒類提供中止なのだから、その趣旨を考えれば、たとえ微アルコール飲料であっても、アルコールが含まれる以上は出すのを避けるべき、というふうにです。
私にはそこをどう判断すべきか、答えを出せませんでした。ただひとつ言えそうなのは、厳しい逆風下でなんとか踏ん張っている飲食店にとって、微アルコール飲料の提供は必死の判断のすえであったのではないか、ということです。
結果として、微アルコール飲料は「普段さほど飲まない人」「それほど飲みたくない人」を取り込むというのにとどまらず、期せずして「すごく飲みたいのに飲めない状況にいる人」の渇望にも応える存在となりました。少なからぬ飲食店が提供に踏み切ったことで、微アルコール飲料の認知度も一層高まったはずです。
ヒットの契機はどこから? ときには意外なところから? 今回はそういう話でした。