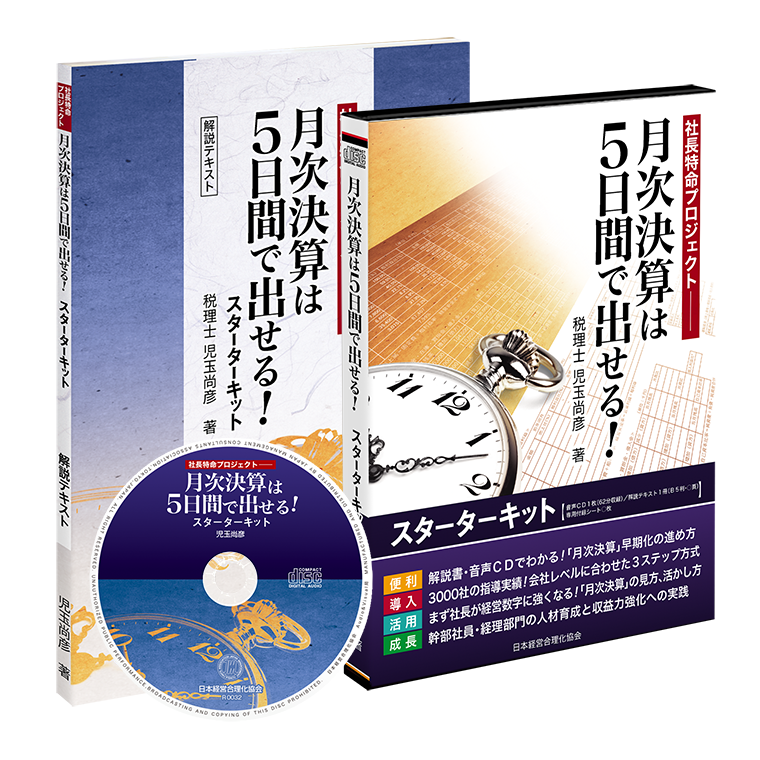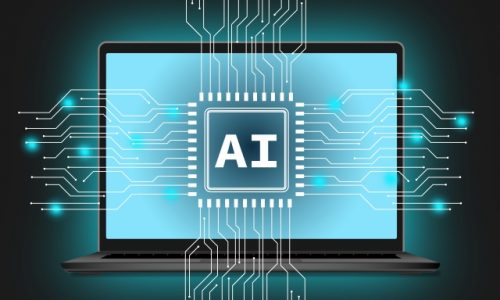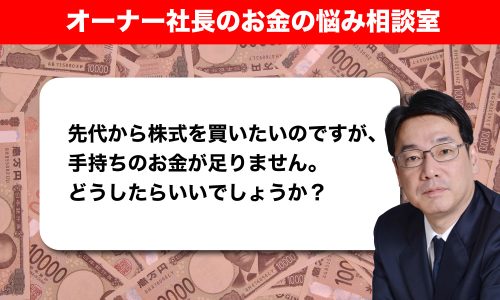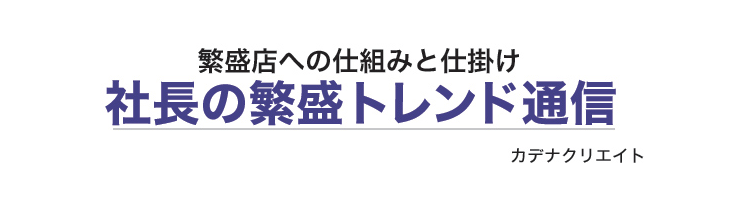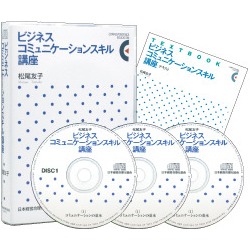電子取引データはどの範囲まで保存すればいいのですか?
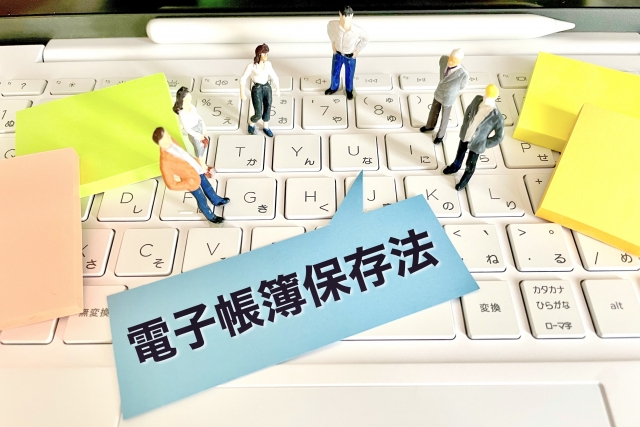
改正電子帳簿保存法(電帳法)が2024年1月から始まり、このような問合せが企業の取引担当者から経理部門に多く寄せられています。
電帳法が規定する電子取引は、電磁的に行われる取引データが広い範囲で該当することになります。
しかし、すべての取引データを電帳法の要件どおりに保存していたら、事務作業が増えてしまいます。
会社としては、実務上必要な範囲で保存するデータを決めて運用していくことになります。
そこで今回は、電子取引のデータ保存に関するよくある質問について、説明します。
電子取引データの保存範囲は社内で決まっていますか?
金額訂正前の見積書データは保存すべきか?
電帳法は、そもそも法人税法及び所得税法において定められている帳簿書類を電子的に保存するための法律です。
したがって、電子取引として保存する書類の対象範囲についても、今まで紙で保存してきた書類と変わりません。
これまでと同様に、取引相手とやり取りした請求書や領収書、見積書、発注書、納品書などの書類を、紙に替わって電子データで送受信したものが保存対象となります。
また最近では、このような取引関係書類を電子メールに添付して送受信することが増えており、交渉過程で複数の取引先と金額や内容等の条件を何度も変更してやり取りすることが珍しくありません。
この場合、特に見積もり段階においては、一つの取引に関して確定する前の書類データが複数発生することがよくあります。
例えば、取引の交渉段階で金額が改定された訂正前の見積書や、実際の取引には至らなかった見積書等のデータが何種類も存在しますが、これらの確定前にやり取りしたすべてのデータまで電帳法の要件に従って保存していたら、事務負担が増えてしまいます。
社内の事務手続き上、確定後の見積書だけを保存し、確定前の書類は保存していなかったのであれば、電子取引になった後も同様に取引確定前のデータを保存する必要はないでしょう。
電子取引データの保存が義務付けられたからといって、保存する書類の対象範囲を広げないように注意してください。
電子取引データの保存により事務負担が増えていませんか?