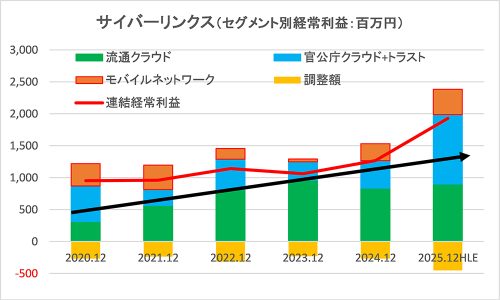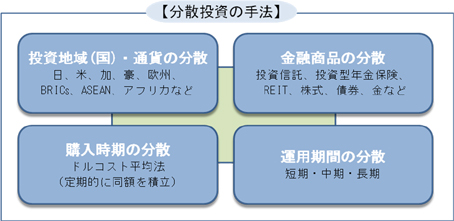決断の正体
経営とは決断(の連鎖)であり、決断とは選択である。リーダーの一義的な役割は決断の継続にある。
ポイントは2つ。第1に、決断が選択である以上、複数の選択肢がなければならない。「○○せざるを得ない」という言葉を軽々に使う人はリーダーの要件を欠いている。これは単に「追い込まれている」のであり、もはや戦略ではない。
第2に、真の戦略的意思決定は「良いこと」と「悪いこと」の間の選択ではない。決断は常に「良いこと」と「良いこと」、もしくは「悪いこと」と「悪いこと」のどちらを選ぶのかという問題である。ここに決断の難しさがある。良いことと悪いことであれば、前者を選べばいいに決まっている。そんな仕事は誰でもできる。そもそも「決断」は必要ない。
無能なリーダーは「一理ある」というフレーズを連発する。しかし、考えてみれば世の中に「一理もないことなど存在しない。錯綜するさまざまな「理」のどれを捨てるか。これが決断の正体だ。それは定義からして「苦渋の決断」になる。
「嫌われ者のリーダーシップ」を体現したフランスのド・ゴール
フランスの政治家ド・ゴールは嫌われ者のリーダーシップを体現したひとだった。第二次世界大戦で祖国がナチスドイツに支配されると、ひとりロンドンに渡り革命政府を宣言、徹底抗戦を呼びかける。戦後処理でもチャーチルやルーズベルトを相手にした交渉で粘り粘り、自らをフランス政府代表と認めさせ、ついには植民地軍を統率して「戦勝国」の将軍としてパリに凱旋 ― ここまでの「救国の英雄」としてのド・ゴール像は日本でもよく知られている。
しかし、この人の凄みはその十数年後の晩年に下した一大決断にある。植民地アルジェリアの独立の承認である。日本が「もはや戦争しかない」という戦略喪失状態で開戦に踏み切ったのは、最後通牒で突きつけられた満州からの撤退をどうしても飲めないからだった。すでに満州には巨額の投資をしており、多数の日本人が満蒙開拓団として生活し、関東軍という軍隊まで持っていた。満州放棄という選択は内戦になりかねなかった。
当時のフランスの状況はこれに似ていた。アジアの植民地からの撤退はそう難しくない。事実、ベトナムからの完全撤退は国民から歓迎された。しかし、アルジェリアには100万人近いフランス人(コロン)が入植し、経済的にも不可分の関係にあった。
1954年にアルジェリア戦争が勃発し、事態はいよいよ混迷を深める。こうなったら植民地に顔が利くド・ゴールしかいない。全権委任を条件にギリギリのタイミングで首相を引き受けたド・ゴールは、アルジェリアの総督府で入植者の大群衆を前に演説する。「君たちの言いたいことはよーく分かった」 ― 人々は「フランスのアルジェリア」路線を信じた。
しかし、内心では民族自治路線を決意していたド・ゴールは完全独立へと一気に舵を切る。戒厳令並みの強権で古い反乱軍を鎮圧し、130年間のアルジェリア支配に終止符を打った。フランス国民の怒りはすさまじかったが、この決断がアフリカの民族自治の潮流を生み、泥沼の植民地問題を回避することになった。これぞ決断中の決断だ。「その成否は歴史しか評価できない」という覚悟がある。ド・ゴールは「決断王者」の観がある。
日本の「決断王者」薩摩藩家老、調所広郷(ずしょひろさと)
日本史上でド・ゴールに匹敵するリーダーは誰か。薩摩藩家老、調所広郷を第一に挙げたい。天保期に「貧乏日本一」だった薩摩藩。明治維新をリードする富強藩へと生まれ変わった。この起死回生の改革を主導した調所の波乱万丈の生涯は味わい深い。
当然のことながら調所を敵視する人も多かった。最後はお家騒動で自死に追い込まれる。しかし、調所の財政再建がなければ、その後の西郷や大久保の活躍もあり得なかった。悪循環を断ち、好循環を生み出す。構造改革のリーダーシップの最高のモデルがここにある。
関心がある方は原口虎雄の名著『幕末の薩摩: 悲劇の改革者調所笑左衛門』をお読みいただきたい。古い本で、残念ながら絶版になっているが図書館にはあると思う。