諸外国の鉄道利権争い
1872年(明治4年)12月11日、わが国最初の鉄道路線として東京・新橋〜横浜間が開通した。その後の国内での鉄道の建設ラッシュはすさまじく、明治末年には世界に冠たる鉄道大国の仲間入りをしている。鉄道敷設はその後の経済発展をもたらすことになるが、明治新政府の財政基盤も整わないうちに行われた大規模投資の裏には、強い反対論を押し切り日本の将来を見通した当時の解明的人々の英断があった。
江戸幕府末期の19世紀前半、西欧社会は産業革命と鉄道による流通革命で新たな発展段階を迎えていた。日本では倒幕の政治闘争で明け暮れていたが、列強各国の政府と資本家たちは世界的規模での鉄道敷設の主導権争いを演じていた。鉄道利権を握ることでその国の市場と貿易の独占権が得られるからである。日本では英国、米国、フランスの三国が、開港場の横浜と江戸を結ぶ鉄道建設利権の獲得にしのぎを削っていた。
まず、いち早く徳川幕府に開国させた米国が、1867年(慶応3年)1月17日、米公使館員のポートマンが幕府老中・小笠原長行(おがさわら・ながみち)から、同路線の免許状を得た。戊辰戦争開始直後のどさくさに紛れての免許取得だった。
自国管轄方式に踏み切る
やがて明治新政府が発足すると、ポートマンは免許を追認するように新政府に求めた。幕府が米国に認めた免許状では、鉄道の敷設権は独占的に米国が保有し、測量や土地の買い上げのみ日本側が負担することになっていた。経営権も基本的に米側にあり、収益は全て鉄道会社に帰属するとなっていた。
「これをきっかけに日本は植民地化されてしまう」と危機感を持った外国官(外務省)は明治2年3月、この追認申請を拒否した。理由は、「免許状の日付は王政復古の大号令の後であり、江戸幕府はすでに国政権限を失っており無効」というものだった。
断を下したのは、外国官副知事(次官)だった大隈重信だった。大隈は決断に当たって、当時、日本との貿易をめぐって対立する英国の駐日公使・パークスの力を得て、米国を抑え込んだ。そして大隈は、鉄道敷設にあたり〈わが内国人の合力をもって行う〉との「自国管轄方式」の原則を立てた。開明的な佐賀藩の出身だった大隈は、国家発展の基幹として重要であることを熟知していた。発足間もない新政府にあって日本の植民地化を防ぐ重大な方針決定だった。
鉄道は国家発展の原動力
維新政府にあって、鉄道推進論者は少数派だった。大隈は、「生まれたばかりで財政基盤の弱い国家の経済力を伸張するには、交通・運輸を発達させることが不可欠である」と考えていた。さらに、新国家はまだ形の上では旧藩の連合体のような段階だった。鉄道によって広域での物流、人流を促進することが、中央集権的な国家形成に利するとの狙いがあった。
しかし、守旧派士族たちは、「鉄道が経済に利するところは小さい。かえって鉄道は敵の侵略に利用される危険がある。無駄な鉄道に財力を注ぎ込むぐらいなら、海軍力を増強すべきだ」と鉄道建設に反対した。
大隈の鉄道推進論に賛同したのが、会計(大蔵)官僚として力をつけ始めていた伊藤博文だ。二人は開明派で大蔵卿の伊達宗城(だて・むねなり=旧宇和島藩主)を立てながら鉄道敷設計画を推進してゆく。
二人は、鉄道先進国である英国の公使パークスの助言を得ながら、計画を進め、1869年(明治2年)12月7日、天皇の隣席を仰いだ廟議で、鉄道敷設計画が正式に決定された。
〈幹線は東京と京都を連絡する。枝線は東京より横浜に至り、また琵琶湖周辺より敦賀に達し、別に一線は京都より神戸に至るべし〉
当初計画の幹線は内陸の中山道経由で東西を結ぶものだったが、のちに東海道経由に改められる。そして翌年4月にはパイロット路線として東京・新橋と開港地横浜間29キロが着工され2年半で完成を見ることになる。
大隈と伊藤は資金手当にも配慮した。パイロット路線には公債を募り、この早期完成を見せることで、全国各地に民間資本で鉄道網を建設することを期したのだ。実際にその後、東北本線、中央本線などが地元財界の出資した新会社で次々と着工され、物流と人流の幹線となってゆく。
生まれたての新国家の担い手たちの決断が自前の鉄道を準備し、いま、われわれに大きな財産を残した。これこそ歴史の英断なのである。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考文献
『日本鉄道史 幕末・明治篇』老川慶喜著 中公新書
『日本の歴史20 明治維新』井上清著 中公文庫











































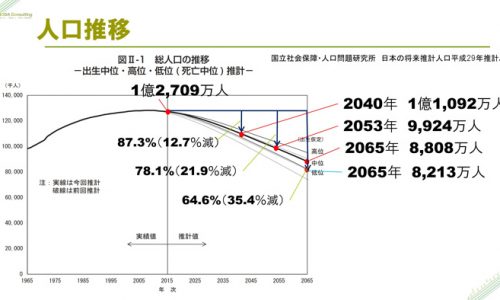
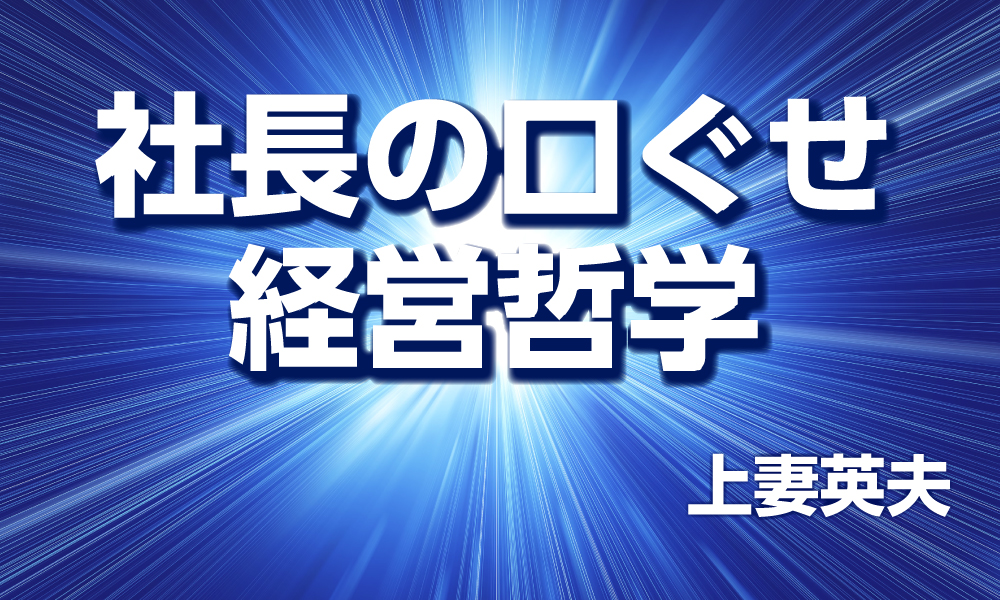


-1-500x300.jpg)