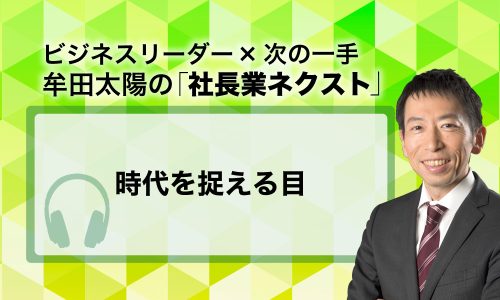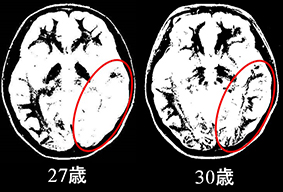巷で戦国武将の人気調査をすると、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の「三英傑」と呼ばれる人は必ず上位に入る。それぞれの考え方を「ほととぎす」に対する接し方で表現した有名な川柳もある。組織のリーダーの性格や行動も「織田型」、「徳川型」などと呼ばれることがあるほど、多くの人気を得ている人物だ。
三人の治世や性格、生涯についてはいろいろな見方もあろうが、信長は「直情径行型」、秀吉は「一代成功型」、家康は「隠忍自重型」とでも言えよう。
どんな性格や生涯であったにせよ、三人の功績なくしてはこの時代の日本の「天下統一」が果たせなかったであろうことは自明の理だ。中世の観点では近代的・合理的な感覚を持った信長の着想による「統治システム」を、金銭感覚に優れた秀吉が継承し、思想と金銭のバランス感覚を持った家康が合体させ、そこに自分の考えを加えて盤石のシステムを実行した。その結果、265年にわたり、大きな内乱のない泰平の「江戸時代」が続くことになる。歴史的偶然か必然か、血のつながりのないこの三代の連携プレイは見事なものだ。
余談になるが、江戸期の人々は「番付」を作るのが大好きだった。今も「ベスト〇〇」が健在なのと同じ感覚だろうが、明治の初期まで、変わったものでは実名で医者の番付まで作られた。「相撲」や「歌舞伎」などの人気商売だけではなく、多くの分野に浸透していたことがわかる。その中で、秀吉、家康は番付に名が載っても、信長はほとんどなかった。時代が「明治」と改まって以降、その時点から歴史を遡って見た時に、信長の感覚が「近代的」と感じられ、信長人気は急上昇し、今やベスト10の座から落ちることはない不動の人気者となった。泉下の信長がこの事実を知ったら、何と言うだろうか。
子供の時に人質に出され、いつ自分の首が刎ねられてもおかしくない状況で、自分の本心を押し隠してひたすら耐えることを学んだ家康。自らの出自を恥じ、血統を望み、さらには吝嗇であると思われないように大盤振舞をして、懐の深さを見せようとした秀吉は、終始コンプレックに付きまとわれた。弱小大名の子息ではあったが、当時の人々には考えられず、受け入れられもしない感覚を持っていたのが信長だった。
築城のために大きな石を山の上まで運ぶ仕事は「苦役」でしかない。しかし、信長は一番早く運んだ人々には褒美を与えると宣言し、家族も応援に来い、と労役を「祝祭」に変えた。このエピソードの真偽はともかくも、この発想は紛れもなく優秀な組織のリーダーのものだ。「泣かぬなら殺してしまえほととぎす」と、その短気さや奇行を取り上げられがちな信長が近代的だと人気を誇るのは、今のリーダーも学ぶべき行動が多いからだろう。今で言うパフォーマンスによる人心掌握術に長けたリーダー像も人気の原因の一つかもしれない。
しかし、運命は信長に日本を掌握させるまでの時間は与えなかった。現在とは少し離れた場所にあった京都・本能寺で、家臣の明智光秀に焼き討ちに遭い、数え年49歳の生涯を閉じることになった。その遺骸が発見されていないにも関わらず、全国で20か所を超える供養塔や衣冠墓があるのは、その人気ゆえだろう。
なぜ光秀が無謀とも思える特攻のような方法で謀反を起こしたのか、この理由も信長の遺骸の行方と共に歴史の謎の一つだ。いずれ明らかになるのかならないのか、それは別にしても、リーダーと腹心の関係性から読み取り、学ぶべきことは少なくない。
秀吉は信長に忠臣を尽くすことで出世の手掛かりを得た。その後の昇進の速さは、単なる要領だけではなく、機を見るに敏の長所を生かした行動である。主人の機嫌を損ねぬように、あるいは自分の本心を見抜かれていても悪びれずに「馬鹿になる」才能があったとも言える。その苦労は察するに余りあるが、それが信長亡き後、リーダーの座に就いた折に「人たらし」と呼ばれるほどの振る舞いにもつながり、自らの保身と相手を懐柔するためにそうした姿を演じ続けたのだとも言える。一方で、「朝鮮出兵」という大胆な行動に出る胆力も持っていた。
信長、秀吉の二代に仕えて辛酸を嘗めた家康は何事にも慎重な姿勢を生涯崩さず、自らの健康にも気を遣い、さまざまな面で「律する」ことを旨とした。「人の一生は重き荷を負うて遠き道を行くが如し」の言葉は、その性格と人生を端的に言い表している。信長は本能寺で炎に包まれる中、好んだ幸若舞『敦盛』の一節「人間五十年、下天のうちを比ぶれば夢まぼろしの如くなり」と謡ったという。秀吉の辞世は、「露と落ち露と消えにし我が身かな浪速のことは夢のまた夢」である。
これも「ほととぎす」の川柳同様とも取れるが、三人の人生観や生き方、行動原理を見事に表現したものだと言える。リーダーたる者、日常においてもその終焉にあっても、それらしき振る舞いを求められることを覚悟せねばならないのだろう。そのために、先人に学ぶ事例は多い。