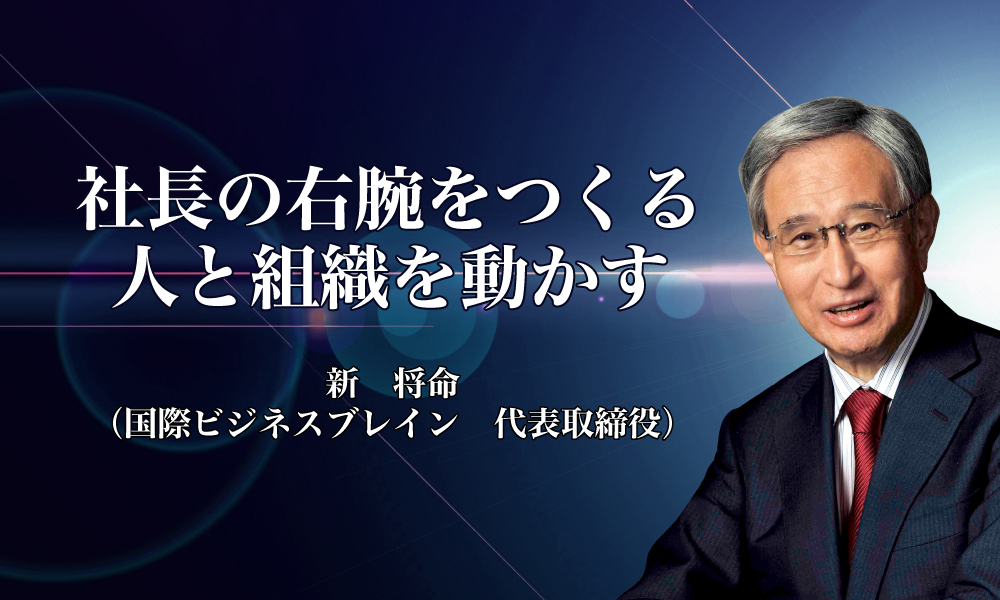【意味】
昔から、的を射た上申書ほど厳しいもので、厳しさは非難の表現に似ています。
【解説】
名著「貞観政要」には、数々の太宗の優れた治世の実例を挙げていますが、その根底には度量ある君主とその君主を信頼する臣下との強いきずながあります。
太宗の政治は、臣下の意見を受け入れ自らの治世に反映させる方法ですが、如何に名君太宗とはいえ、最初から度量大きく意見の受け入れができたのではありません。
例えば、貞観8年に臣下の徳参(トクサン)から厳しい上申書を提出されたところ、太宗はその批判の厳しさを受け入れることができずに、誹謗の輩として処罰しようとしています。
この時の太宗の狭量を戒めたのが、諫義大夫の魏徴であり、掲句はこの時の言葉です。「一般的に的を射た上申書は厳しいものです。その厳しさは誹謗中傷の書と似ているために、しばしば誤解されます」と。更に「このように誤解を招きやすいものが上申書ですから、本物の上申書かそれとも誹謗中傷の書かどうかを、陛下ご自身で念入りにご検討願います」と続けました。魏徴の諫言は、相手の行為の否定でなく自省を促すのが特徴であります。
その結果、太宗は「貴公でこそ言えることだ」と魏徴を誉め、徳参にも絹20段を与えました。平凡な皇帝であれば「貴公の口添えもある故に特別に計らう」などと、自己の判断ミスを取り繕う場合も多いのですが、太宗のレベルとなると決断変更をしています。
トップが一度決断したことを覆すには、さまざまなケースがあります。
まずその一つは、"外部を相手にする決断変更"です。外部との戦いや競争は臨機応戦が原則ですから、トップの方針変更には部下も素直に納得します。それ故に決断変更により部下の信頼を損なうことがないから、比較的安心して決断変更ができます。
もう一つは、"内部の者を相手にする決断変更"ですが、自らの判断で変更する場合と、部下からの進言によって変更する場合の二つがあります。
前者の自らの判断の変更のケースでは、例えば坐禅中の熟慮による変更であれば、トップの立派な省悟心となりますが、自らの判断であっても優柔不断の迷いからの変更となれば、部下は決断のできないトップと判断しますから信頼を失いかねません。
後者の部下の進言による変更のケースでは、トップと部下の間に"トップの度量に対する信頼関係"が前提となります。部下の方は、少々の出すぎた進言をしても"清濁併せ吞む"ことのできるトップであれば、心配なく進言ができます。またトップの方も、度々進言を受け入れても権威は失墜とならなければ、決断変更も柔軟にできることになります。