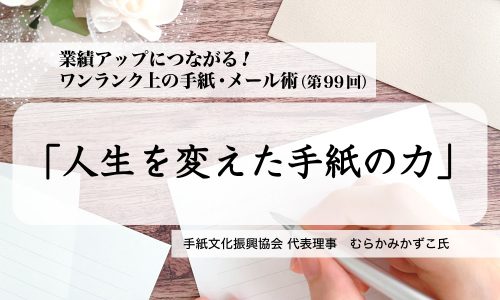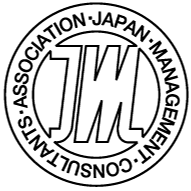平成14年に八十八ヶ箇所をまわられたと伺い、かねてから興味をもっていたので感想・効用を聞いてみた。
故に人間にもどれる。と。
1100年もの長きにわたって続くものには、本質的な力があるのかも知れない。
尚、四国の銘菓「畑田本舗」さんの玉の石という和菓子の栞(しおり)に、四国遍路の開祖「衛門三郎」の物語がある。
伊予の国、浮穴郡荏原(うけなぐんえばら)の里に、衛門三郎(えもんさぶろう)という強欲な郷長(ごうちょう)が住んでいました。ある日、托鉢に訪れた僧に非情な仕打ちしてしまった三郎は、次々と不幸に見舞われます。僧が弘法大師だったこと知り、懺悔の気持ちを胸に旅に出た三郎が、大師に出会えたのは二十一回目の巡礼の時。過酷な旅で、病に倒れた三郎の枕元に大師が立ち、「衛門三郎」と刻んだ石を左の手に握らせると、三郎は安心して息を引き取りました。
その後、伊予の国・道後の領主河野息利に男の子が生まれましたが、左手を固く握り開きません。そこで、河野家の菩提寺安養寺に連れていき祈念すると手が開き、「衛門三郎」と刻んだ小石が出てきたといいます。石は寺に納められ、寺名を石手寺に改められました。
「玉の石」と呼ばれるその石は、現在、石手寺の大講堂に納められ、一般にも公開されている。