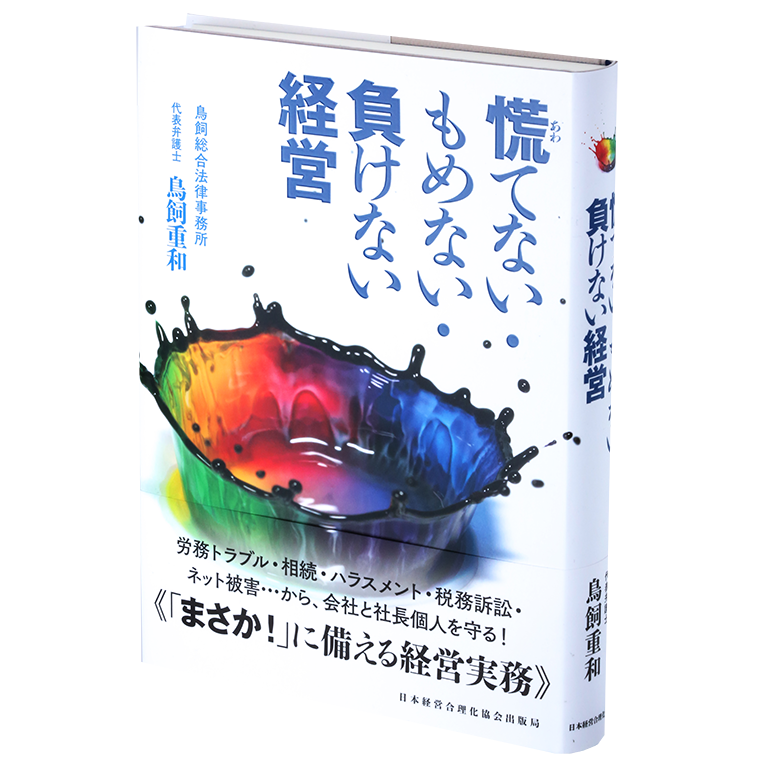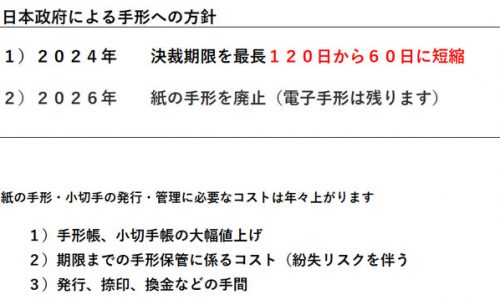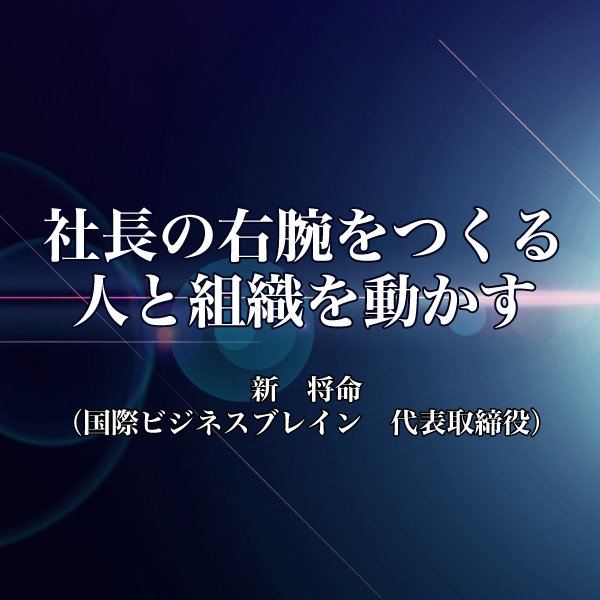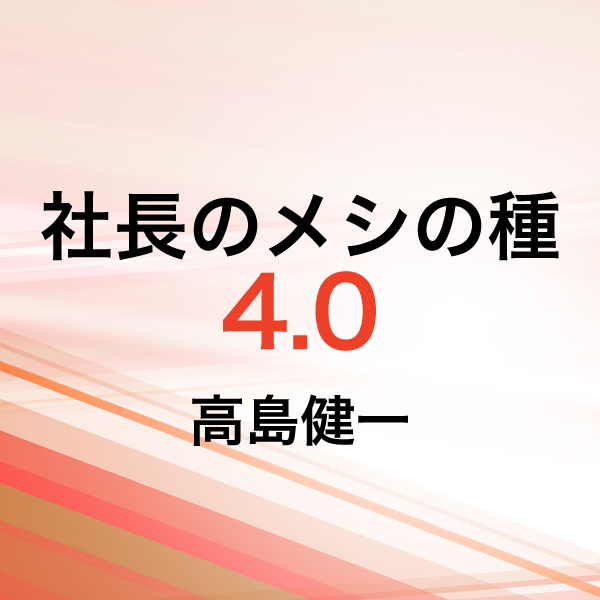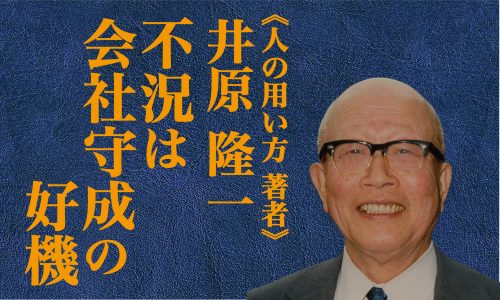- ホーム
- 中小企業の新たな法律リスク
- 第51回 『メンタルヘルス不調による休職からの復職』
何らかの精神疾患等、メンタルヘルスの不調により就業に困難をきたして休職させた社員への対応に苦労している企業は少なくないでしょう。主治医の診断書に従って復職をさせたものの、なかなか通常の勤務ができるようにならなかったり、再び不調になって休職を繰り返したりすることは、珍しいことではありません。
* * *
名倉社長: メンタルヘルス不調で休職している社員が、就業規則で定めている1年間の休職期間が終わる間ぎわに、「復職可能」という主治医の診断書をつけて復職を求めてきたのですが、復職させなければまずいでしょうか。
賛多弁護士:通常のように就業できるようになったというのであれば、復職させなければなりませんね。休職期間が満了しても復職できなければ、就業規則によって退職になるのでしょうから、社員が退職に納得しなければ、退職が法的に無効だとして裁判を起こすかもしれません。
名倉社長:その社員は、休んでいる間、会社から連絡されることを嫌がっていたので、病気に差し障ってもいけないと思って、そっとしておいたのです。もうすぐ休職期間が終わるので、このまま退職するつもりなのだろうと思っていました。本当に働ける状態なのか疑わしいので、別のドクターに診察してもらってセカンドオピニオンをもらいたいのですが、精神科の良いドクターをご存知でしょうか。
賛多弁護士:まず、患者が主治医ではない医師の診察を受けてその意見を聞いてみるという通常のセカンドオピニオンと、社長ご自身が社員の復職を認めるべきかを判断する参考にするために医師にその社員を診てもらって意見を聞くこととは、全く異なることなので、区別してください。
通常のセカンドオピニオンを提供する医師は、主治医と同じく、社員本人との診療契約に基づいて、医療行為として診察します。何よりも、患者さんの利益を第一に考え、病気の治療に全力を尽くす立場です。
一方、会社との契約に基づき、社員が、健康上の問題が支障にならずに働くことができる状態か、また、働くことが健康上の問題を発生させたり悪化させたりするおそれがないか等について医学的な見地から会社に助言する一環として社員を面接することは、「産業保健」としての医師の業務であり、医療行為ではありません。
後者の典型が、産業医です。御社にも産業医がおられるでしょう。
名倉社長:近所で内科を開業している知り合いの医師が産業医になってくれているのですが、精神科のことはよく分からないからと言って尻込みしているのです。
賛多弁護士:たとえ精神科を専門にしている医師でも、その人が働くことができる状態かどうかを判断することは、必ずしも容易ではありません。医学的に治療の対象にする精神疾患の症状がおさまって日常生活ができるようになったことと、会社から求められる仕事をできるようになることとの間には、決して小さくない隔たりがあるものです。
名倉社長:社員がその隔たりを埋めるためには、どうしたらよいのでしょうか。また、会社としては、その隔たりが埋められたことを、どうやって確認したらよいのでしょうか。
賛多弁護士:素晴らしいご質問ですね。
会社ができることは、社員に対して、あらかじめ、復職を許可できる状態の要件を示し、それを目標にした復職準備をすることを社員に求めることです。
社員自身は、主治医から安静にするよう指示されている時期には療養に専念しなければなりませんが、その後は、毎日の生活の記録をつけて、睡眠や食事などの生活習慣を整え、外出や勉強などの社会的な活動を増やして、仕事をする心身の状態を作っていくのです。大切なことは、その過程で、自分がどういうことをきっかけに心身の調子を崩しやすいのかを発見し、かつての自分の働き方や物事のとらえ方なども振り返り、それを繰り返さないためにはどうするかを考え、試行錯誤してもらうことです。
このような復職準備について、社員の方から会社に対して定期的に書面で報告するようにさせ、会社からもフィードバックして社員の努力を後押しするようにします。
名倉社長:まるで仕事のようですね。確かに、そのように復職を準備するプロセスを報告し続けてもらえば、仕事ができる状態になってきているかは、自ずと明らかになりますね。
賛多弁護士:おっしゃるとおりです。医師の判断に依存するのではなく、仕事の当事者である社員と会社が、再び働けるようになるという共通の目標に向けて、主体的に行動するのです。
名倉社長:社員が自分ひとりでこういう準備をしていると、独りよがりになってしまったり、対人関係を良好にする訓練が不足してしまったりすることはありませんか。
賛多弁護士:精神科などの医療機関で、心理カウンセリングや「デイケア」を提供していることもありますし、各都道府県の障害者職業センターが運営する「リワーク」に参加するのも良いでしょう。
名倉社長:社員も会社も、休職期間を漫然と過ごしていてはいけないことが良く分かりました。これからそういった復職プログラムを作りたいので、お手伝いいただいて宜しいですか。
賛多弁護士:もちろんです。
さしあたって、ご相談の社員の方については、産業医に面接していただいて、明らかに働かせるのはまずいと分かる状態であれば、主治医に再考いただくよう連絡するべきですが、それほどでなければ復職は認めるのが無難でしょう。ただし、残業させないなどの配慮をする期間は予め明示し、その間に通常の働き方に戻ることができなければ、再び療養し、今度は会社が定めるプログラムに沿って復職準備してもらうことを社員本人に伝えておくのが良いでしょう。
* * *
職場は働く場所なのですから、働くことができるかどうかは、本来、当事者である社員と会社でこそ判断できるはずのことであり、医師の意見を伺うのは、当事者が働くという判断をしようとするときにドクターストップを掛けるかどうかを確認するためです。病気の治療と仕事の両立支援の機運が高まる中、病気が治ったかどうかではなく、求められる働きができるかどうかを軸に、休職制度を運用していくことが求められます。
【参考】
● 休職制度の適正な運用に効果をあげている代表的な手法として「高尾メソッド」があります。職場は働く場所であるという原点に立ち戻り、業務遂行レベルに着目した復職支援プログラムを構築し、休復職のプロセス全体にわたって使用する書式やチェックシート、書簡や面接のシナリオを用意しています。高尾総司著「健康管理は社員自身にやらせなさい―労務管理によるメンタルヘルス対策の極意」(保健文化社・2014年)、高尾総司・森悠太・前園健司著「ケーススタディ 面接シナリオによるメンタルヘルス対応の実務」(労働新聞社・2020年)等をご参照ください。
執筆:鳥飼総合法律事務所 弁護士 小島健一