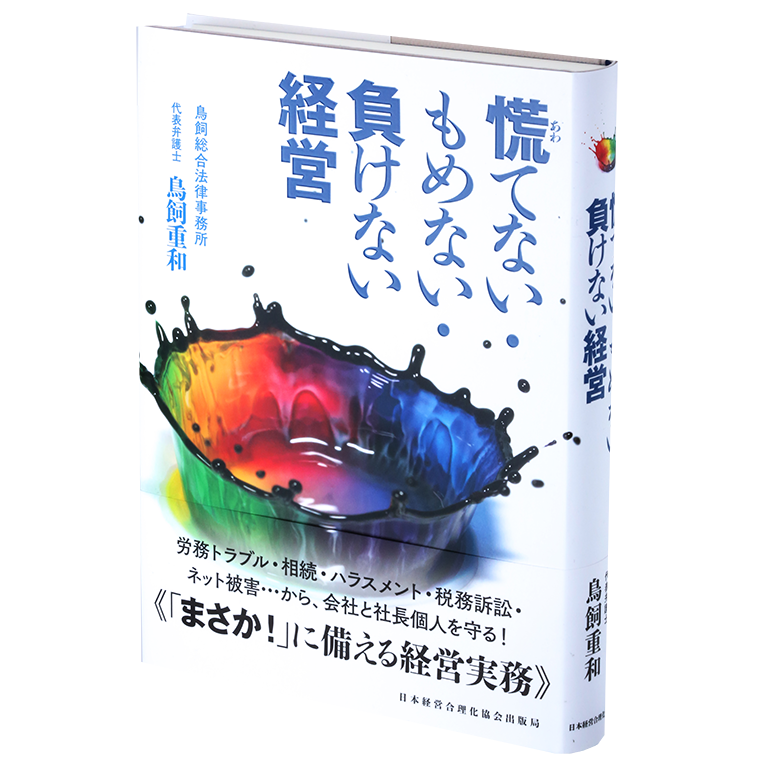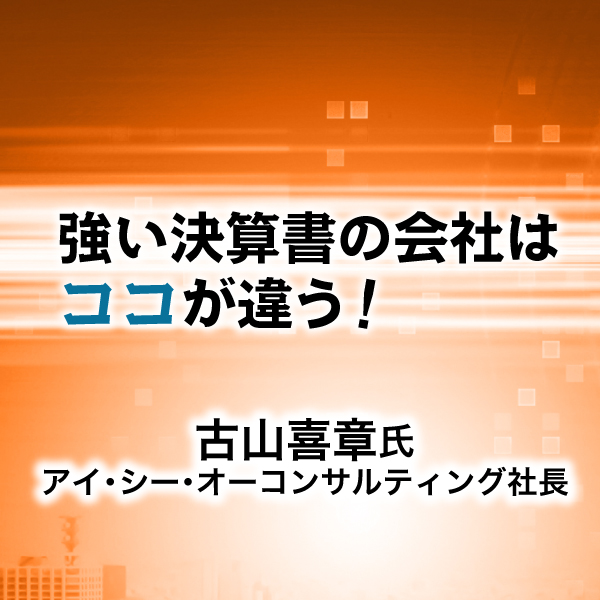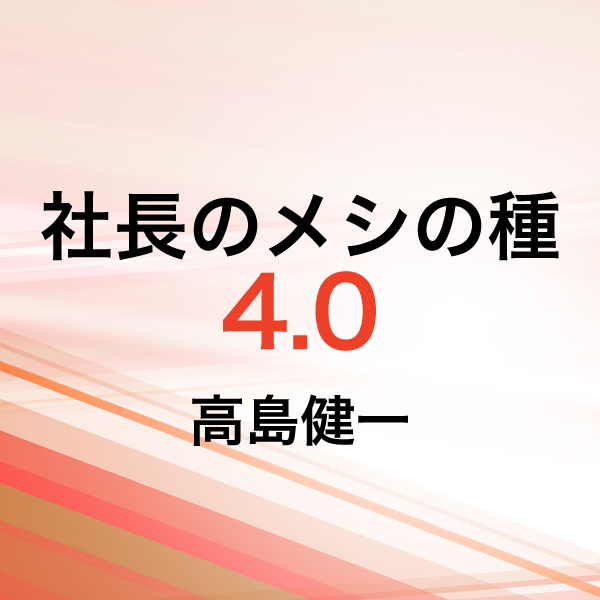改正された公益通報者保護法が令和4年6月から施行されました。
皆さんの会社も、新たに内部通報制度を設けたり、既にある内部通報制度のルールや運用を変更したりするなど、コンプライアンス強化の取組みを進めていることと思います。
公益通報者保護法による通報者の保護は、所属組織の規模を問わずに適用されていたのですが、この法改正によって、従業員数301人以上の組織では、通報に対応する窓口その他の体制整備等や対応業務の従事者の指定が「法的義務」とされ(同法11条1項・2項)、通報者が特定されてしまう情報について、従事者は刑事罰(同法21条。30万円以下の罰金)によって担保される守秘義務を負うことになりました(同法12条)。
従業員数300人以下の組織であれば、体制整備等や従事者指定は「努力義務」にとどまりますが(同法11条3項)、自主的に内部通報制度を設けている会社は少なくありません。
さらに、親会社が上場企業である場合には、親会社が「コーポレートガバナンス・コード」によって内部通報に係る適切な体制整備を要求されていることもあるため、親会社の内部通報制度がグループ会社をカバーすることとし、自社の従業員等が親会社の内部通報窓口へ通報できるようになっていることがあります。中小規模の組織であっても、ひとたび公益通報対応業務の従事者として指定された関係者には、公益通報者保護法による守秘義務の違反について罰則の適用があり得ることが否定できません(注1)。
* * *

賛多弁護士は、顧問先である物流会社の上田社長から、パワハラ問題に関する相談を受けています。
上田社長: 当社の内部通報窓口で受け付けたパワハラ通報にどう対応したらよいか、窓口と調査を担当している法務・コンプライアンス担当の社員が悩んでいるので、先生のお知恵を拝借させてください。
賛多弁護士: どうぞ、どうぞ。
上田社長: 実は先日、上司からパワハラを受けたと通報してきた社員が、『自分が通報したことがその上司に絶対にばれないように調査して、その上司を処分して他の部署へ異動させろ、それができないのであれば、自分を他の上司のところへ異動させろ!』と言ってきたのです。
賛多弁護士: なるほど。通報してきた社員のその気持ちは分からないではありませんが、それでは、事実の調査・認定に欠かせない上司や同僚へのヒアリングが難しく、担当者も板ばさみでしょうね。
上田社長: はい。このたび公益通報者保護法が改正されて、窓口や調査の業務に従事する者には、罰則つきの守秘義務が課されるようになったと聞きました。担当者は、通報社員がたとえ勘違いであっても、担当者から上司にばれたと思い込んで、自分を刑事告訴するのではないかと心配しています。
賛多弁護士: 担当者が安心して対応するために、通報社員から書面によって明確な同意なり、免責なりを得ておくことも考えられますが…。
上田社長: 実は、その通報社員は、今、メンタルヘルス不調で休職中なのです。
賛多弁護士: おやおや。困りましたね。
上田社長: 通報社員がメールで窓口に申し立てたパワハラの事実関係に辻褄が合わないところがあり、信用性が疑わしいので、担当者は、まず通報社員のヒアリングを実施したいと言っているのですが。
賛多弁護士: 精神疾患のために働けない状態で、自分の主張について根掘り葉掘り聞かれたり、ましてや、疑われたり、否定されたりする可能性があるヒアリングを受けさせることは、万一のことを考えて、復職して安定するまでは、控えた方がよいのではないでしょうか。
上田社長: そうなると、内部通報に対する調査が進められませんが、問題ないでしょうか。
賛多弁護士: はい、それを通報社員にしっかり説明してください。
もっとも、その部署には限定せずに他の部署も含めた社員全般に対して、アンケートを実施するとか、もっと広いテーマでヒアリングをするとか、カモフラージュした方法で実態調査を実施してみることは考えられます。その上司が、公然とパワハラをしているのであれば、浮かび上がってくるでしょう。
上田社長: これから、休職から復職するにあたっては、パワハラしたと通報されている上司が管理している休職前の部署へ職場復帰させるのは、問題があるでしょうか。
賛多弁護士: 原職復帰の原則どおりでしょうね。休職前の職場で従前からの業務へ復帰するのが、新しい人やことによるストレスが少ないですから。勿論、すでにその上司の管理や指導の方法に問題があることを察知しておられるなら、リスク回避のために、定期異動としてその上司を他の部署へ移しておくことも考えられますが。
上田社長: 内部通報窓口で受け付けても、解決できることがほとんどないですね…。
賛多弁護士: パワハラというものは、当事者相互の認知や感覚、価値観の違いから起きている現象という面がありますから、元来、隠れた不正を告発させるための内部通報制度には馴染みにくいのだろうと思います。内部通報窓口とは別途、教育やカウンセリングへと当事者双方を誘導できるように、ハラスメント専用の相談窓口を設けて、人事や産業保健に担当させた方が、適切に扱いやすいかもしれませんね。
1
2