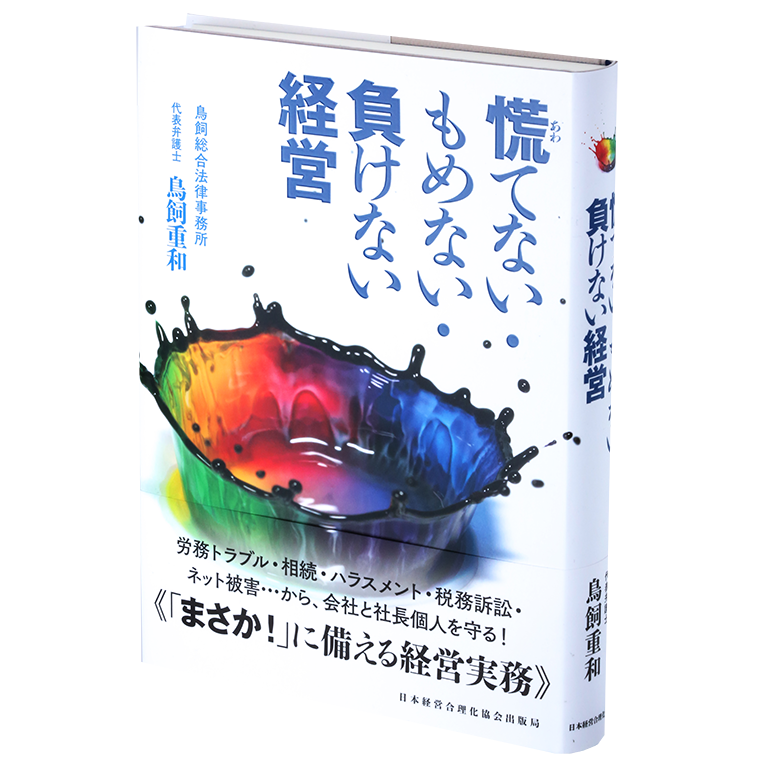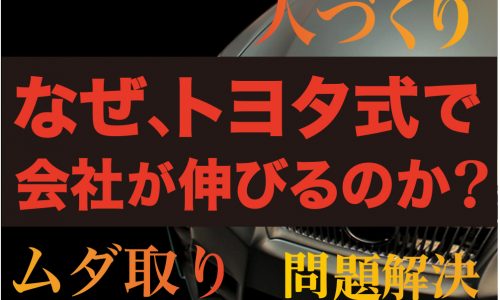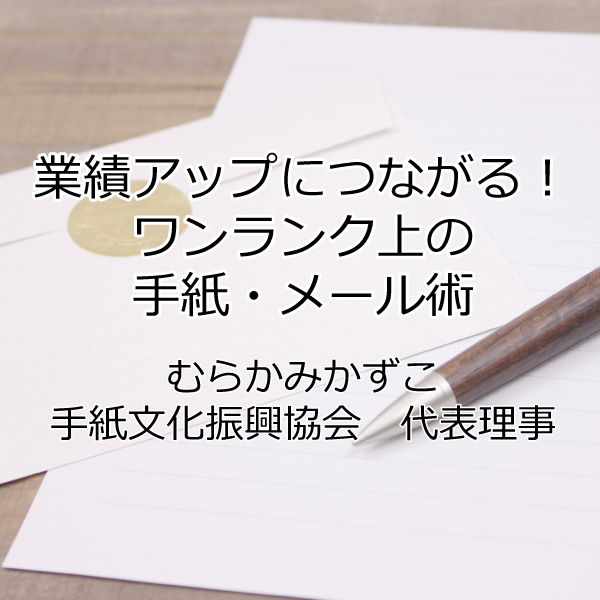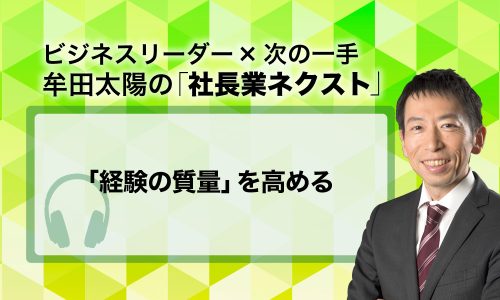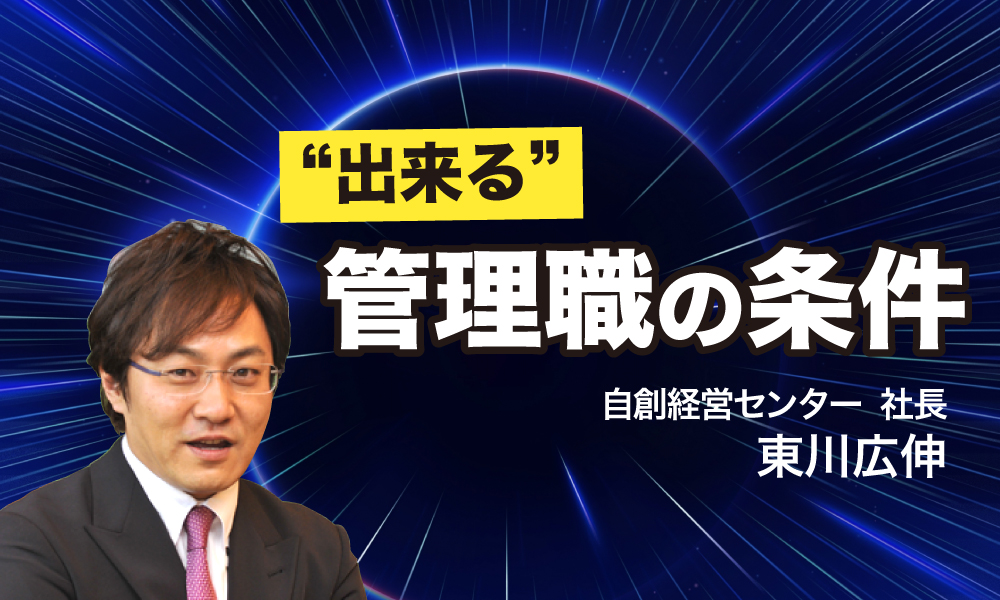山本社長は都内で飲食店を経営していますが、いくつかの店舗は建物を借りて営業をしています。今回、ある店舗のオーナーから賃貸借契約の更新をしない旨の連絡が届いたため、今後、どのように対応したらよいのか、山本社長は賛多弁護士に相談しました。
* * *
山本社長:当社は都内で飲食店を経営しています。そのうち何店舗かは建物を所有するオーナーから建物を借り、営業をしています。そのうちA店については、当社は、オーナーとの間で契約期間10年の賃貸借契約を締結しており、そろそろ契約期間の満了の時期が近づいていたため、契約の更新をしなければならないと考えていました。そうしたところ、先日、オーナーから賃貸借契約の更新はしない旨の連絡文書が届きました。その理由として、①建物の老朽化が進んできたため、建物の安全性向上のために建物を建て替えたい、②建物の収益性を高めるために高層の建物に建て替えたい、という事情が書かれていました。当社は、今後もこのA店で営業を続けたいのですが、オーナーが出て行ってほしいと言っている以上、出て行かなければならないのでしょうか。
賛多弁護士:建物の賃貸借契約には、「借地借家法」という特別な法律が適用されます。かつて地主や大家さんといった貸主の立場は強く、借主は貸主から出ていくよう求められれば、これに応じざるを得ませんでした。そこで、借主の権利を拡充し、借主の保護をはかるため、「借地法」、「借家法」という法律が定められ、今ではこれらに代わって「借地借家法」が定められています。
山本社長:借地借家法は、具体的にはどのようにして借主の保護をはかっているのでしょうか。
賛多弁護士:たとえば、契約期間を定めた賃貸借契約が契約期間満了になったとしても、貸主からその更新を拒絶するためには、契約期間の満了の1年前から6カ月前までの間に、借主に対して更新をしない旨の通知をしなければなりません。
山本社長:なるほど、だから今回、オーナーからそのような連絡文書が届いたんですね。
賛多弁護士:そのとおりです。ただ、貸主側から更新を拒絶するためにはこのような通知をすることに加えて、更新をしないことについて正当な事由があるといえなければなりません。
山本社長:特に理由もなく更新を拒絶することはできない、ということですね。正当な事由があるか、ないかはどのようにして決まるのでしょうか。
賛多弁護士:まず、前提として貸主にその建物を使用する必要があるといえることが必要です。その上で、貸主の建物使用の必要性が、借主の建物使用の必要性を上回るといえる場合に、更新拒絶について正当な事由があると判断されます。
山本社長:今回、A店のオーナーは、①建物の老朽化が進んできたため、建物の安全性向上のために建物を建て替えたいと言っていますが、これは貸主の建物使用の必要性を裏付けるものでしょうか。
賛多弁護士:いえ、ここで問題となるのは、あくまで貸主の建物を使用する必要性です。建物の安全性向上は、貸主の建物使用の必要性とは直接関係はしませんので、建物使用の必要性を裏付けるものとはいえません。ただし、建物の老朽化が著しい、あるいは、建物の耐震性能に大きな問題があるというような特別な事情がある場合には、そのような事情は、正当な事由の有無を判断する際に考慮されます。
山本社長:A店のオーナーは、②建物の収益性を高めるため、高層の建物に建て替えたいとも言っていますが、これは貸主の建物使用の必要性を裏付けるものでしょうか。
賛多弁護士:貸主は、建物を賃貸することで収益を上げるという事業を行っているといえますので、建物の収益性を高めるための建て替えは、貸主の建物使用の必要性を裏付けるものといえます。ただし、現に借主がその建物で営業を行っている場合、通常、貸主の建物使用の必要性が借主の建物使用の必要性を上回るとはいえないため、正当な事由は認められないでしょう。
山本社長:建物の収益性を高めるための建て替えをしたい貸主としては、どのような手立てがあるのでしょうか。
賛多弁護士:貸主の建物使用の必要性が借主の建物使用の必要性を上回るものではないものの、そこまで大きな差がないといえる場合、貸主は借主に立退料を提供することで、正当な事由があると認められやすくなります。また、借主としても立退料を受け取れるのであれば、賃貸借契約の終了に応じる場合もあります。そのため、建物の建て替えを理由として賃貸借契約の更新を拒絶する際には、実務上は、貸主と借主との間で立退料について交渉を行うということが広く行われています。
山本社長:当社としては、今後もA店で営業を続けたいとは考えていましたが、確かに建物の老朽化は気になっていました。当社としても賃貸借契約の終了に応じる場合には、オーナーとの間では、立退料について話し合いをすべきということでしょうか。
賛多弁護士:そうなりますね。建物の老朽化があまりにもひどいという場合はさておき、そうでない場合には、立退料について話し合いをすべきでしょう。
山本社長:立退料は、どのようにして決まるのでしょうか。
賛多弁護士:借主が新たな建物を借りるための費用(移転費用、仲介手数料、敷金等)や移転後に家賃が増えた場合には一定期間の賃料の増額分、また、一定期間の営業補償などをもとに決められます。
山本社長:なるほど。貸主は、建物を賃貸すると、なかなか借主から返還を受けることが難しいということが今回、よく分かりましたが、そうなると、建物を賃貸することをためらってしまう貸主も出てきてしまうのではないでしょうか。
賛多弁護士:借地借家法は、そのような貸主の事情も踏まえ、「定期建物賃貸借」という特別な契約を定めています。これは、通常の建物賃貸借契約と異なり、契約の更新がないことを適法に契約内容として定めることができるもので、定期建物賃貸借契約の場合、賃貸期間満了により契約は終了となります。そのため、たとえば、老朽化が進んできた建物を建て替えまでの数年間に限って貸したいというような場合に利用されています。
山本社長:なるほど、借地借家法では貸主にも配慮した定期建物賃貸借契約という契約類型を定めているということですね。
賛多弁護士:そのとおりです。そうなると、今回のA店のオーナーとしては、もし、御社と10年前に建物の賃貸借契約を交わした際、10年後の建て替えを予定していたのであれば、定期建物賃貸借契約を交わすべきだったといえるでしょう。そうすれば、今回、御社に立退料を支払う必要もなく、契約を終了させることができました。ただ、御社としては、10年間という期間限定ということであれば、A店の建物を借りなかったかもしれませんが。
山本社長:そうですね。建物を賃貸する際には、将来のことも想定しつつ、慎重に検討すべきということがよく分かりました。
* * *
建物の賃貸は広く行われていますが、建物の賃貸借契約には借地借家法が適用されます。そして、借地借家法は、借主を保護するため、様々な定めを置いています。今回の契約更新に関するルールは、その1つです(借地借家法26条~28条)。また、どのような場合に契約更新の拒絶、つまり、正当な事由が認められるかは、実務上、度々、裁判で争われ、多数の判決が存在します。立退料の金額に関する問題についても同様です。
定期建物賃貸借契約は、契約更新がないため、貸主にとっては利用しやすい契約といえますが、①書面による賃貸借契約の締結、②一定の内容を記載した書面の交付、③更新がない旨の説明、が求められます(同法38条1項、2項)。書面によって賃貸借契約を締結し、一定の内容を記載した書面を交付したとしても、更新がない旨の説明を怠った場合は、通常の建物賃貸借契約になってしまいます(同法38条5項)。そのため、定期建物賃貸借契約を締結する際には、通常の建物賃貸借契約の締結と比して一層の注意が必要です。
執筆:鳥飼総合法律事務所 弁護士 山田 重則