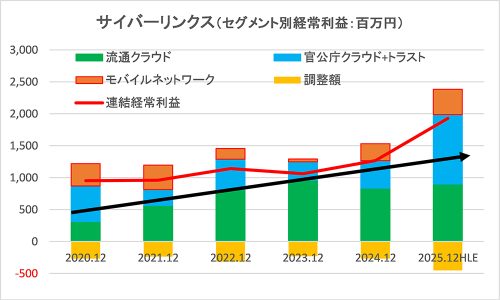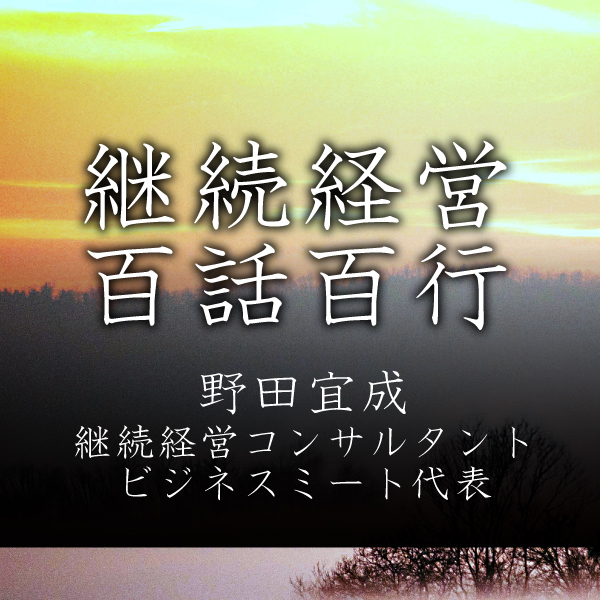「ギバー」は人間の「本性」
前回の「GIVE & TAKE」の話を続ける。
ギバーであるためにはどうすればいいのか。薄っぺらな自己啓発書だと、「悔い改めよ」とか「これからはこういうことをしなければならない」とか、あっさり言えば「頑張れ!」という話に終始することが多い。
これに対して、『GIVE & TAKE』の著者、アダム・グラントの発想と主張は180度異なる。ギバーであることは人間の本性だ。もともと人間がもっている本性を正面から見据えて理解すれば、人間は自然とあるべきギバーに戻っていく――そういう論理展開になっている。
例えば、「自己利益」と「他者利益」についての著者の議論がその典型だ。多くの人は「他者に利益を渡す=自分の利益がなくなる」と考える。だから、「他者のために何かしてあげたい」「ギバーになりたい」と思っても、なかなか行動できない。
成功するギバーが持つ「他者志向性」とは
しかし、「自己利益」と「他者利益」は一つの次元の両極ではない、したがって相反するものではない。他者に利益をもたらすためには、自己犠牲は必要ないのである。成功するギバーは、「自己犠牲」ではなく、「他者志向性」をもっている。他者志向性とは、たとえばチームで仕事をするときに、自分の取り分を心配するのではなく、みんなの幸せのために高い成果を出す、そこに目的を設定するということだ。
「自分にとって意義のあることをする」「自分が楽しめることをする」――この条件が満たされれば、ギバーは他人だけではなく、自分にも「与える」ことができる。自分が認識する「意義」のもとに、他者と自己が一体化するからだ。他者に対する共感と愛着が生まれる。こうなると、ギブはもはや犠牲ではない。何のことはない、真のギバーはギブすることによって他者のみならず、意義に向かって仕事をする自分自身を助けているのである。だから自然とギブするという成り行きだ。
「情けは人のためならず」という考え方は、アメリカ人よりも日本人にとって、より親和性が高いだろう。アメリカでは、ことビジネスとなると、極端な「テイカー社会」である。「うかうかしているとやられてしまう」という考え方が、歴史的、社会的、文化的に共有されている。
本書に書かれていることは、アメリカ人たちにとっては驚きの発見ばかりかもしれないが、日本の読者にしてみれば「昔からいわれている、当たり前のことじゃないか……」という感想を持つかもしれない。
「情けは人のためならず」は日本の「天然資源」
だとすれば、それは日本にとって重要な意味のあることだ。ビジネスにおいてもギバーが(潜在的に)多いということは、日本の社会と日本人が伝統的にもっている「天然資源」といってよい。しかし、一歩間違えると、その美点が自己犠牲にすり替わってしまう。人に自己犠牲を強いることにもなりかねない。ギバーになるということは、「仕事とは、いったい何のためにするのか」ということを、突きつめるということだ。そもそも仕事というのは、「自分以外の誰かのためにするもの」だ。こんなことをいうと「きれいごと」に聞こえるかもしれないが、そういう話ではない。単純に、「仕事」は「趣味」とは違うというだけの話だ。
たとえば、「釣り」は趣味だ。趣味であれば自分志向でまったく構わない。自分が楽しければいい。ところが「漁師」となると、それは仕事だ。人のために新鮮で安全な食料を安定的に供給しなければならない。魚を買ってくれる他者のためにならなければ仕事にならない。世のため人のためと大上段に構える必要はない。ささやかであっても必ず自分以外の誰かのためになるから、仕事として成立する。この意味で、趣味は仕事ではない。当たり前の話だ。
「仕事の評価」は誰がするものか?
「この人は頼りになるな」「役に立ってくれたな」。人にそう思われてはじめて「仕事」になる。裏を返せば、テイカーは、そもそも仕事に向いていないといってもよい。仕事として仕事に向き合っていないのである。
テイカーの頭の中は「自分の評価」でいつもいっぱいになっている。自分の評価をなるべく楽をして上げることしか考えていないからだ。世間でよくありがちな「人脈術」などというものも同じことだ。たとえば、「誰と知り合えば自分のビジネスが有利になるのか」「どの人間と仲よくすれば、おいしい話があるのか」など、ひたすら自分のことにしか目が行っていない。これでは趣味である。仕事ではない。
そもそも、仕事の評価は自分でするものではない。それが仕事である以上、他社に評価されてこその仕事だ。ギバーとは、この当たり前のことを実践している人々である。