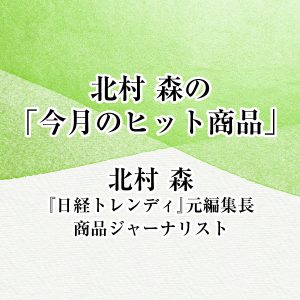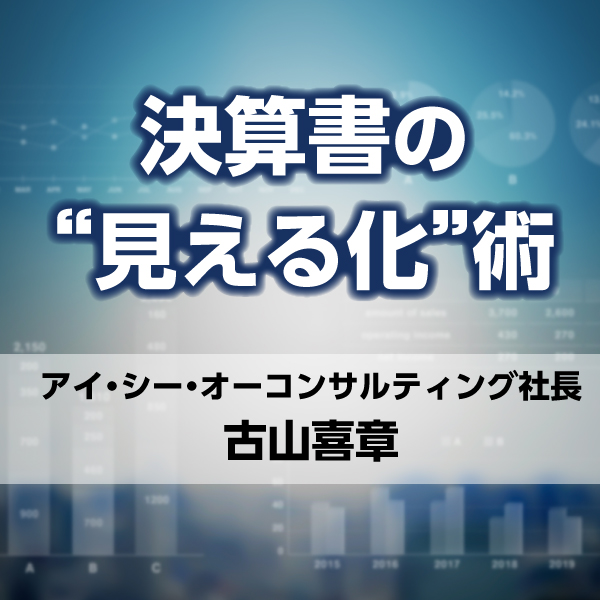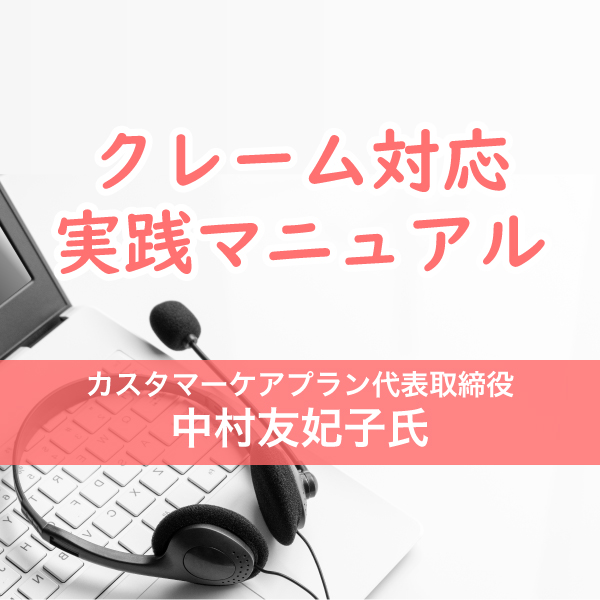これをヒット商品という言葉でくくっていいのかには躊躇があるものの、地域からの取り組みとして多くの人を振り向かせているのは事実ですから、今回、お伝えしたいと考えました。
昨年(2024年)の元日、北陸地方は能登半島地震に見舞われました。1年半ほどが経過していますが、復興への道は半ばであると知った、そういう話です。
なぜ、現在の状況を学べたかと言いますと、先月、能登半島を訪れて、第三セクターによって運営されている「のと鉄道」が運行する「震災語り部観光列車」に乗車してきたからでした。

のと鉄道は、石川県で最初に観光列車を走らせた鉄道会社だったといいます。ところが昨年の震災から1年3カ月ものあいだ、観光列車は営業運転を休止したままでした。
その観光列車の車両を生かし、今年(2025年)4月に運行開始したのが、「震災語り部観光列車」です。4月から大型連休直後までの土曜日曜と祝日に、1日3往復。座席は予約制で900円(乗車券は別)、のと鉄道のサイトや電話で予約を受け付けていました。
七尾駅と穴水駅とのあいだを、小1時間かけて走ります。大型連休の時期は乗車する客でとても賑わいをみせたと聞きます。

車両の内部はとても凝ったつくりです。
写真は組子細工です。とても端正なしつらいでした。また、車内では輪島塗をはじめとした作品の数々を目にすることもできます。
能登半島にはいくつもの職人文化が宿っていることを改めて理解できる、そんな車両なのです。能登に根づく伝統工芸によって彩られていて、車内を歩くだけでも心躍ります。と同時に、伝統工芸の歴史を支える職人さんたちのこれからを思わずにはいられません。

列車が走り出すと、アテンダントさんが能登の歴史、沿線の風景にまつわる逸話を教えてくれます。
そして、しばらく経ったところで、昨年元日の状況をアテンダントさんは語り始めました。大きく揺れた瞬間から、乗り合わせていた客全員をどう誘導したか、でした。坂道を急ぎ、避難所にたどり着いたものの、肝心の鍵がすぐに見つからなかったこと。その夜は眠らずに対応策に集中したこと…。
そう伝えてくれるアテンダントさんの話に合わせて、また別のアテンダントさんが、写真を貼ったパネルを手に、それぞれの座席をめぐり、細く説明を加えてくれました。
沿線には、屋根にシートを被せた状態のままの家屋が残っていました。被害がとりわけ甚大だった地区を中心に、復旧はいまもなお続いているのだと知りました。

アテンダントさんは私たち乗客に、地元の人たちが奮闘している姿についても語りました。
牡蠣の生産者たちが設備を復活させて頑張っている話、あるいは能登半島の先のほうに広がる千枚田(海に向けて広がる棚田です)が崩れたのを有志が懸命に直して今年も田植えできたという話などでした。
さらには、一部のトンネルが土砂で埋まってしまった、のと鉄道の路線を、震災からわずか3カ月で全線復旧させて運行を再開するに至るまでの話も、印象に深く刻まれました。社員は駅舎に寝泊まりし続け、県外からはいくつもの会社が力を貸してくれたそうです。
この列車を体験して改めて思ったのは、私たちが震災を忘れない、ちゃんと覚えていることの大切さについてです。直接に被災をしておらず、遠方で暮らしている立場であっても、記憶にとどめておく、そして、支援について思いを馳せ、ちいさくても行動に移す。「震災語り部観光列車」に乗りに行くことも、まさにそうですね。
この列車、次回は7月19日〜8月31日の土曜日曜と祝日に運行予定です。座席の予約は、乗車の1カ月前から同社のサイトもしくは電話から可能になります。