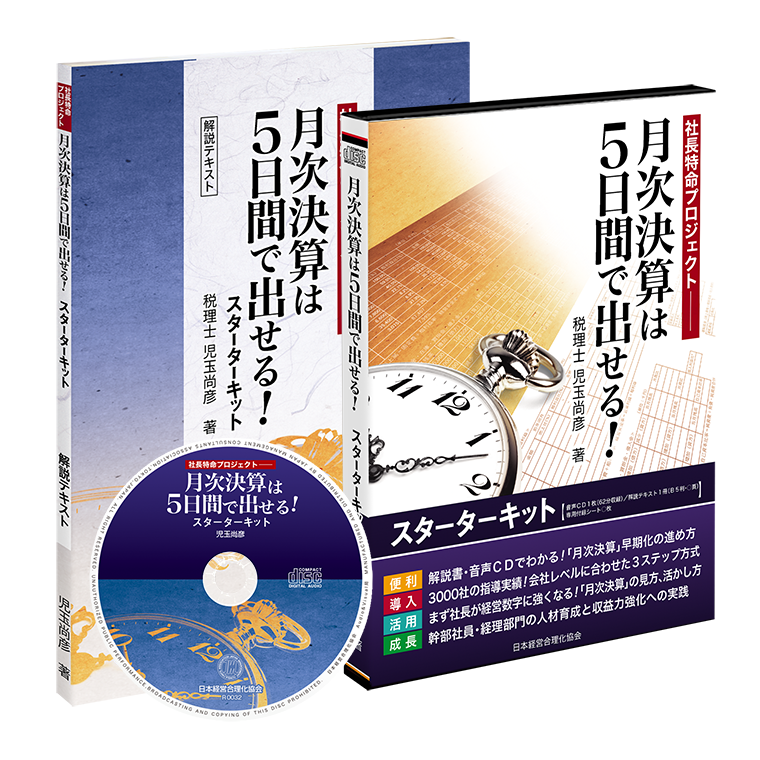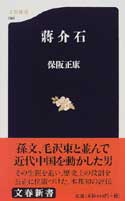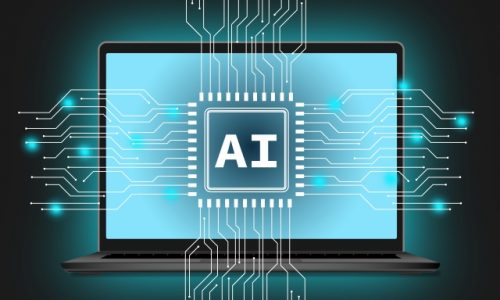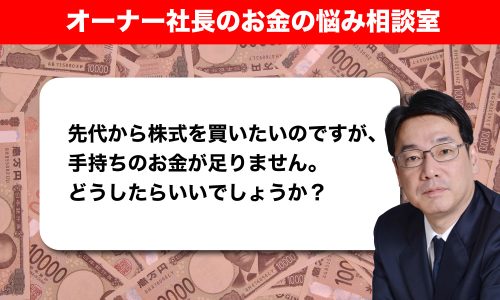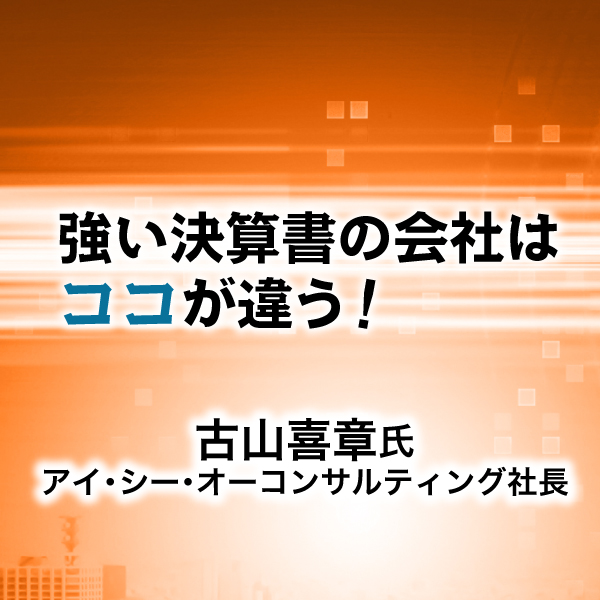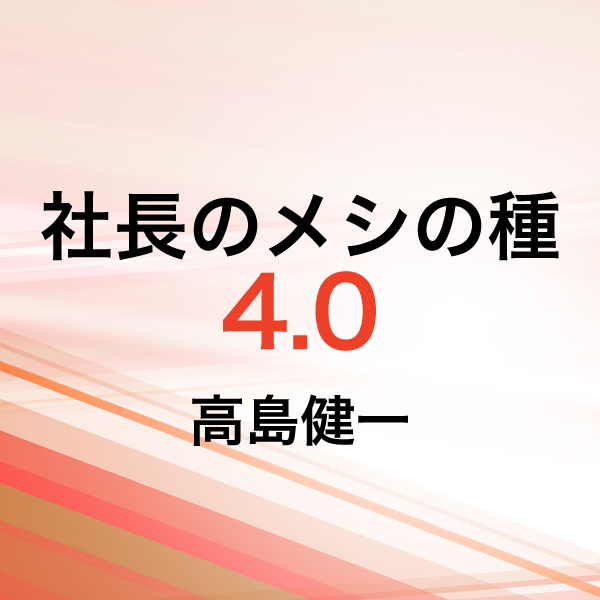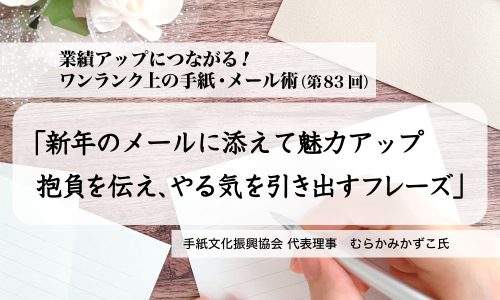下請法改正による中小企業の経営環境の整備

令和7(2025)年5月に下請法が改正され、令和8(2026)年1月施行となります。
この改正は、中小企業、特に下請事業者の経営環境を大きく左右する重要なものです。
取引の上下関係を表していた「下請」という用語は廃止され、「下請事業者」は「中小受託事業者」、「親事業者」は「委託事業者」に改められました。
特に、長年の課題であった価格交渉の適正化、および下請事業者の資金繰りを圧迫してきた手形払いの原則禁止は、中小企業の経営者、そして経理担当者にとって、すぐに対応すべき事項となります。
そこで今回は、下請法改正で中小企業が取り組むべきことについて、説明します。
下請法改正の内容を理解していますか?
価格交渉の義務化と一方的な価格決定の禁止

今回の下請法改正で、委託事業者(親事業者)が中小受託事業者(下請事業者)との価格協議に応じない、または必要な情報提供を行わずに一方的に代金額を決定する行為が禁止されました。
これまでも「買いたたき」と言われる一方的な「値下げ」は禁じられていましたが、今回の改正で、「値上げ」交渉に応じないことも禁じられました。
これは、原材料費や人件費の高騰が続く現状において、中小企業が適切な価格転嫁を行えるようにするための措置です。
これまで値上げ交渉をしても、なかなか受け容れてもらえなかった下請事業者も、正当に価格交渉ができるようになります。
しかし親事業者が価格交渉のテーブルに着く姿勢を示したからといって、値上げを簡単に了承するとは限りません。
人件費や材料費、設備費などの上昇率、そして適正な利益率を明確に盛り込んだ見積もりを提示する準備が必要となります。
会社としては、原価構成やコスト増加の要因を具体的に説明し、価格改定の正当性を示す資料を準備することが重要です。
経理担当者に指示し、原価計算の根拠となる材料費や労務費、間接経費を正確に把握し、製品やサービスごとの原価を算出できる体制を確立しておきましょう。
また、契約期間中でも、コスト変動に応じて価格を見直す機会を設けることが推奨されていますので、経済情勢に合わせて定期的な価格の見直しを発注側と相談するようにしてください。
賃上げとインフレに見合う価格転嫁ができていますか?