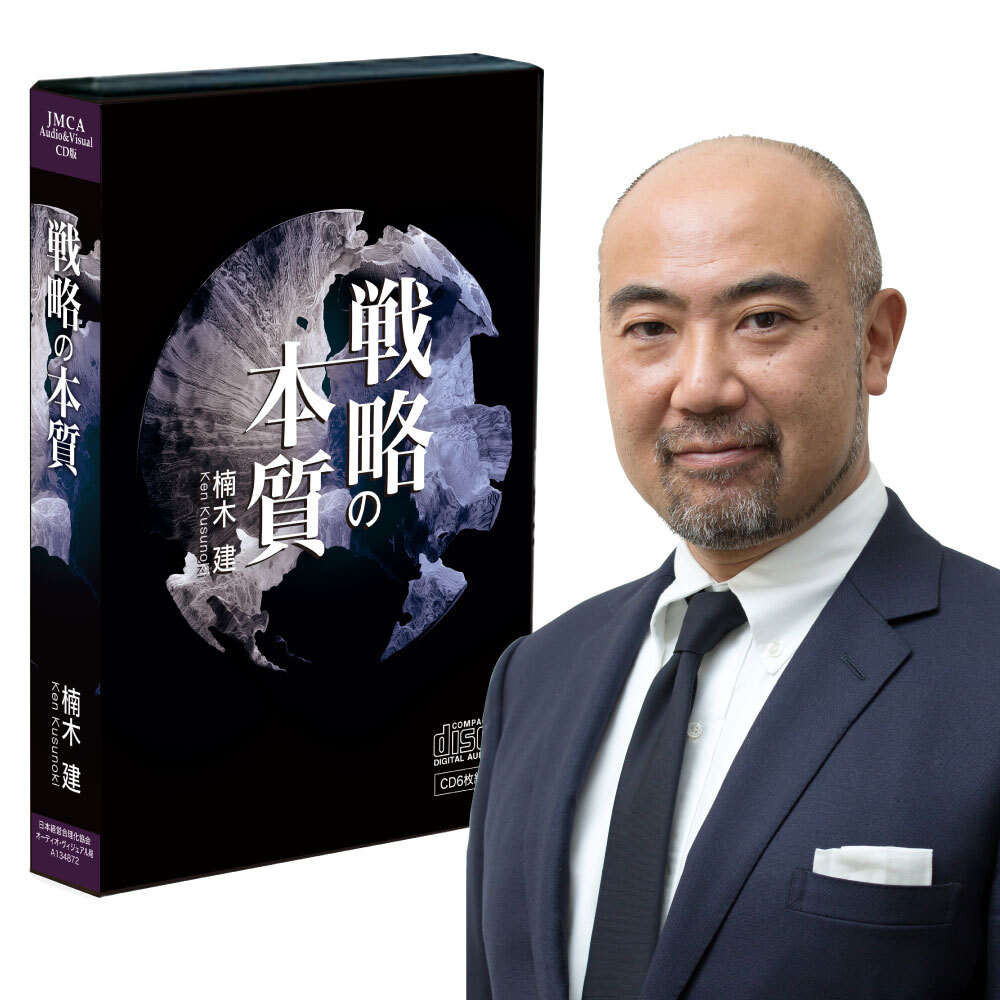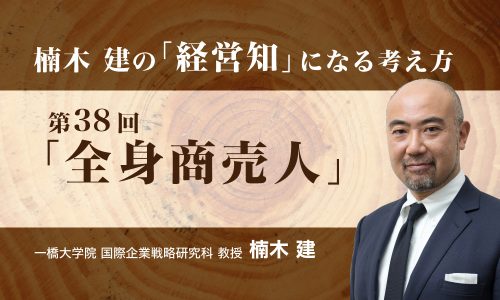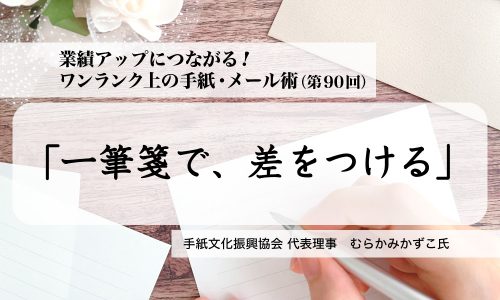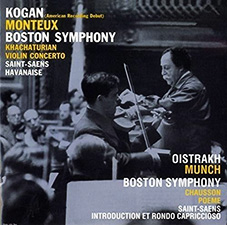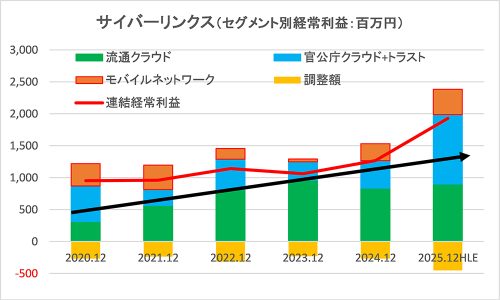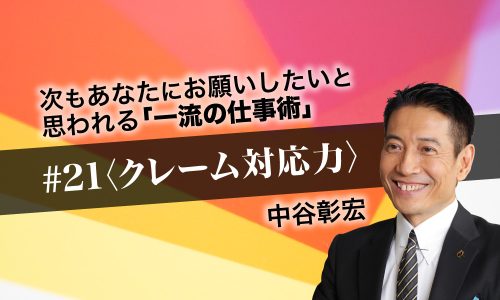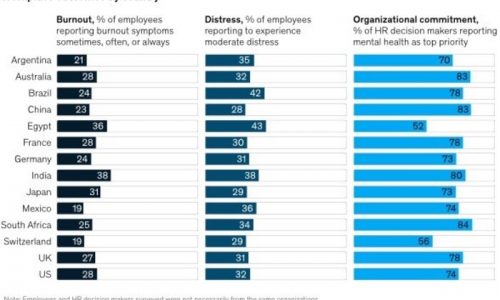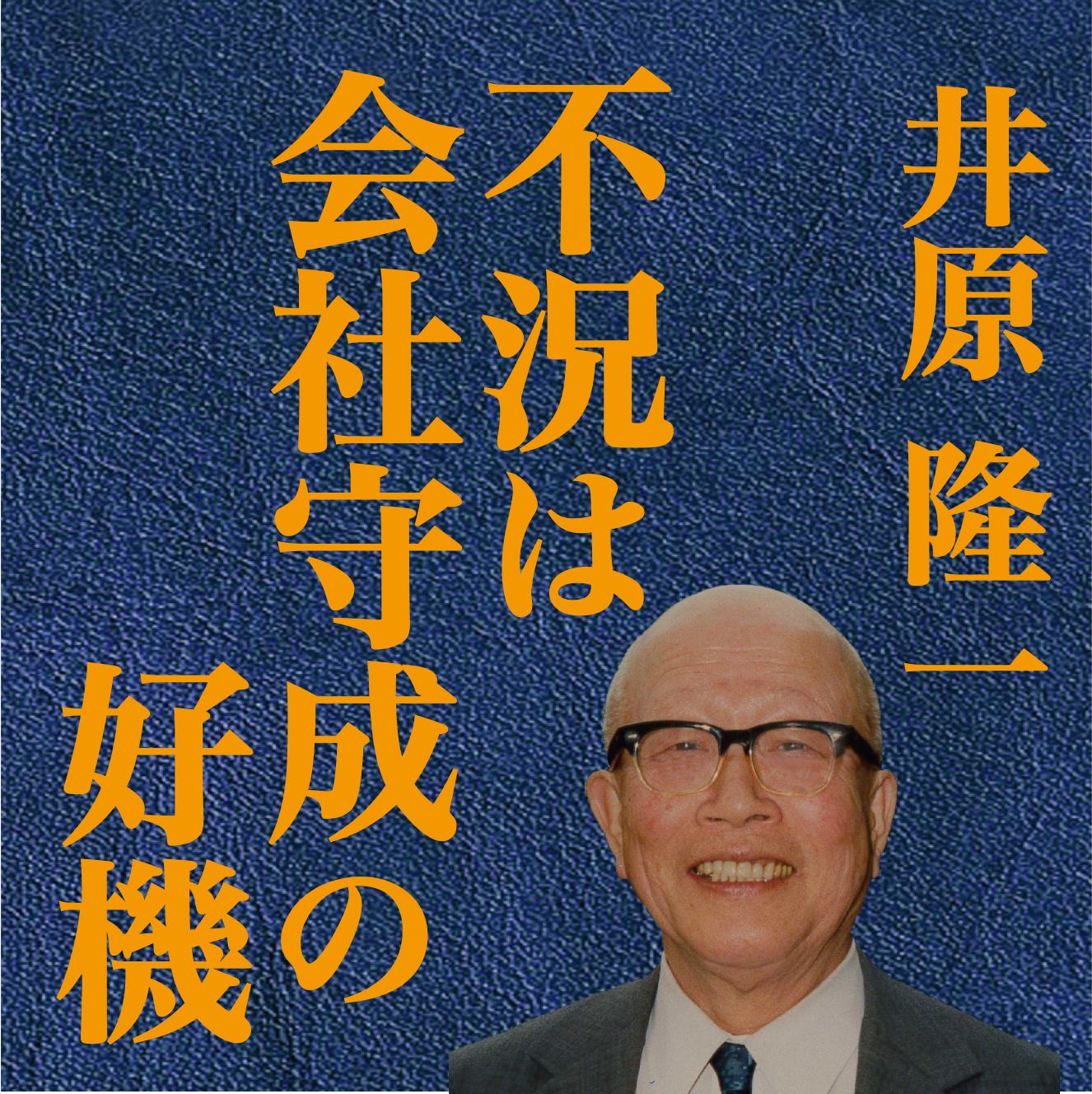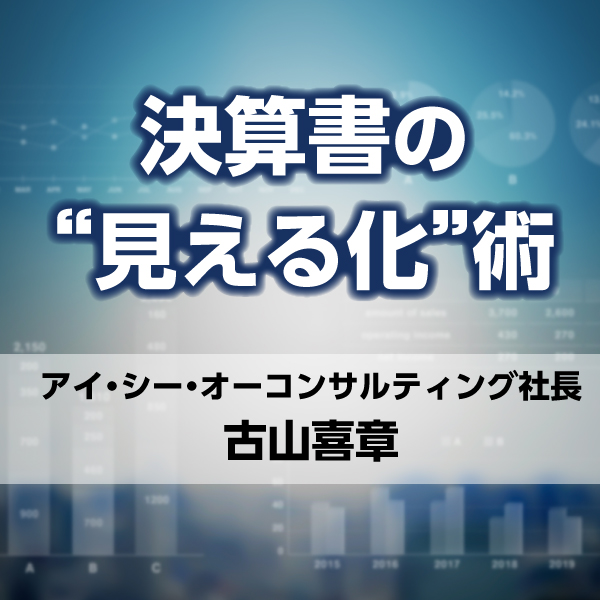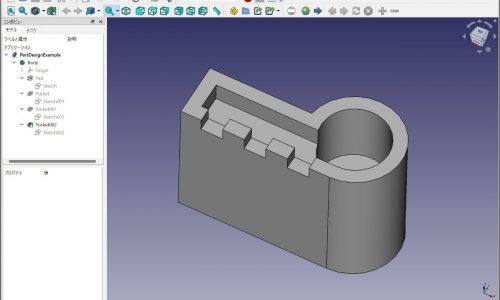紙ベースのスケジュール管理にこだわる理由
スケジュール管理でデジタル・ツールを一切使っていない。万が一紙の手帳を紛失してしまうと、とんでもないことになる。その先、どこでいつ何をやるのかがまったくもってわからなくなってしまう。対策としては「なくさないように気をつける」ぐらいしかない。あまりに大切なものだからか、いつも無意識のうちに意識しているようで、手帳を失くしたことはこれまでにない。
かつて一度だけ「ついに失くしたか?」と冷や汗をかいたことがあった。気づいてから自分の直近の行動を振り返ってみると、軽井沢の家に置き忘れたのではないか――わざわざ手帳があるかどうかを確認するためだけのために新幹線で軽井沢を往復した。テーブルの上に手帳があるのを見つけたときはホッとした。
さっさとデジタルのスケジュール管理に移行すればイイのでは……という意見をもらうことがある。しかし、僕の場合はこれからもおそらく紙の手帳を使い続けると思う。
というのは、デジタルは「遅すぎる」からだ。まず、アプリを開くのに手間がかかる。スマホで文字を打つのが得意でなく、年相応に老眼も進んでいるので、なによりもひとつの予定を書き込むのに時間がかかる。スマートフォンでアプリを開いて指先でチクチクと書き込む手間に耐えられない。その点、アナログ手帳ならノーストレス。スピードにこそアナログの優位がある。ということで、スケジュールノートを開いて予定を立て、書いたり消したりする行為を1日に何回も繰り返している。
「仕事に追われるな、仕事を追え」
ファーストリテイリングの手伝いの仕事を始めて十数年になる。自分で経営をやっているわけではないが、「門前の小僧習わぬ経を読む」。総体としての経営がどのようなものなのか、柳井正さんから多くを学んできた。
具体的な仕事の方法論についても学ぶことが多い。その一つが「仕事に追われるな、仕事を追え」――時間軸での仕事姿勢だ。仕事に追われるようになるとスケジュール管理がうまくいかないどころか、パフォーマンスが確実に低下する。こちらから攻撃的に仕事を追うという姿勢を心がけている。
例えば、今書いているこの文章がそうなのだが、原稿を書く仕事。締め切りが近づいて慌ててやるとロクなことにならない。締め切りにまでに間があるうちに書いてしまい、しばらく寝かせてから推敲作業をかけるようにしている。
仕事を追いかける状態をキープするためには、つまるところ仕事の総量の管理が大切になる。僕は一人で仕事をしているので、目の前の仕事量が自分のキャパシティを超えないようにすることがとりわけ重要だ。一定のラインを超えるような仕事は引き受けないようにしている。断るのも能力のうち、と心得ている。
仕事は「前始末」をつけよ
こちらから仕事を追いかけるようにするためには、後始末ならぬ「前始末」をつけておくに限る。これもまた柳井さんから学んだことだ。
先日、ファーストリテイリングのある役員の方と話をしているときに、なるほど……と思う話を聞いた。毎週日曜日に20分ほどかけて、次の月曜日からの1週間の仕事の脳内シミュレーションをしているという。向こう1週間のうちどのような仕事がどういう順番であり、そのために自分が何をしておくべきか、1週間分の仕事をイメージしておく。あくまでも1週間の「流れ」で考えるというのがポイントだ。「現実に月曜日からやることは僕にとって2回目の仕事です」――これぞ前始末と感心した。
1週間単位で始める「前始末」イメージトレーニング
そこまで徹底したものではないが、僕も似たようなことをやっている。その週の仕事が終わると、週末に次の1週間のスケジュールをゆっくり見て、流れのイメージを組み立てる。この歳になると、とりわけ重要なのが仕事体力の配分だ。1週間の中で負荷がかかるヤマ場がどこにあるのかを見極めて、そこに合わせてしっかり休養を取り、体調管理をするようにしている。とことん疲れる仕事があったときは、帰宅してすぐ「集中治療室」(何もやらずにひたすら横になって休む)に入る。
これを1週間単位でやる。1週間単位で仕事の量と負荷がなるべく一定の水準に収まるようにしている。ハードな日の次は少し緩くしておく。週の中で1日はテンションがかからない仕事(相手がいない仕事)だけの日を作っておくのが理想です。無理なら、半日だけでもリラックスして仕事ができる日を作る。
このイメージトレーニングは1週間単位でやるのがちょうどよい。向こう2週間や1か月となると仕事と仕事の間にある流れを具体的にイメージできなくなるからだ。目の前の1週間に集中して、次の週のことは考えない。
TO DOリストを作るという人は多い。しかし、個人的な経験でいえば、仕事をリストアップして優先順位をつけてもなかなかその通りには行かない。やり残しが気になって、かえってストレスになりかねない。何事も流れで考えるのが大切だ。