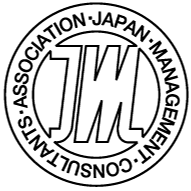ところが、今になっても、価格は下がったが支払い条件はそのままで続いているところが散見される。「○○万」以下は現金で!などが典型的だ。
結果、販売も業種によっては相当厳しい環境であり、回収サイトを短縮するわけにもいかず、支払いの現金比率だけが上がったままであれば、資金が逼迫するのは必定である。
社歴も60年と長く、知名度も財務体質もしっかりしておられた。社長のお話では、大手メーカーの代理店として拡販は当然だが、高度な技術、先進的なソリューション技術を持っておられる企業と新たな代理契約ができないだろうか?と。
省力、環境、新しい素材部品…四国県内の大手企業の業績アップに貢献できそうな商材があれば、担当がどこへでも飛んでいって話を聞きたいとまで言っておられた。
全国からすれば四国のシェアは、決して大きくなく中堅メーカーといえども、高松、松山と営業所を出すほどでもない。おのずと手薄になってしまう。
ただ、モノを流すだけでは、マージンも薄くお客様からも頼りにされない。技術陣がしっかりフォローできる強みを最大限に活かすには「新たな仕入先開拓」こそ、最大の業績向上策である。
【宣伝】 大豊産業様と連絡を取られたい方は、
作間までメールにてお問い合わせ下さい。 sakuma@jmca.co.jp
大豊産業株式会社 http://www.taihos.co.jp/