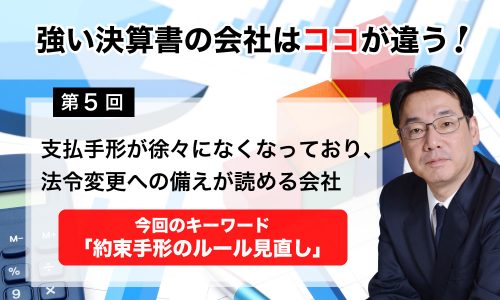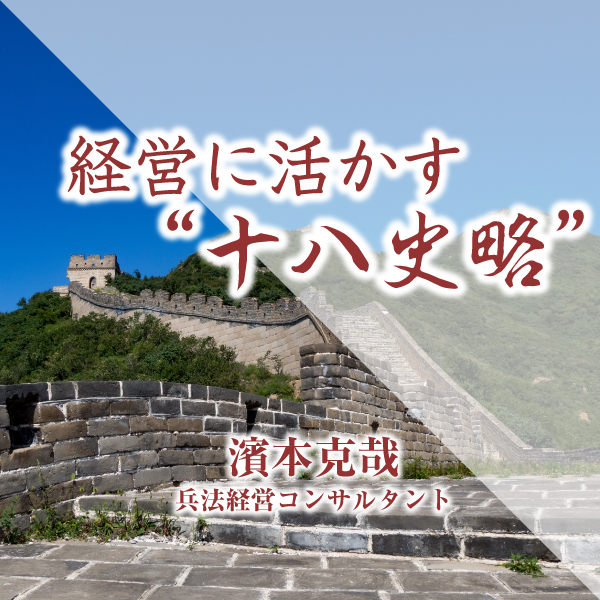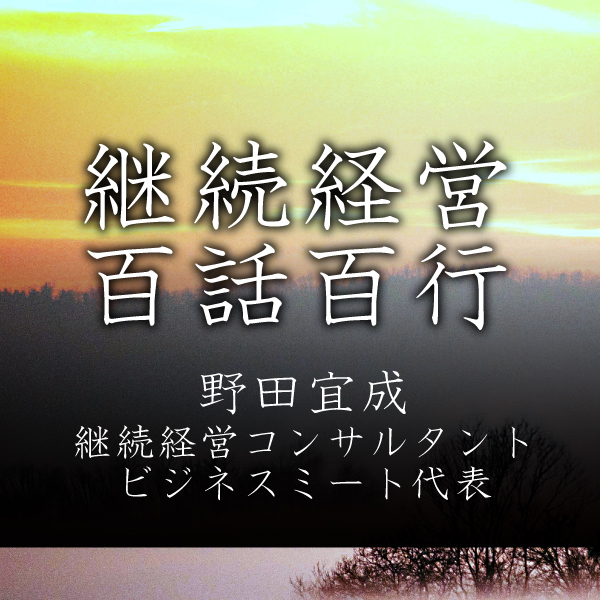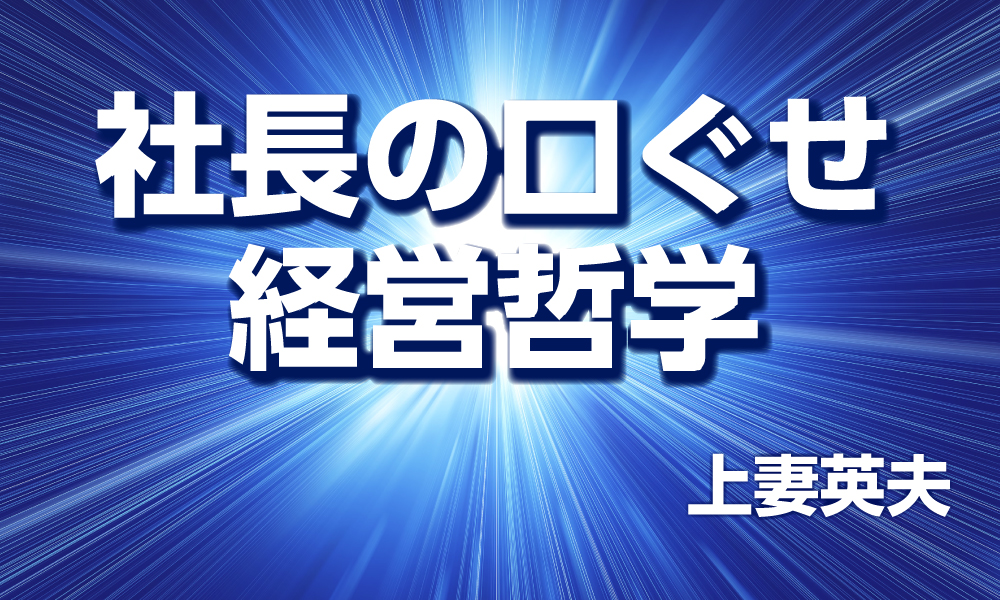日本人はどちらかと言うと「この道一筋 何十年」の生き方が好きだ。匠の技とか職業の一分野とか、若い頃から一つの分野にただ一筋に打ち込んで、その奥義を究めるところまで突き進むという生き方にある種の憧れを抱くようだ。
- ホーム
- 欧米資産家に学ぶ二世教育
- 第88回 「この道一筋」にこだわりますか?
私自身もそうした生き方が「素敵だ」と思わないではないが、自身は真逆で、頻繁に仕事を変えている。特派員助手、英語塾経営、専業主婦、同時通訳、M&A、ファンドの運営、著作やコンサルティング、講演や大学教授などなど。
兄の一人はもっと派手で、医者をしながら新薬を開発、政治家になり、オーケストラの指揮や映画作りまでに手を染めた。父は物理化学者だったが、音楽が好きで、詩をそれもドイツ語で作り、それを作曲してもらったりしていた。あちこちに気が散るという遺伝子のなせる業かもしれない。
海外の知人はとみると、「一筋は」よりは何度か仕事が変える人が多いように思える。同業にスカウトされて移るというだけでなく、知り合いのファンドマネージャーの中には元ボクサーの人もいれば、宇宙工学からの転向者もいた。
1990年代私が研究していたヘッジファンドの考案者、アルフレッド・ジョーンズという米国人はまず船のパーサーになり、大使館員になり、次がレポーター、そして雑誌の編集や執筆の仕事に就き記事を書く過程でウォ―ルストリートの予測専門家やアナリストと知り合いになる。そして自身でヘッジファンドという投資手法を編み出して資金運用者として大成功するのである。なんと5番目の仕事になる。慈善家としても尊敬されていたというから本当にカラフルな人生を送ったに違いない。
勿論社会は「一筋人間」「マルチ人間」双方を必要とする。
その人がどちらに傾くかは、就職市場の状況や性格にもよるだろうが、今後は社会の変化が益々激しくなり、また新しい発想が絶えず求められていくことを考えると、「マルチ人間」の方が有利だろうか。
人材を求めるときも「同業」ではない人を加えることは会社に「異なる視点」をもたらすことができるから、更なる飛躍に繋がるかもしれない。同様に社員の副業もその可能性を秘めているのではないだろうか。ノウハウの漏えいなど禁止する理由も分からないではないが、社員が新たなスキルや経験を身に付けることは決して本業にとっても不利なことではないと思うのだが。
ライフスタイルアドバイザー 榊原節子