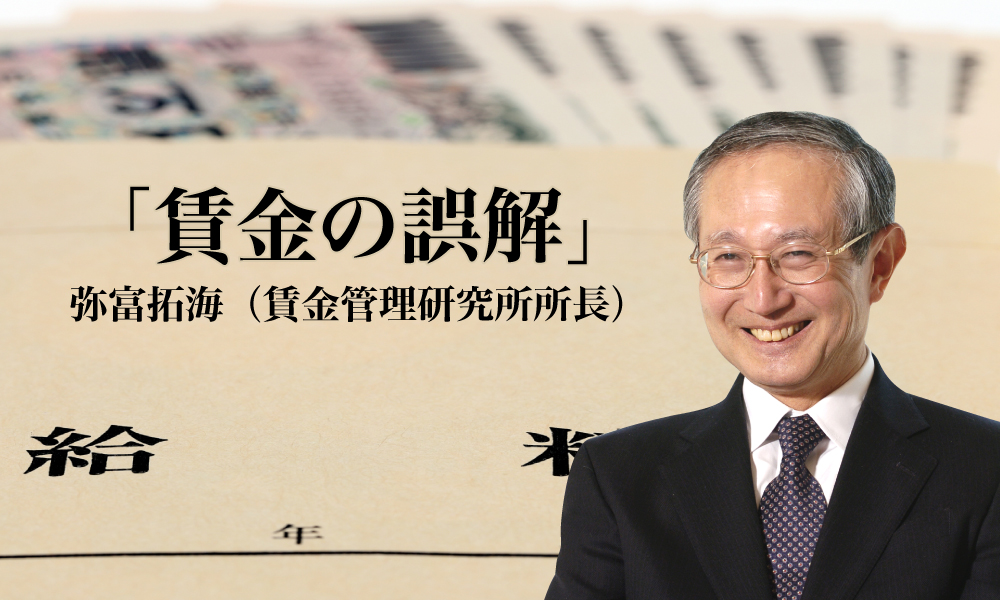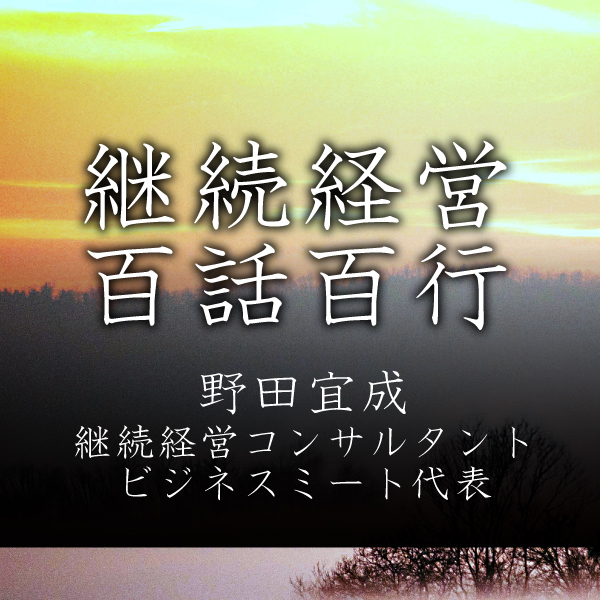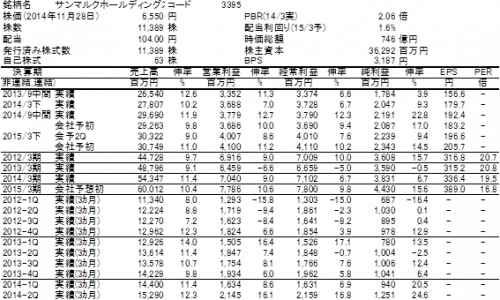最高裁まで争われた「長澤運輸事件」に代表されるように、継続雇用制度における嘱託再雇用時の給与決定に再び関心が集まっています。今回は改めてこの問題を考えてみましょう。
高年齢者雇用安定法で65歳までの継続雇用が義務化されたとき、大企業を中心に満60歳定年到達時の60~70%程度に賃金を減額する例が多く報告されました。
このような賃金の減額が受け入れられてきた背景として、
1) 雇用期間が延長され生涯年収が増加することに加え、職制上の責任が大幅に低下
することが多くあり、給与の減額も当然のことと考えられていたこと
2)それ以前の基礎年金部分の支給開始年齢が引上げられる段階では、再雇用時の給料
が減額されても、雇用継続給付金に加え在職老齢年金の受給も行われていたため、併給調整分を考慮しても相応の手取り額になったこと
3) 大企業では賃金水準が高いこともあって、雇用継続給付金の支給率が最大となる
「再雇用時の賃金が満60歳定年到達時の61%以下」まで引き下げても、年金受給額より大きな手取り額であったこと
などが考えられます。
中小企業でも同様に、60~70%に引き下げるケースが少なからずありました。雇用継続給付金の支給が、定年到達時賃金の75%を下回ってから開始され、61%で支給率が最大となるのですから、「それだけ引き下げても良いのだろう」と経営者が考えるのは無理もありません。
しかし、定年到達時の賃金水準は、大手と中小では大きく異なります。さらに、報酬比例部分が支給される方でも年額100万円に満たない方が多数であることを考えれば、まずは「我社の社員が生活できるだけの給料を払っていく」ことを基本とすべきです。
大手企業では組合員ベースの賃金が310,000円であるのに対して、中小企業組合員のベース賃金は245,000円ほどです。中小企業ではもともと賃金水準が低いうえに、責任の軽い他の仕事に異動させることもままなりません。継続再雇用となった後も、今までと同じ仕事(職務・責任レベルとも)を続けてもらうしかないのが実状です。
今までと同じ仕事で同じ水準の成果を期待されていながら、絶対額の少ない給料を、大企業並みに減額されたのでは、やる気はおろか生産性が低下するのは無理もないことです。
忘れてはいけないのは、「嘱託再雇用の対象社員とは、わが社を定年まで勤め上げた同志であり、いわば同じ釜の飯を食べた仲間」だということ。会社としては、その社員が年金を満額受給できるまで、働き甲斐のある仕事を与え、その仕事に見合う給料を支払い、生活に不安を感じさせないようにするのが基本です。そう考えれば、賃金の下げ幅の許容範囲もおのずと見えてきます。
嘱託再雇用後もその生産性に見合った給料を支払っているのであれば、直近の最高裁判例の判断基準を持ち出すまでもなく、「同一労働同一賃金」で揉めることはないはずです。