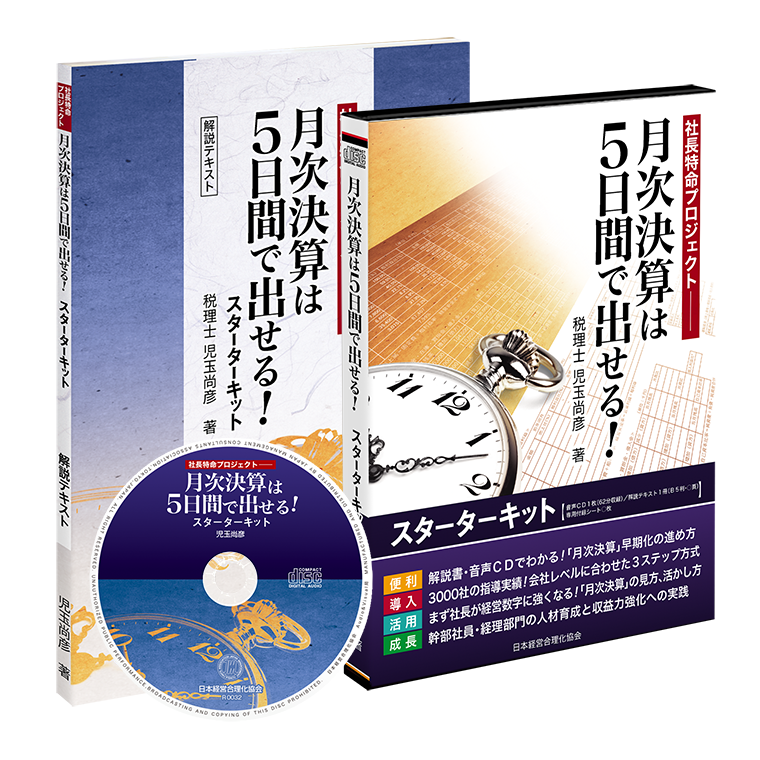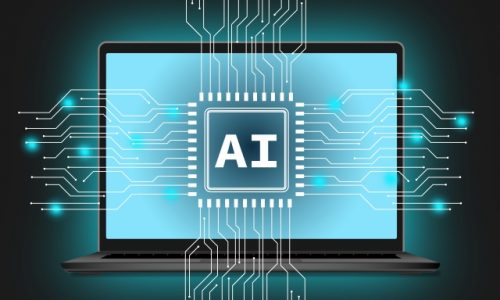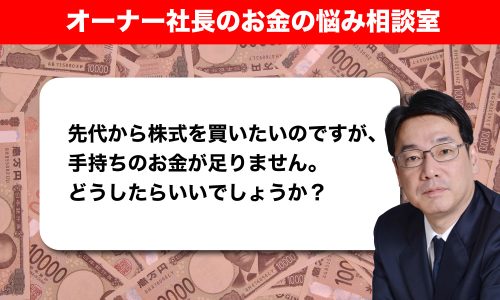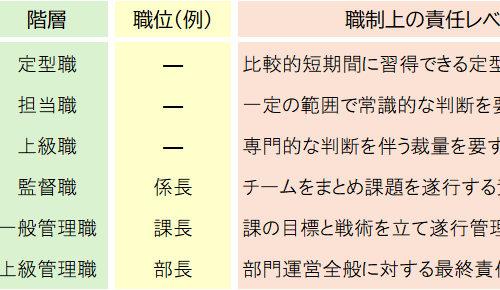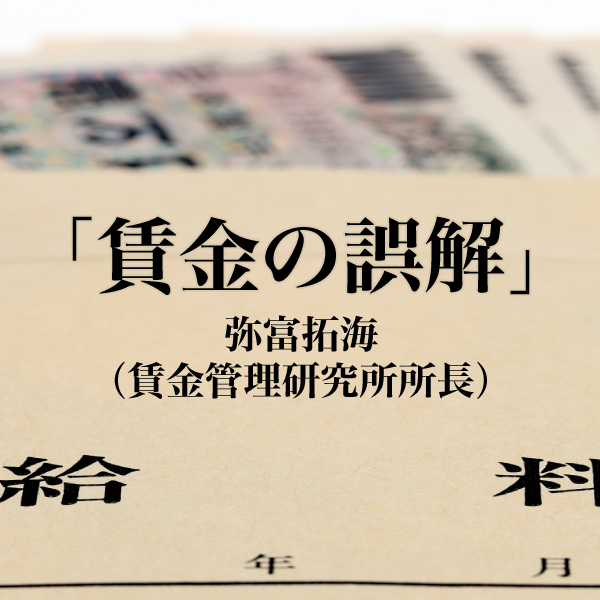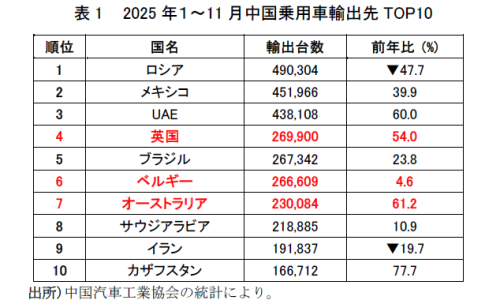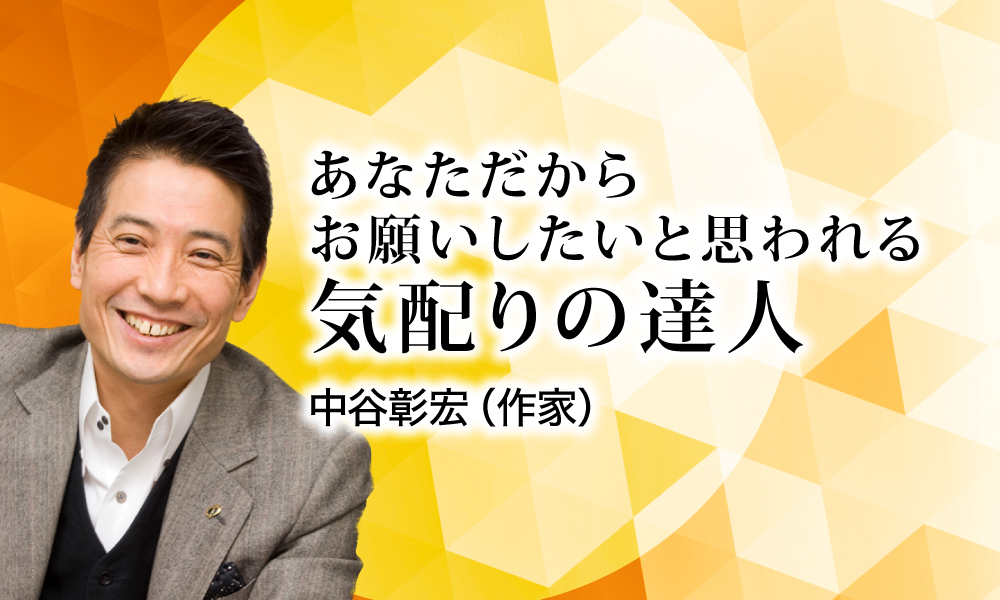2022(令和4)年1月から改正後の電子帳簿保存法が施行されます。直前になり、経理関係の書類の保存方式が紙から電子へ変わることに関して、企業経営者や経理担当者からの問い合わせが急増しています。
そこで今回は、そのなかでも最も問い合わせの多い[電子データの保管]について[関心の高い3つの項目]への対処法を説明します。
第34回のコラム「直前確認!2022年1月改正[電子帳簿保存法]」では[2021年12月末までに、絶対に確認して準備しておくべき3つのこと]について説明しています。こちらも参考にしてください。
https://plus.jmca.jp/kodama/kodama-034-2111.html
御社の経理は、電子データの保管について正しく理解していますか?
ポイント①[電子データの保存が不完全な場合]の対処法
2022(令和4)年1月からは、取引書類を紙ではなく電子取引で行った場合、原本の電子データの保存が義務付けられます。請求書や領収書をインターネット経由やEメールを利用して、PDF形式等でやりとりした場合は、その原本の電子データは必ず保存しておかなければなりません。
しかし、電子データの保管義務を取引担当者や経理担当者が知らずに、紙に印刷して処理し、電子データを保存していないケースが考えられます。
原本の電子データを保存していない場合は、電子帳簿保存法上では原則として、「必要な書類が保存されていない」とみなされます。つまり、「支払いに関する証拠書類である請求書や領収書の保存がない」として、「経費として認めない」というわけです。
また、「書類の保存がきちんとされていない」と判断されて、青色申告を取り消されてしまう危険もあります。
正常な取引を行い、会計処理も適正に行っているにもかかわらず、「電子データの保管状態が悪い」というだけで、本当に経費を否認され、青色申告まで取り消されるのでしょうか?
現実的には、すべての企業がデジタル化へ移行するには時間がかかります。特に中小企業においては、経理事務のIT対応が追いついていない会社も多く、法律上の原則的な取り扱いを当初から徹底させるのは困難です。
したがって、国税庁側も取引実態や他の書類によって取引内容が確認できる場合は、電子データの保管がないだけで経費を否認したり、青色申告を取り消したりしないことを公表しています。
御社では電子請求書を紙に印刷して保管していませんか?
ポイント②[取引明細がメール本文に記載されている場合]の対処法
これまでは、取引結果が確定した請求書や領収書は、紙の書類のイメージをPDF形式に出力して、メール添付で送受信するのが一般的です。一方で、取引途中での見積もりや注文段階でのやりとりは、メール本文に取引内容の詳細を記載することがよくあります。
このように、取引明細をメール本文に記載した場合のデータの保存はどうすればよいのでしょうか?
メールシステムによっては、データ容量の問題もあり、何年間もメールデータを保存することができない場合があります。メールサーバーの設定で一定期間を経過すると、メールが自動的に削除されることもあります。
ですので、メール本文にしか取引情報が記載されてない場合は、メール内容をPDF形式などで出力しておくことも認められています。
会社の事務管理としては、一連の取引内容が後から確認できるように、請求書や領収書の電子データと一緒に、メールの取引情報も同じ形式で保管しておくように社内で徹底しておきましょう。
御社では、見積もりや受注発注の経緯の記録はどうしていますか?
ポイント③[電子取引の税務調査]への対処法
これまでの税務調査では、会計年度ごとの伝票、総勘定元帳、請求書・見積書ファイル、領収書綴り等を会議室に用意して、紙の書類を調査官が1枚1枚調べていました。そこで取引に疑念が生じた場合には、該当する取引について経理担当者に質問し、関連する請求書や領収書のコピーの提出を求められました。
今後、紙の書類が電子化されると、税務調査のやり方も変わっていきます。伝票や帳簿、請求書、領収書が電子データになれば、税務調査はPC画面の中で行われます。
税務調査官が取引の詳細な内容を閲覧したい場合には、「取引先名」「金額」「日付」によって、次のように電子データを検索します。
「取引先A社の〇年〇月の請求書」
「△年△月の××円の領収書」
電子データが条件検索できない保管状態の場合には、税務調査官は必要な電子データをダウンロードして提出することを求めてくるので、注意が必要です。
電子データが迅速に検索閲覧できるように、経理担当者は日ごろから適切にデータを管理するようにしておきましょう。
税務調査の時に、電子データの保管状態が悪く、社員のパソコンやメールの中身まで調査範囲を広げられないようにしたいものです。
電子取引データは必要なときに速やかに検索できる状態になっていますか?
電子取引データの保存管理の準備をする
今回は、【[電子帳簿保存法]についての[質問ベスト3]】を解説しました。
ポイントは次の3つです。
①電子取引データの保存が不完全であっても、直ちに経費を否認され、青色申告が取り消されることはない
②メール本文に取引情報が記載されている場合には、メール内容をPDF形式等で出力しておく
③税務調査に備えて、電子取引データを[取引先名][金額][日付]で検索できるようにしておく
2022(令和4)年1月(電子帳簿保存法改正)以降は、すべての会社で電子取引の利用が増えることが予想されます。
早い時期に顧問の会計事務所と相談し、電子取引データの保管方式を決めて、適正に運用できるように準備してください。
電子取引対応の準備は完了していますか?
[補足]
電子帳簿保存法改正にともなう電子データの保存義務は2年間猶予されることが「令和4年度税制改正大綱」(2021年12月10日公表、自由民主党 公明党)に盛り込まれました。
第36回のコラム「【解説】電子保存の義務化、2年間猶予が確定|改正[電子帳簿保存法]」では、「企業の電子帳簿保存法の対応状況と電子データの保存の義務化が延期された理由」、そして「今後2年間で経理が取り組むべきデジタル化の準備」について説明しています。こちらも参考にしてください。
https://plus.jmca.jp/kodama/kodama-036-2112.html
【参考】
国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」(令和3年7月)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_03.pdf
国税庁「お問合せの多いご質問」(令和3年11月)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021010-200.pdf