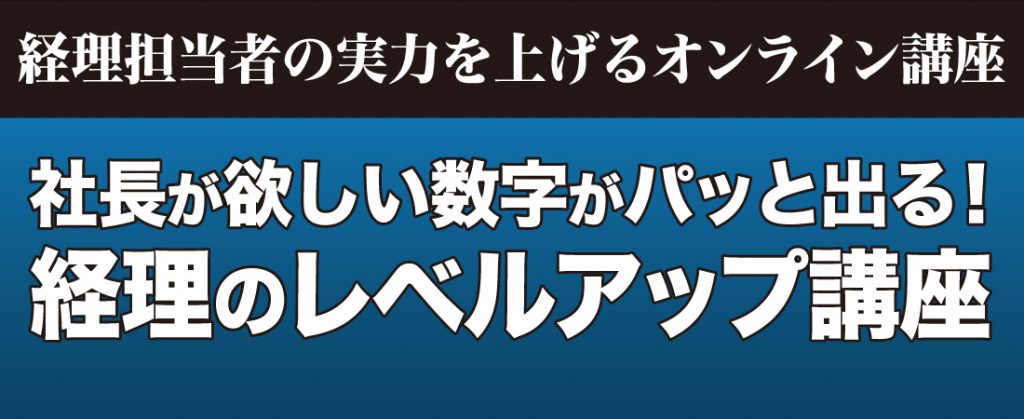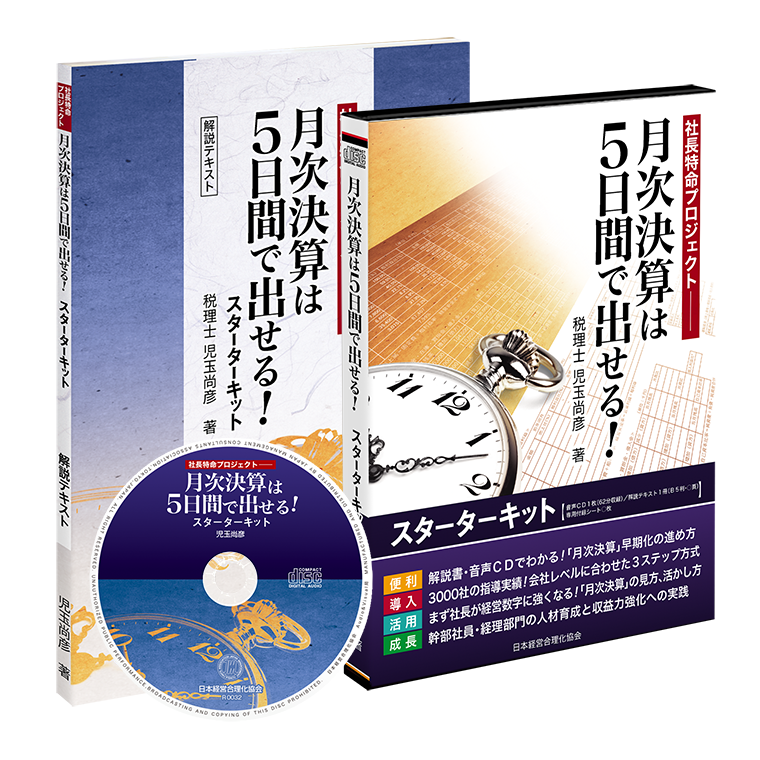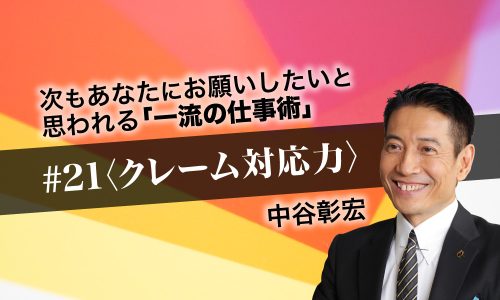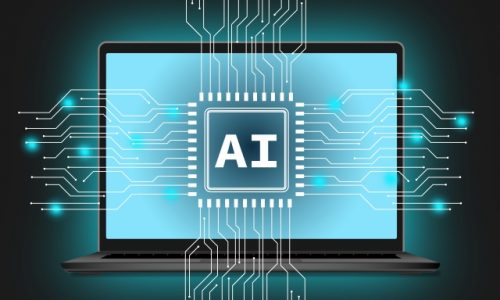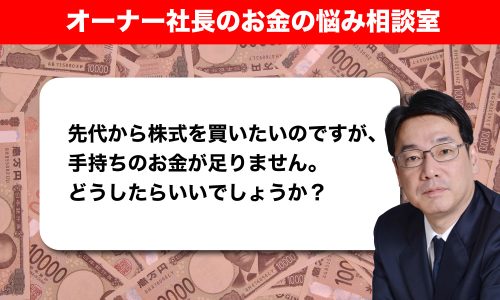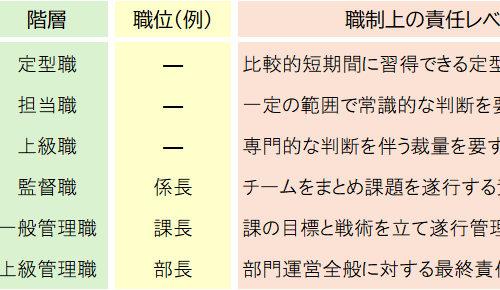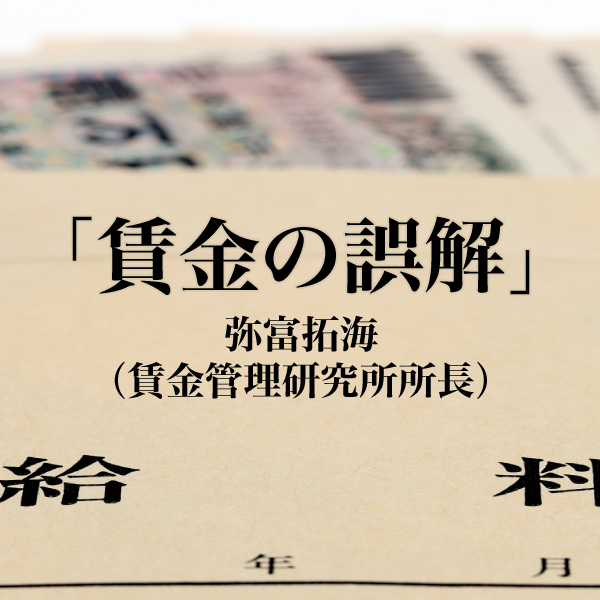2022(令和4)年1月1日、[電子帳簿保存法]の改正が施行されました。これまでは紙でしか保存が認められなかった帳簿や書類を電子化できるようになりました。
しかし開始直前になって、電子データの保存要件が緩和される事態になり、多くの企業の経理部門において混乱が生じているようです。企業の経理担当者からは次のような声が聞かれます。
「電子帳簿保存法が改正されて、結局何がどう変わったのですか?」
「これまでのやり方を続けても、問題ないですよね?」
そこで今回は、「電子帳簿保存法」の改正について、改めて経理の対応を整理しておきます。
御社の経理の電子化対応は順調ですか?
ポイント① 経理のペーパーレス化がしやすくなった
今回の電子帳簿保存法の最も大きな改正点は、税務署への承認申請なしで電子化が始められるところです。
各社の経理部門により、利用システムの状況はそれぞれ異なります。自社に合ったペーパーレスのやり方を選択することが可能です。
取引のすべてを電子データで管理するシステムを導入してからでなくても、現在利用している会計システムだけでも始められます。
部分的なペーパーレスや、段階的な電子化も可能です。紙の振替伝票の作成をやめたり、画面で見ればわかる補助簿の印刷を廃止したり、できるところから始められます。
また、ペーパーレスを試してみたけれどもうまくいかなかった場合には、元通りに紙の運用に戻しても問題ありません。
まずは、習慣的に紙に印刷していた書類から、ペーパーレス化を始めてみましょう。
試しに次の事業年度から、月次試算表の紙への印刷をやめて、PDF形式で出力して、パソコンで閲覧するようにしてみてください。
問題がなければ、徐々に他の書類もペーパーレス化し、どうしても必要なときだけ紙に印刷するように変えていきます。
必要な情報を紙で探すのと、パソコンで検索するのと、どちらが早いですか?
ポイント② 2023年(令和5年)末までは、電子取引の印刷保存も認められる
今回の電子帳簿保存法の改正でいちばん問題となったのは、電子取引データの保存についてでした。
法律上は、電子取引で受け渡しされた原本の電子データは、必ず電子的に保存することが義務付けられていました。
しかし、民間企業の対応が間に合わないこともあり、法改正の直前の2021 (令和3) 年12月になって、電子取引データの保存の義務化については、2年間猶予されることになりました。
その結果、電子取引データについても、これまでどおり、紙に印刷して保存することも認められています。
つまり、メールに添付されて受領したPDF形式の請求書などの電子取引データについては、電子データのまま保存してもいいし、紙に印刷して保存してもどちらでもいいことになりました。
したがって、各企業は2023年(令和5年)末までの2年間の猶予期間の間に、社内で電子データの管理体制を整えて移行することになります。
第36回のコラム「【解説】電子保存の義務化、2年間猶予が確定|改正[電子帳簿保存法]」では、「企業の電子帳簿保存法の対応状況と電子データの保存の義務化が延期された理由」、そして「今後2年間で経理が取り組むべきデジタル化の準備」について説明しています。こちらも参考にしてください。
https://plus.jmca.jp/kodama/kodama-036-2112.html
御社は、いつまでに電子データの管理体制を整備しますか?
ポイント③ 脱「紙の経理事務」で生産性を上げる
「これまでの紙の書類での仕事で支障がないのであれば、当分の間は電子化対応を先延ばしにする」ということでは、経営上、問題があります。
電子帳簿保存法の改正で、経理の伝票や帳簿だけでなく、注文書や見積書、請求書、領収書等を電子化する会社が増えていくからです。
情報をデジタル化すると、仕事の効率が圧倒的に改善されます。
特に経理関係の事務処理は、ほぼ100%コンピュータに置き換えられます。
紙の書類の場合は、経理社員が手に取って内容を見て判断し、コンピュータに入力し、結果を紙に印刷し、検証してハンコを押す。1枚の作業で10分以上もかかるでしょう。これを電子データで処理すると、1秒もかからずに完了します。
経理のデジタル化を促進している会社は、事務作業時間を大幅に短縮し、事務コストを削減していきます。
それに対して、これまでどおりに紙の書類で経理事務を続けていくと、生産性にどんどん差がついていくのは明らかです。
御社の経理の労働生産性は、高いですか?
経理のデジタル化で「経営格差」を勝ち抜く
2022年(令和4年)の電子帳簿保存法の改正で、会社が自由にペーパーレス化を始められるようになりました。これをきっかけにして、多くの企業が電子化に取り組みます。
電子化は義務ではありません。ですので、これまでどおり、紙の書類を中心に経理事務を継続する会社もあるでしょう。
どちらの道を選択するかは、会社の自由です。しかし自由化は、その結果として企業間に格差を生じさせます。
電子化する会社と、電子化しない会社とのあいだで、労働生産性の格差が生まれます。デジタル社会では、ITを効率よく活用した会社が生き残ります。経理の仕事についても同様です。
これからのデジタル社会において、経理のデジタル化も避けて通れない時代になりました。
社長として、自社の経理部門のデジタル化の方向性について、早めに検討を開始してください。
御社の経理は、デジタル社会の中で生き残れますか?
【参考】
国税庁「電子帳簿保存法が改正されました(令和3年12月改訂)」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021012-095_03.pdf
- - - - - - - - -
【講師セミナーのお知らせ】
社長が欲しい数字が、パッと出る経理に変わる!
「経理のレベルアップ・オンライン講座」
児玉尚彦(プロ経理育成コンサルタント)
2022年4月6日(水)~4月27日(水)【全4講】
第1講 4/6(水)《経理の自動化》経理処理のスピードアップ・効率化の実現
第2講 4/13(水)《財務分析力》 中小企業に必要な財務分析の基本を身につける
第3講 4/18(水)《資金計画力》 強い会社の資金繰りの管理手法を覚える
第4講 4/27(水)《経理が覚えるべき財務戦略》会社を良くする財務改善提案
形式:オンライン講座
全講 14:00開始~15:30終了 ※復習用動画あり(4月中限定)
▼ 詳しくは日本経営合理化協会サイトをご覧くださいませ
https://www.jmca.jp/semi/S224454